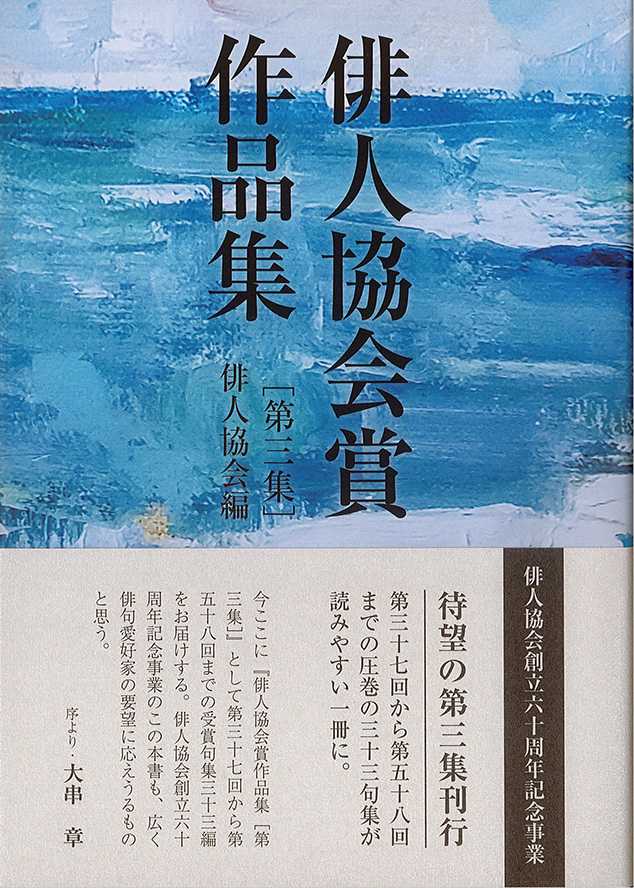『俳人協会賞作品集 第三集』を読む①
俳句αあるふぁ編集部
俳人協会は年に一度、協会員の優れた句集に対して俳人協会賞を与えています。句集は発行部数が少なく、時間が経つと入手困難になりますが、協会では従来から節目の年ごとに、受賞句集を集成した作品集を刊行してきました。今回刊行された『俳人協会賞作品集 第三集』は、平成9~30年度までの33冊(同時受賞あり)を収めます。平成時代の大部分にあたるこの時期の受賞作が並んでおり、平成の俳句とはどのようなものだったか、おのずからふり返ることができます。本連載では、全4回にわたって、トピックごとに受賞句集を読み解いていきます。
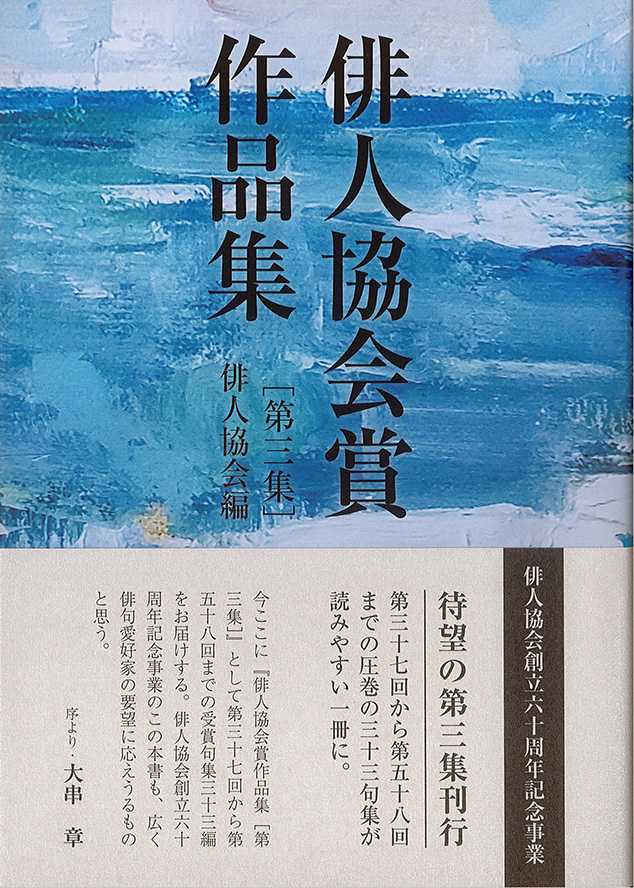
■諧謔と抒情の時代
作品集として集まった33冊の句集を通読して、まず気づかされるのは、諧謔を基調とした句集の多さです。
嚔して俳壇諸氏の中にをり(鈴木鷹夫『千年』平成16年)
微量とは致死量のこと春の宵(同)
かりがねの百の着水ぶつからず(今瀬剛一『水戸』平成19年)
前進あるのみ稲刈機進みけり(同)
熱き夜もありけむ雛を納めけり(辻田克巳『春のこゑ』平成23年)
黄金週間屋上も駐車場(同)
養生訓ちりばめてある日記買ふ(伊藤伊那男『然々と』平成30年)
有難く泣かせてもらふ初芝居(同)
今回の作品集の収録時期からは外れるため、気づきにくくなっていますが、俳人協会賞といえば、平成初期に、俳壇を驚かせた大きな出来事がありました。平成2年に第1句集『蕩児』で俳人協会新人賞を受賞したばかりの中原道夫氏(昭和26年生まれ)が、その後まもなくの平成6年、第2句集『顱頂』によって、異例の若さで俳人協会賞を得たのです。同時受賞は大正7年生まれの皆川盤水氏、翌年の受賞者は昭和4年生まれの綾部仁喜氏と大正7年生まれの吉田鴻司氏でしたから、中原氏の受賞がいかに異例であったかがわかります。
ちなみに中原氏が俳人協会新人賞を受賞した平成2年といえば、蛇笏賞を角川春樹氏が、現代俳句協会賞を池田澄子氏が得た年で、いずれも話題の受賞でした。平成元年には「伊藤園お~いお茶新俳句大賞」がはじまり、平成3年には「俳句」誌で〈結社の時代〉という有名なスローガンが提示されました。平成に入ってすぐ、俳句をめぐる環境は大きく変容していったのです。
思えば、滑稽に対する評価が高まったのは、平成の序盤における中原氏の存在が大きかったのかもしれません。中原氏、鈴木氏、今瀬氏はともに能村登四郞門下ですから、登四郞の影響力と言い換えてもいいでしょう。「俳壇」という共同体をやや皮肉めかして面白がる鈴木氏、「前進あるのみ」という俗な言い方と「けり」という古典語の言い方を同居させる今瀬氏、どちらも、このころの俳句界ではまだもの珍しい俳句を提示する存在だったはずです。
同時に、秋元不死男・山口誓子門の辻田氏、皆川盤水門の伊藤氏という異なる出自を持った二人が、同様に諧謔を志向する作風を示したことは、それぞれの師風に通じるところもあるとはいえ、平成という時代の特徴と感じられます。 一対の夫婦である雛人形の「熱き夜」を空想するのも、新年のお芝居の「ありがたさ」をことさらに強調するのも、強烈に通俗的で、だからこそ面白いのです。
こうしたトーンの作者としては、現代俳句協会に属した大牧広氏も登四郞門でした。その弟子として出発した櫂未知子氏が俳人協会賞を受賞しています。〈誰からも見えて蠅取リボンかな〉(櫂未知子『カムイ』平成29年)のような句を上記の句と並べてみると、その接続性が窺えます。『カムイ』は滑稽ではなく、むしろ〈卒業や見とれてしまふほどの雨〉〈いちじくの火口を覗く夜なりけり〉など峻険な抒情を主とする句集ですが、上に挙げた句集にも抒情の句が散見されます。
夕櫻やがて夜汽車となる窓に(鷹夫)
パラソルの中に母ゐる渚かな(剛一)
夾竹桃楸邨も人憎めりき(克巳)
ラガーらの負け銭湯の湯を減らす(伊那男)
滑稽と抒情は、知的な態度で心理の機微を発見するという点で、近いところにあるのです。
抒情といえば、抒情句の名手だった大野林火門からは二人が受賞しています。
ほろびしもの折々雪に目覚めけむ(宮津昭彦『遠樹』平成9年)
桐の実を花のごとくに灯が照らす(同)
雪渓へ音楽室の窓ひらく(大串章『大地』平成17年)
流星は旅に見るべし旅に出づ(同)
雪のつめたさにかの世から覚醒する「ほろびしもの」、やわらかな灯火によって花のような印象を醸す桐の実、子どもたちの歌声と大自然をつなげる窓、流星を見るためだけの旅。素朴で甘やかな言葉の連なりは師ゆずりといえるでしょう。
もっとも、諧謔と抒情だけが平成の俳句の特質ではありません。次回は、受賞者の師系に注目しながら、作品の諸相を見ていきます。(編集部)
-
22-12-05『俳人協会賞作品集 第三集』を読む④
【4】有季定型の成熟
-
22-12-05『俳人協会賞作品集 第三集』を読む③
【3】地方の視点
-
22-12-03『俳人協会賞作品集 第三集』を読む②
【2】昭和俳句の残響
-
22-12-02『俳人協会賞作品集 第三集』を読む①
【1】諧謔と抒情の時代