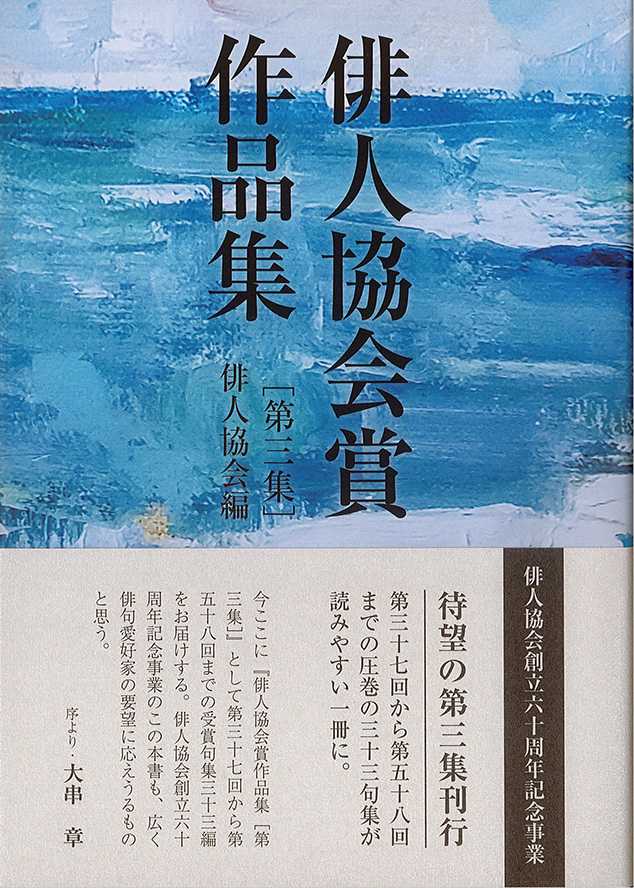『俳人協会賞作品集 第三集』を読む③
俳句αあるふぁ編集部
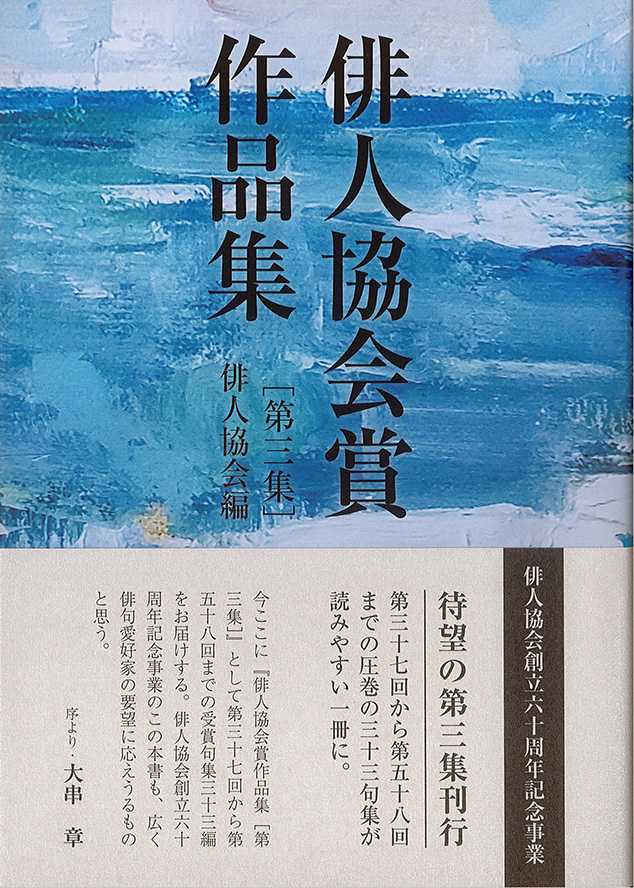
【3】地方の視点
1950年代の俳壇では、地方在住の俳人に注目が集まり、「風土」がキーワードになったことがありました。それは「運動」とも呼べる現象であり、やがて沈静化していきました。しかし、もちろんのことですが、地方の俳句が消滅したわけではありません。地方在住の精力的な個々人に光を当てたことも、平成期の俳人協会賞が果たした役割の一つでした。
月に脱ぐシャツの農薬くさきかな(本宮哲郎『日本海』平成12年)
山眠りをり日本海溢れをり(同)
本宮氏は新潟の地で農業に携わりながら作句した俳人でした。1句目は、「農薬くさきシャツ」に自分のアイデンティティを見出し、そのシャツを月下の光に持ち出すことで詩として昇華した句です。2句目は表題句で、「日本海」という地名が持つさまざまなイメージを「溢れる」という動詞で表現し、海と対になる山と取り合わせ、日本海側の長い冬を表現しています。
黒土の畝たかく春去り行くも(若井新一『雪形』平成26年)
雪壁の繫がり合へる地縁かな(同)
世代は違いますが、若井氏もまた、新潟で農業を生業としている俳人です。農の実感や風土が刻印された句には独特の光があります。
俳人協会は、有季定型を重視する組織です。そして季語の多くは、かつて和歌が文芸の中心だった時代、京の都で育てられた雅な言葉に淵源があります。江戸時代以後は、京都以外の都市、特に江戸の生活実感が季語として吸収され、文芸の中心自体も、江戸、東京へと移っていきます。人口密度の関係もあり、現在、俳壇といわれる俳人たちの共同体もまた、東京を中心としているのが現状です。
いわば季語、あるいはその本意と呼ばれる言葉のイメージは、各時代の都市部で形成されていくという性質があります。
地方在住の俳人の俳句は、その意味で、季語というものの性質を相対化し、押し広げてゆくものです。たとえば、海と山とが向かい合ってそれぞれに存在感を放つ本宮氏の〈山眠りをり日本海溢れをり〉は、漢詩に由来する「山眠る」という季語のイメージを塗り替えています。若井氏の〈雪壁の繫がり合へる地縁かな〉は、「雪壁」という土地の言葉を季語として用いたものです。
地方色が色濃い句集は他にもあります。
葉の裏の白があざやか若牛蒡(茨木和生『往馬』平成13年)
人参の花の汚くなりゐたり(同)
雪深し鯉の機嫌を見にゆかな(藤本安騎生『深吉野』平成15年)
集め来し米に穀象愛宕講(同)
ともに右城暮石に師事した二氏の、奈良に根付いた句集。自然に近い生活から生まれたたおやかな句が並びます。
茨木氏の二句は、生長中の野菜の様子を写生したものですが、「若牛蒡」「人参の花」に注目した写生句は少なく、題材の選択自体に驚きがあります。藤本氏の1句目は、養鯉農家の多い地方の、ある冬の一夜を描いたつげ義春の短編「ほんやら洞のべんさん」も連想される風趣ですが、こうした情景は作者にとって身近なものだったのではないでしょうか。
敦賀より北に用ある時雨かな(山本洋子『夏木』平成23年)
室生寺へ行くかと問はれ春の風(同)
山本氏は関西の地名を詠みこんだ秀句の多い俳人です。「敦賀より北に用ある」「室生寺へ行くかと問はれ」といったフレーズは、他の地名・寺号と替えが効かず、巧みです。氏の句には、関西の歴史に根付いた言葉の感覚が貫かれています。
「敦賀より北に用ある」ことなど滅多になく、場面設定から面白いのですが、それに加えて、季語「時雨」が効いています。「時雨」は西日本の美意識を代表する季語。京都出身の飯島晴子は「関東の時雨は田舎時雨である」と言ったとか。
前回挙げた柏原眠雨氏は宮城県在住の俳人で、東日本大震災ののち、被災の惨状を見て回ったといいます。氏の『夕雲雀』は、〈避難所に回る爪切夕雲雀〉等、震災詠を収めた句集でもあります。震災を経て東北在住の俳人に注目が集まったのも、平成俳句の一場面でした。(編集部)
-
22-12-05『俳人協会賞作品集 第三集』を読む④
【4】有季定型の成熟
-
22-12-05『俳人協会賞作品集 第三集』を読む③
【3】地方の視点
-
22-12-03『俳人協会賞作品集 第三集』を読む②
【2】昭和俳句の残響
-
22-12-02『俳人協会賞作品集 第三集』を読む①
【1】諧謔と抒情の時代