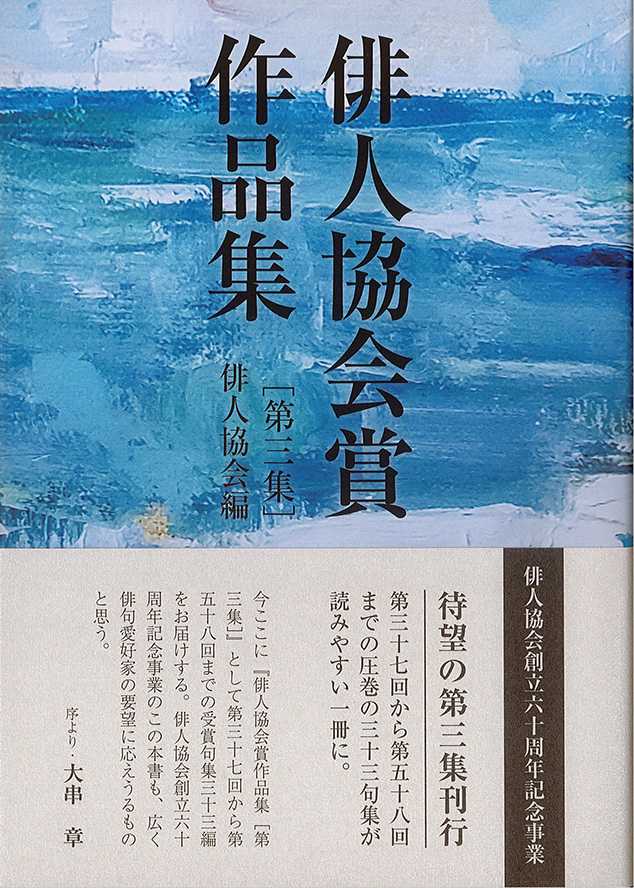『俳人協会賞作品集 第三集』を読む④
最終回
俳句αあるふぁ編集部
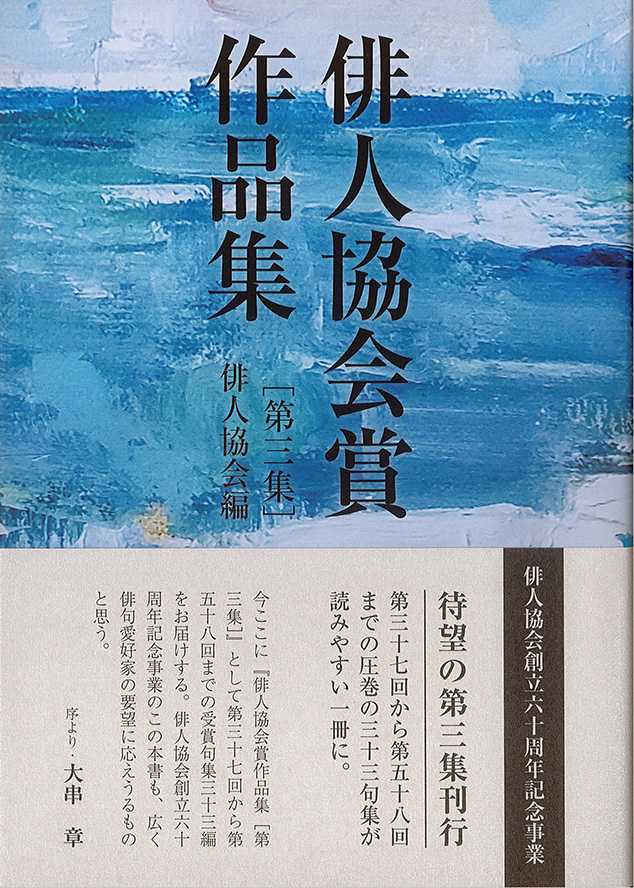
【4】有季定型の成熟
俳人協会は有季定型を重視する立場にあります。ということは、会員の優れた句集を顕彰する俳人協会賞の受賞作は、優れた有季定型の俳句と出合える一冊ということもできるでしょう。平成時代、有季定型の俳句は、どのように成熟していったのでしょうか。
浜菅の切尖のはや萌えにけり(清崎敏郎『凡』平成9年)
鴨のゐて鴛鴦はをらずやをりにけり(同)
供花の屑捨つるもひそか盆の寺(斎藤夏風『辻俳諧』平成22年)
初花のさがり枝檜葉に及びけり(同)
清崎氏は富安風生、斎藤氏は山口青邨に師事した伝統派の俳人です。風生も青邨も高浜虚子に学び、昭和期の伝統俳句を支えた代表的な大家。清崎氏も斎藤氏も、広くいえば「ホトトギス」系に属するといえるでしょう。
萌えはじめる浜菅の先端、いかにも鴛鴦のいそうな水辺、盆の時期の寺の雰囲気、隣の檜にうちかかる桜の枝……。小さなことをこと細かに言葉にしていく写生という価値観のなかで、まだこんなに新しいことが詠めるのかと驚かされます。
同じ伝統俳句でも、大峯あきら氏は、〈日蝕の風吹いてゐる蓬かな〉〈金星の生まれたてなるとんどかな〉(『宇宙塵』平成13年)など、文体と季語の工夫によって、伝統俳句で詠むことができる対象の領域を拡張しました。「日蝕」と「蓬」、「金星」と「とんど」という異質なものが、1句の中でゆるやかにつながり、鮮烈な印象をつくりだしています。
かがみ見る草のいとなみ涅槃西風(加藤三七子『朧銀集』平成9年)
暗く立つ京のはづれの茅の輪かな(同)
襖絵の嵐気匂へり鑑真忌(西村和子『心音』平成18年)
夷売よつてたかつてさは売れず(同)
諡(おくりな)は昭和紅梅はなれ見る(淺井一志『百景』平成20年)
こゑのなき嶽むらがれる大暑かな(同)
どれも重厚で、珠玉のような句です。いかにも言語化の難しそうな情景や情感を、「暗く立つ」「さは売れず」「はなれ見る」といった巧みな言葉で掬い取っており、熟練の技を見る思いがします。
具象を超えた句の凄みにも驚かされます。「草のいとなみ」「襖絵の嵐気」「嶽むらがれる」といった幻視のような把握が、端正な韻律に載せられており、格別の感動を催します。
男らに畏友盟友初鰹(片山由美子『香雨』平成24年)
手紙よく書きたるむかし青葉木菟(同)
「男らに畏友盟友」「手紙よく書きたるむかし」のような、意外さと共感を同時に呼ぶ思考の一端を12音のフレーズで鮮やかに取り上げ、つかずはなれずの季語と取り合わせるという手法は、平成の俳句のスタンダードのひとつ。片山氏はこの手法に関しては俳壇随一の技量の持ち主ではないでしょうか。
こうしたフレーズ型の句は、多くの俳人が試みるところであり、いまなお洗煉に洗煉が重ねられています。この方法の洗煉がどのように進んでいるかは、50歳以下の協会員に与えられる俳人協会新人賞の受賞作とあわせ見ることで、より鮮明になってくるかもしれません。
以上、作品集に収められた全ての句集に触れつつ、その個性を考えてきました。平成という時代とともに歩んだ名句が目白押しで、その豊かさには何度も驚かされます。現在では入手困難になっている句集も多く、資料としての価値も高い一冊です。俳句に本格的に取り組みたい方は、ぜひ触れてみることをおすすめします。(了・編集部)
-
22-12-05『俳人協会賞作品集 第三集』を読む④
【4】有季定型の成熟
-
22-12-05『俳人協会賞作品集 第三集』を読む③
【3】地方の視点
-
22-12-03『俳人協会賞作品集 第三集』を読む②
【2】昭和俳句の残響
-
22-12-02『俳人協会賞作品集 第三集』を読む①
【1】諧謔と抒情の時代