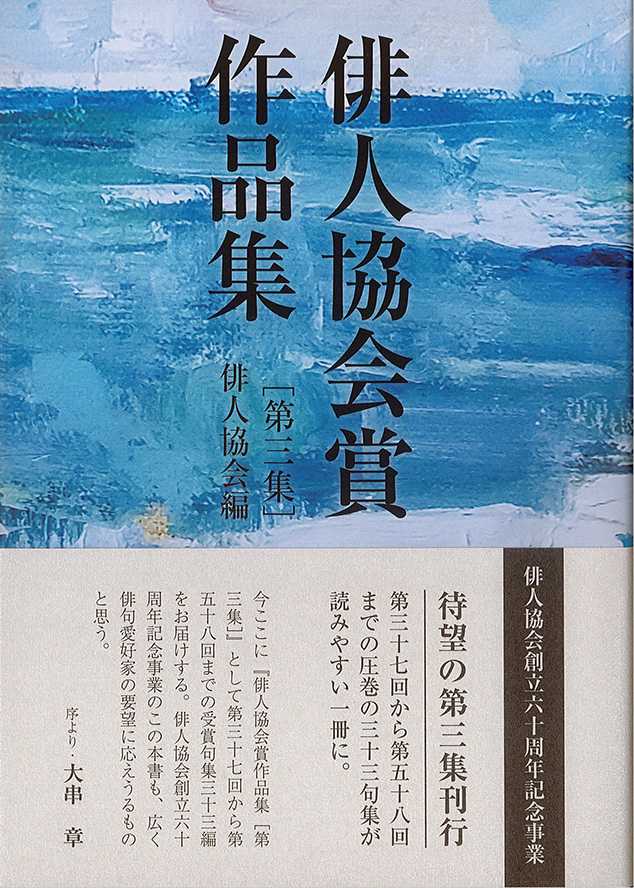『俳人協会賞作品集 第三集』を読む②
俳句αあるふぁ編集部
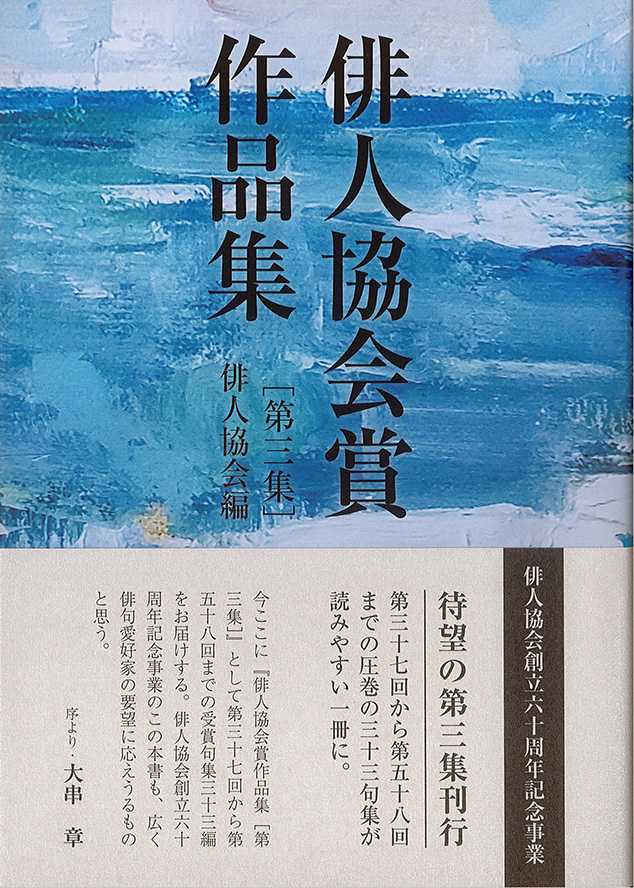
【2】昭和俳句の残響
前回、諧謔と抒情という二つのトピックを考えるうえで、師系について触れましたが、平成期に俳人協会賞を受賞した俳人の多くは、昭和を彩った大俳人たちの直弟子でした。わけても「鶴」から出発した俳人の存在感は大きかったと思われます。
春雪の樫の面テとなりにけり(石田勝彦 『秋興』平成11年)
鰰に映りてゐたる炎かな(同)
うすらひのうごいて西国へむかふ(今井杏太郎『海鳴り星』平成12年)
はくれんの花のまはりの夜が明けぬ(同)
ひたひたと来て雁風呂を燻べ足しぬ(大石悦子『有情』平成24年)
萩見せうと兄人が許のわらべ来る(同)
三氏は石田波郷・石塚友二らの「鶴」の系譜です。三氏の句柄はどれも異なるものですが、それぞれ平成の俳句の一典型となり、多くの追随者を生みました。
たとえば、石田氏の端然として明快な詠みぶりは、『郊外』(平成3年)で俳人協会新人賞を受賞した直弟子の千葉皓史氏や、『秋の顔』(平成9年)で同賞を受賞した息女の石田郷子氏をはじめ、平成の前半に活躍しはじめた俳人たちの、さっぱりとした、そしてライトな文体の、一つの源流になっているように見受けられます。
意味が希薄でつかみどころのない今井氏の独特の文体は、鳥居三郎、飯田晴、茅根知子、仁平勝、鴇田智哉の各氏をはじめとして、主宰誌「魚座」に集った俳人に受け継がれました。結社外にも句集の愛読者が多く、平成30年には待望の全句集『今井杏太郎全句集』が刊行され、好評を博しました。
大石氏の典雅な句風は、平易さを好む同時代の俳句の中では異質で、昭和俳句と比べてさえ高踏的ですが、昨今、20~30代の俳人の間で湧出している古典志向との親和性が高く、一つの範を示しているともいえます。
山国の夕日厚かり冷し瓜(黛執 『野面積』平成15年)
しばらくは代田に映る柩かな(同)
わらんべの顔拭いてゐる桜かな(大嶽青児『笙歌』平成19年)
鯉のぼりたためば草のかをりかな(同)
菜の花や佛参りに姪つれて(伊藤通明 『荒神』平成20年)
うつくしき加賀の手毬を枕上ミ(同)
久保田万太郎・安住敦・成瀬桜桃子らの「春燈」からも次の三氏が受賞しています。それぞれ主に安住敦時代の「春燈」に学んだ俳人です。
共通するのは、平易でありながらも芯があり、格調高さが感じられること。先ごろ随想集『桜新町だより』を刊行した西嶋あさ子氏も安住敦に師事した俳人で、氏の句からも同様の印象を受けます。このような文体もまた、平成俳句の収穫の一つではないでしょうか。
寒水に洗ひ出されし砂鉄かな(林徹『飛花』平成12年)
庖丁を買ふせんだんの実の下で(同)
第九聴き凶作の年暮れんとす(栗田やすし『海光』平成21年)
ふち焦げし原爆の日の目玉焼(同)
立つ浪の懐暗し十二月(柏原眠雨『夕雲雀』平成27年)
避難所に回る爪切夕雲雀(同)
こちらは沢木欣一の「風」に学んだ三氏。林氏の句の、「砂鉄」や「庖丁」のインパクトが視覚的に感じられる即物性、栗田氏の、「第九」と「凶作」、「焦げ」と「原爆」といった取り合せから繰り出される硬質なイメージ、柏原氏の現実を直視する視線のありかた、句風は三者三様ですが、戦後俳句を切り開いた沢木欣一の詩魂のおもかげが感じられます。
師系に注目するならば、〈狂ひても妻がよかりし螢追ふ〉〈鬼灯市一と鉢に風つれて出づ〉(『貴椿』平成13年)など情緒の言語化に優れた句を詠んだ神蔵器氏は石川桂郎門、〈松韻も雀隠れやこの辺り〉〈翁忌の明くれば霜の嵐雪忌〉(『祭詩』平成21年)など重厚な句風を展開した榎本好宏氏は森澄雄門、〈観潮の言葉まづしくなりきたる〉〈初夢の湯殿に遇ひし比奈夫翁〉など軽重を問わず自在に言葉の世界を往き来する山尾玉藻氏は岡本圭岳・差知子の息女です。
俳句を読むときに師系の影響を取り沙汰するのは安易だという考え方もあるかもしれません。しかし、平成期に俳壇をリードした俳人の多くが、昭和期の大俳人の謦咳に接した経験から出発していることには、大きな意味があるはずです。それぞれの句の中に昭和俳句の残響を聞くのはあながち無益なこととは思われません。
〈昭和の日サイタサイタといつか老い〉〈杳として三月十日以後の祖母〉などを収める『銀座の歩幅』(平成28年)で受賞した須賀一惠氏は、〈コスモスや水漬く屍もそよぐらむ〉〈軍隊手牒開かば寒き炎の立つや〉などを収める『胡蝶』(平成17年)で受賞した鍵和田秞子氏の「未来図」で長く活躍した方です。
須賀氏は、受賞時の俳壇的な知名度が高かったとは必ずしもいえませんが、 俳人協会賞を得るにふさわしい作家として、しっかりと評価されました。それが、この賞の懐の広さといえるかもしれません。
平成20年代には小規模で対等な同人グループの結成が年代を問わず増加しましたが、かつて俳句というジャンルは、師からの技術と俳句観の継承によって発展し、そのサイクルによって俳壇という場所が成熟してきたという側面がたしかにありました。
次回は、地方の視点から考えます。(編集部)
-
22-12-05『俳人協会賞作品集 第三集』を読む④
【4】有季定型の成熟
-
22-12-05『俳人協会賞作品集 第三集』を読む③
【3】地方の視点
-
22-12-03『俳人協会賞作品集 第三集』を読む②
【2】昭和俳句の残響
-
22-12-02『俳人協会賞作品集 第三集』を読む①
【1】諧謔と抒情の時代