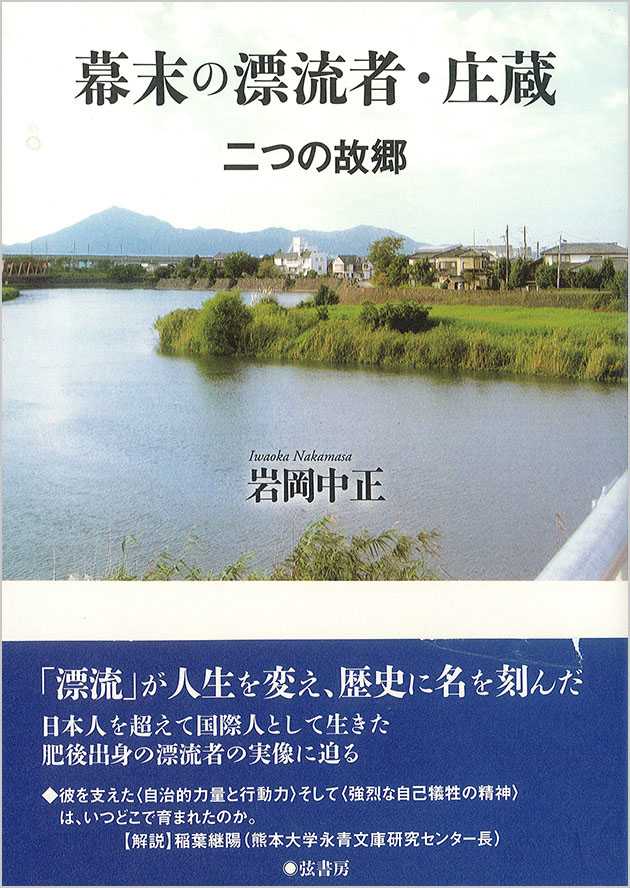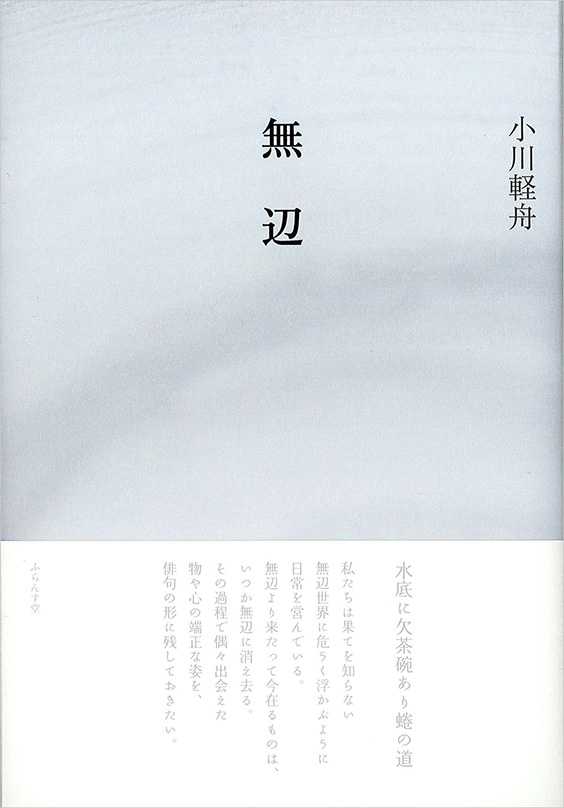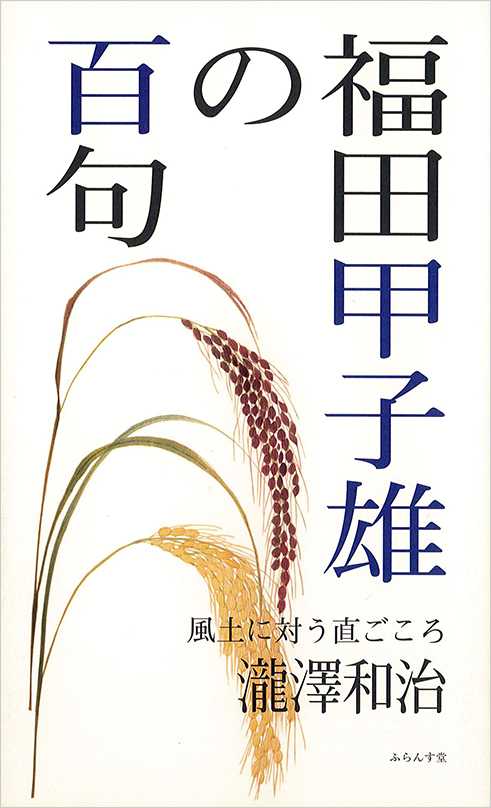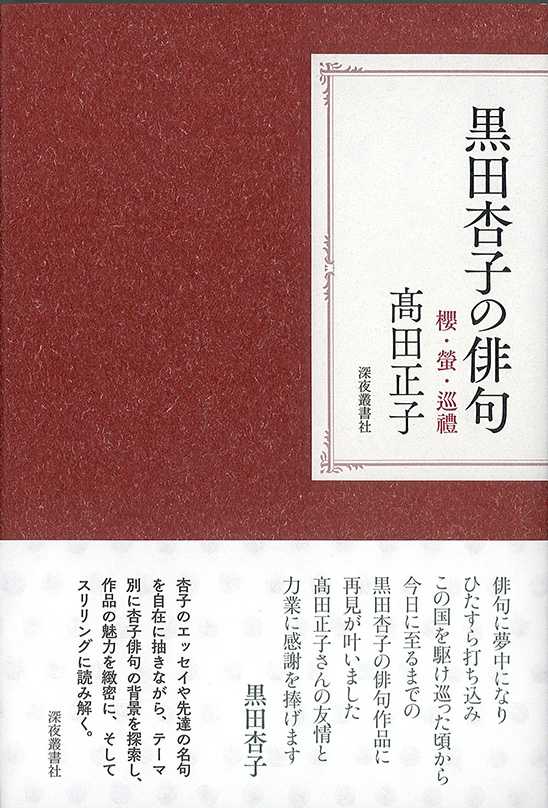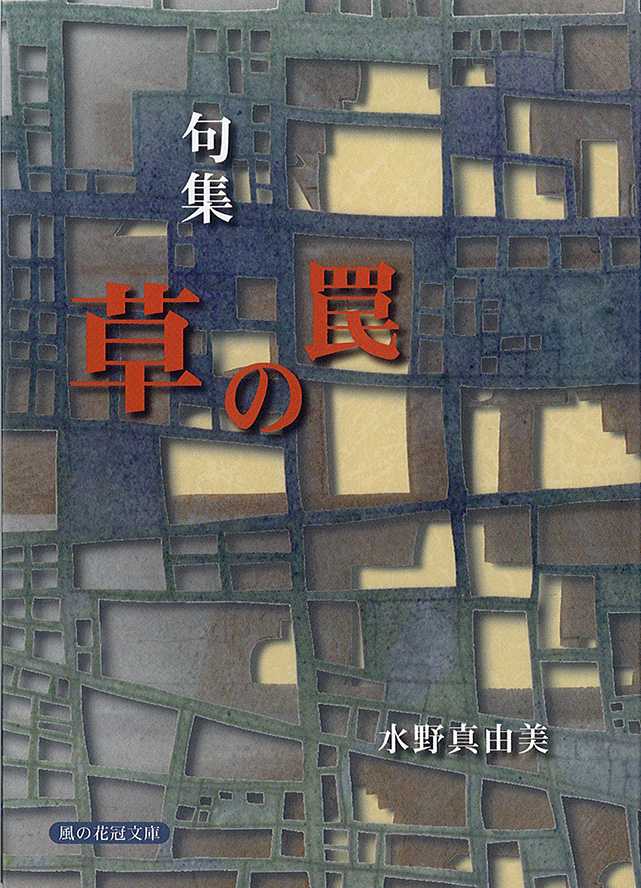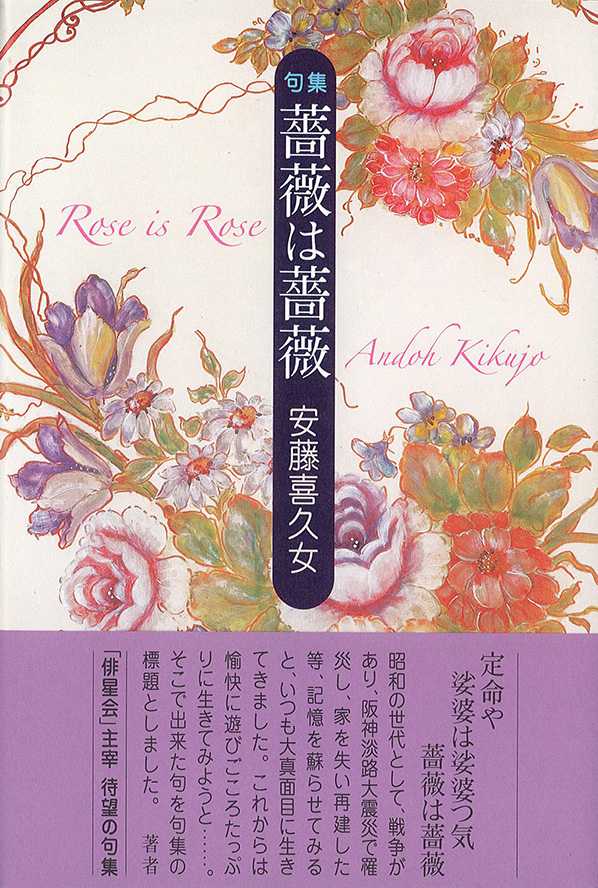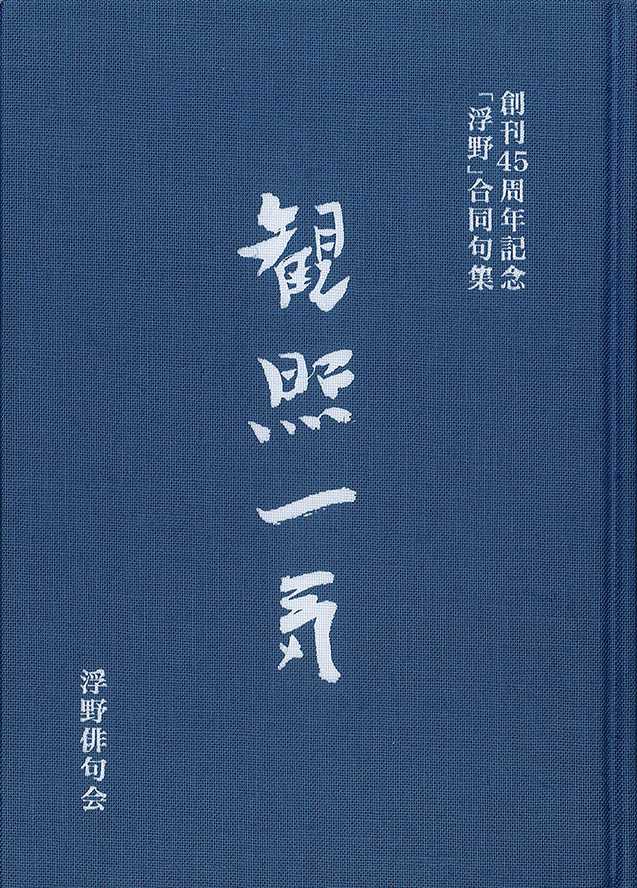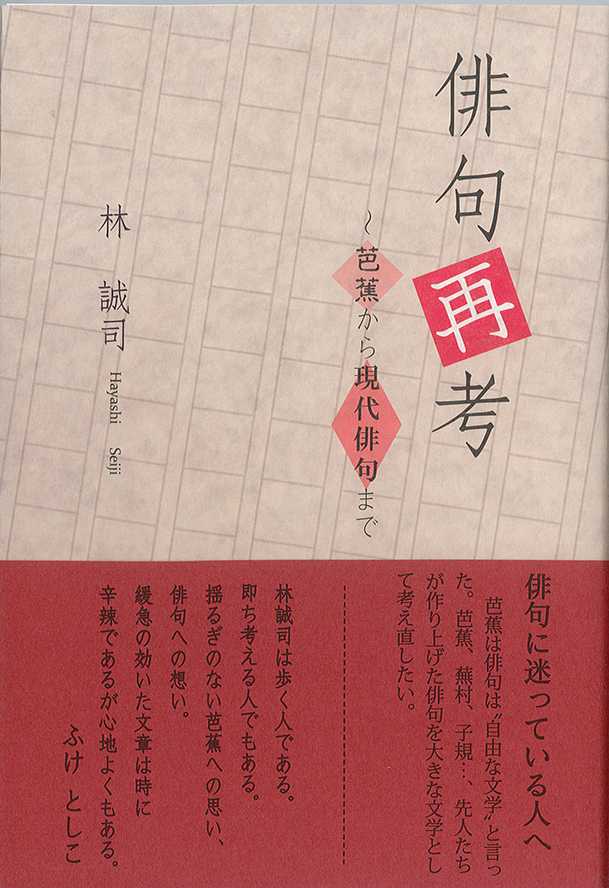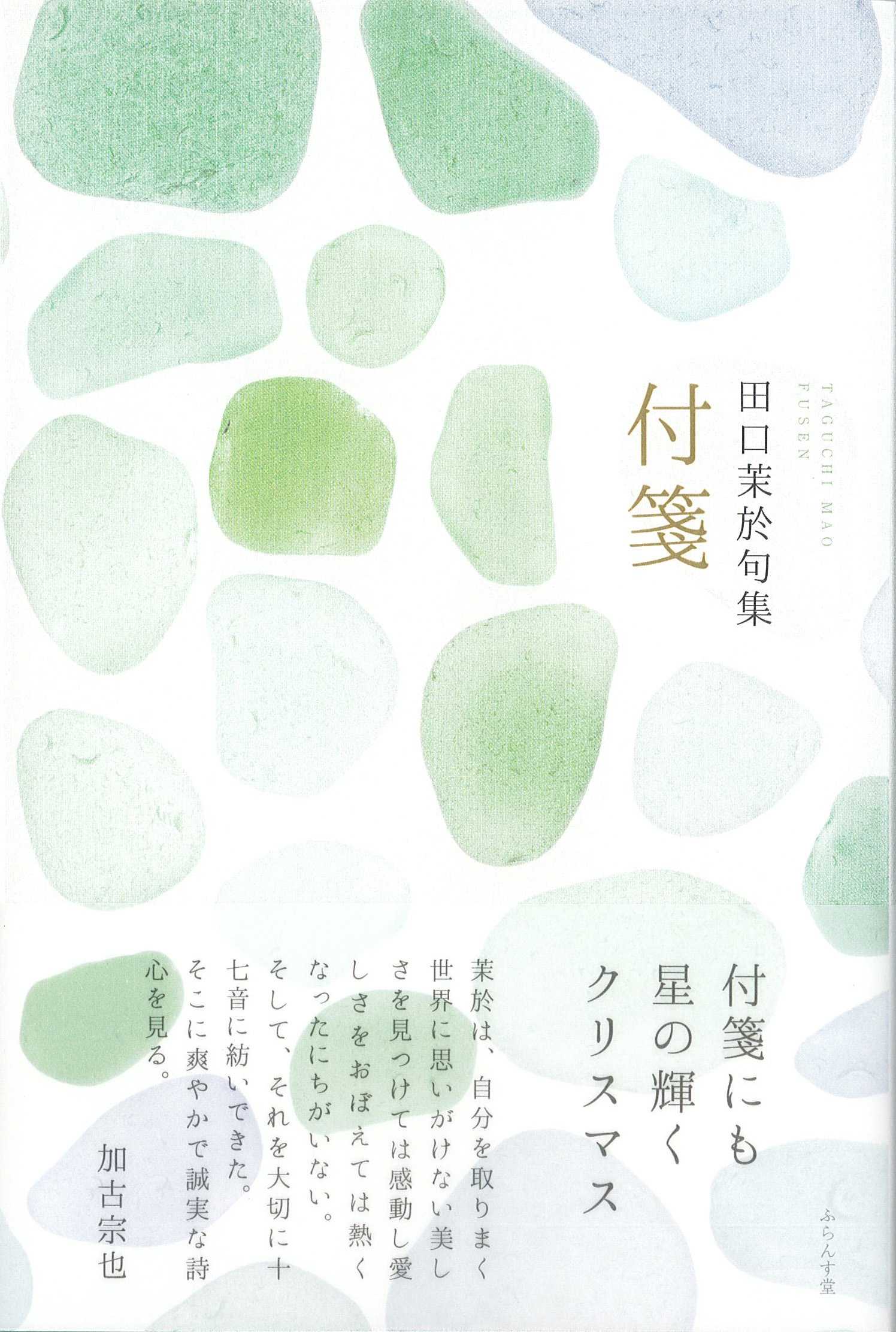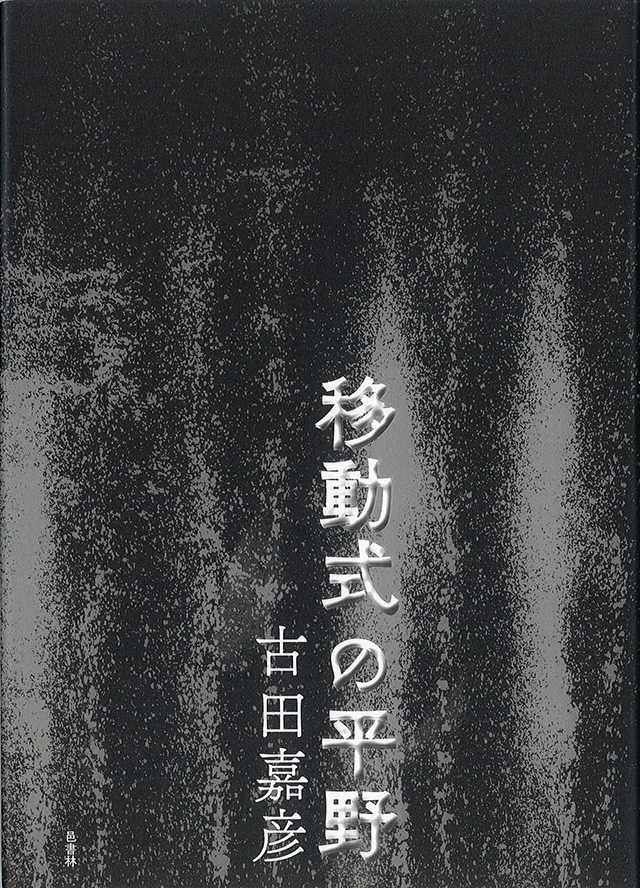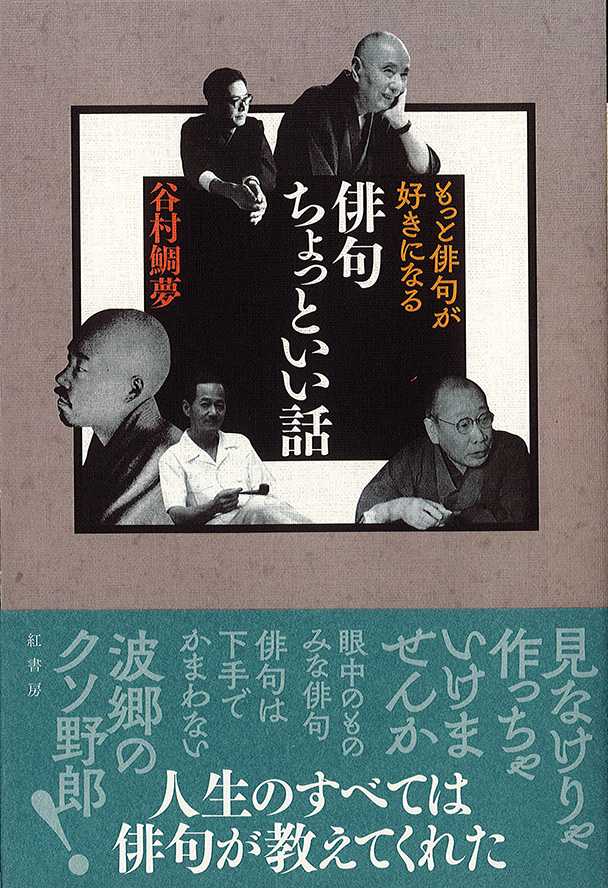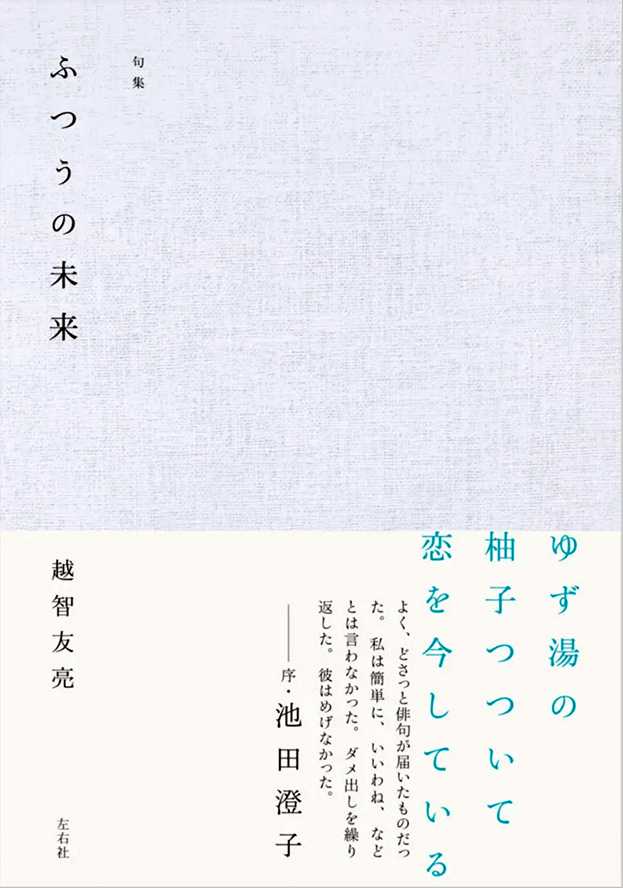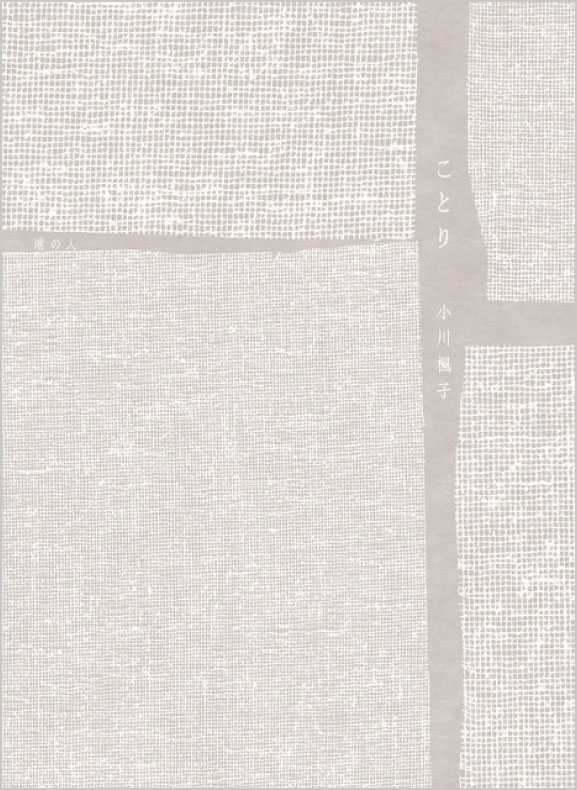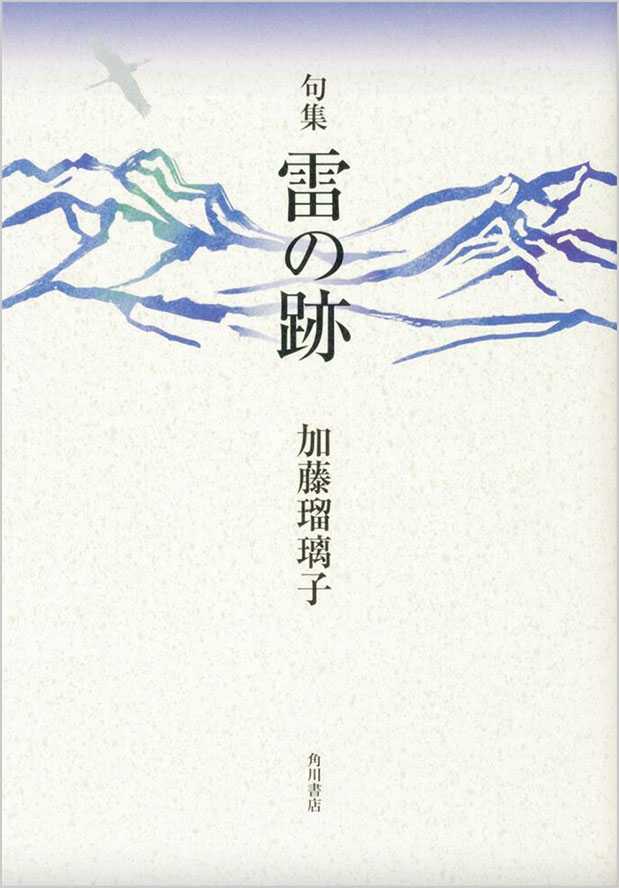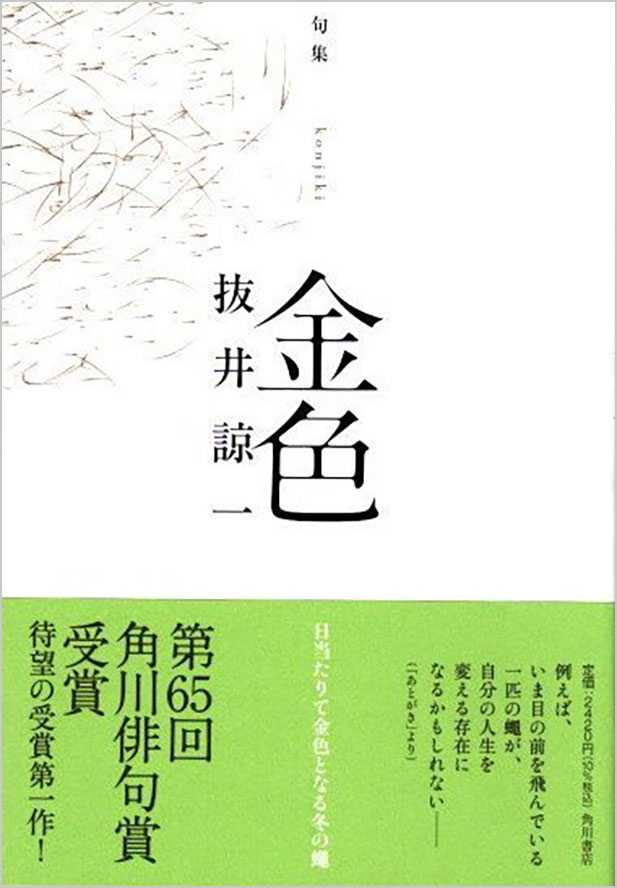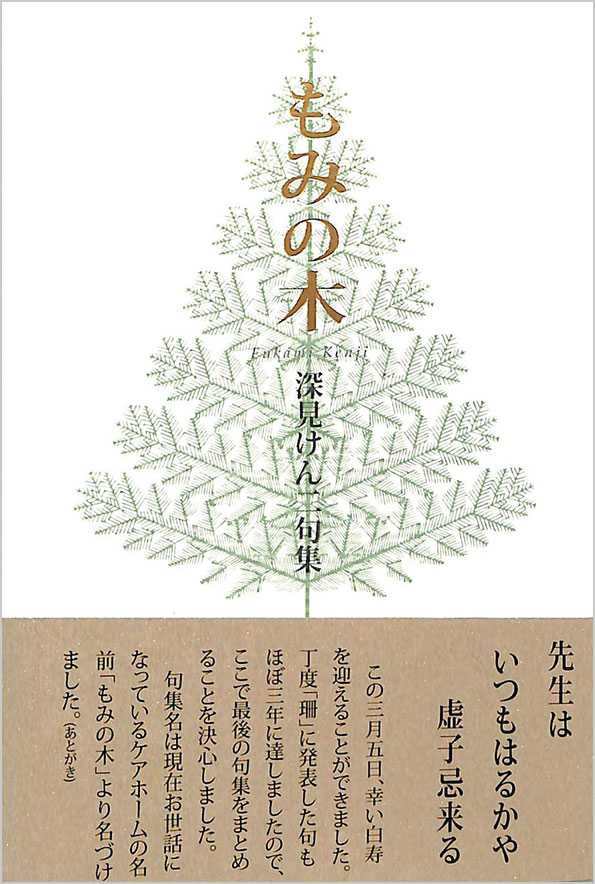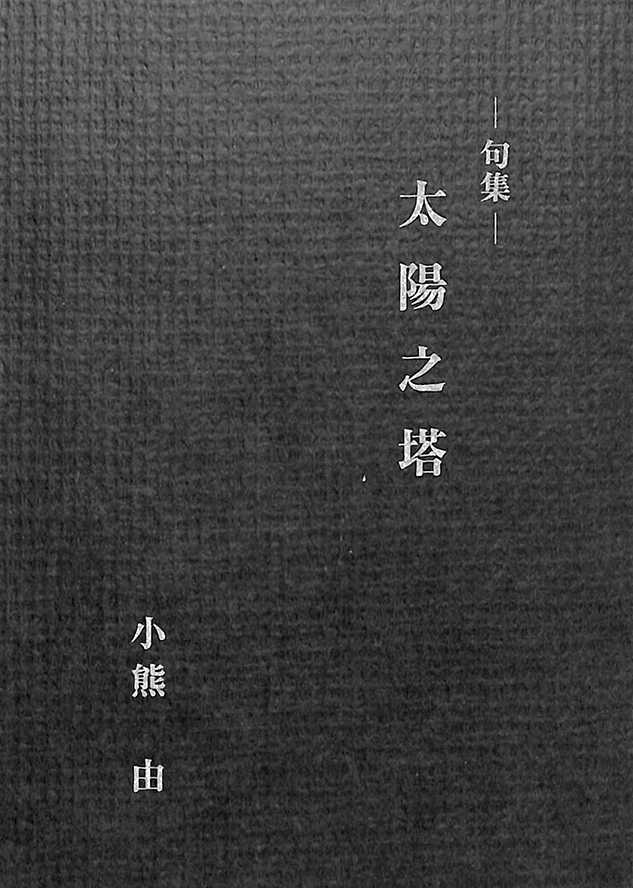本の森
編集部へのご恵贈ありがとうございます
2021年以後の刊行書から順不同でご紹介します
『ぜんぶ残して湖へ』佐藤智子句集
2021年11月
左右社
定価:1800+税
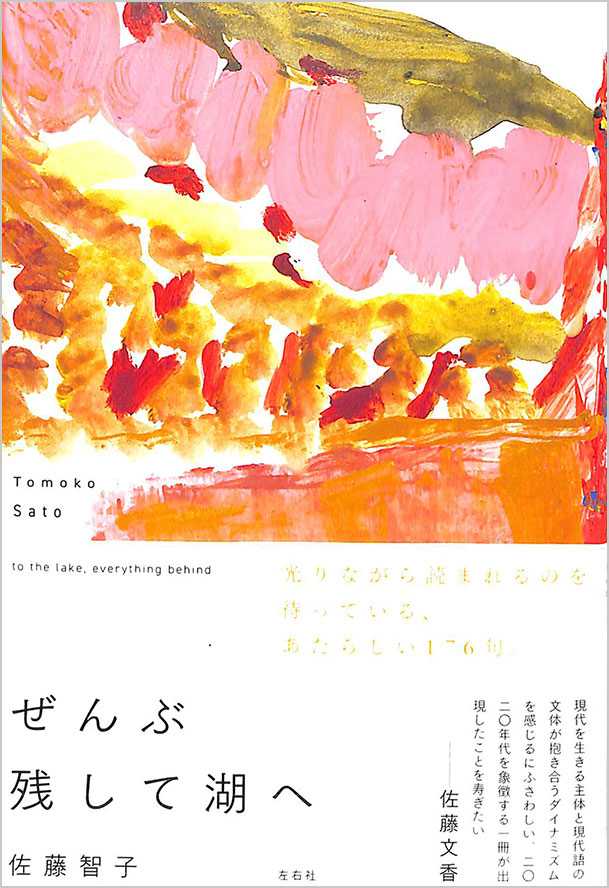
1980年生まれ、句作開始は2014年という著者。佐藤文香氏が講師を務めたワークショップで文香氏の句会に誘われたのが契機といい、今回の第一句集にも文香氏が著者を激賞する栞文を寄せています。自分の書いたものを次から次に面白がってくれる師(?)がいて、著者はさぞ面白かっただろうと思わせられる栞文です。
二人の佐藤氏の気持ちの通いあった句集を手に取って思い出すのは山口誓子と津田清子の関係性です。もともと短歌を詠んでいた津田清子は、近所の橋本多佳子の句会に参加したのをきっかけに無手勝流の俳句を次から次へ作るようになり、それを山口誓子に見せると、句が面白いので誓子は大喜び。のちに清子は「何を書いても誓子先生が「ほうっ!」と言うてくださるから、なんだか俳句を作るのが楽しくなりましてね」(黒田杏子編『証言・昭和の俳句 増補新装版』2021年)と回想しています。
その文香氏の栞文は俳句表現の革新を宣言するマニュフェストの趣きです。特に冒頭の「池田澄子の登場から三十余年。この間、池田の作品の新しさを塗り替える主体の打ち出しと、それを十全に引き出す文体の更新はあっただろうか」という問いかけは、『ぜんぶ残して湖へ』が何を達成したのかを読者に示します。
主体とそれを引き出す文体について、先達として挙げられている池田氏を例に考えてみます。池田氏には〈はつ夏の空からお嫁さんのピアノ〉(『空の庭』1988年)〈じゃんけんで負けて蛍に生まれたの〉(同前)といった句がありますが、これらの句からは天真爛漫な想像力の持ち主という「主体」の印象が感じ取れます。詠まれている内容からいってもそうなのですが、「嫁」ではなく「お嫁さん」を、「じゃんけんに負けて蛍に生まれけり」ではなく「じゃんけんで負けて蛍に生まれたの」を選択するという「文体」の効果でもあります。
どのような言葉遣いをするかによってその句の主体の印象が異なるという意味では、〈忘れちゃえ赤紙神風草むす屍〉(『たましいの話』2005年)〈あっ彼は此の世に居ないんだった葉ざくら〉(『此処』2020年)といったほかの池田氏の句も同様です。これらの句はもちろん戦争を思い、人を思う句ですが、ここで問題になっているのは、そこから一歩踏み込んだ、どんな人が思っているか、ということなのです。
そもそも俳句では、写生の対象やイメージの構成を詠むだけで短い五・七・五が尽きてしまい、性別や年齢、社会的地位、性格といった要素を浮き彫りにして主体を想像させるような言葉を盛り込む余地がなく(これは、現代語であれ古語であれ同じことです)、主体が鑑賞の際に問題になることはほとんどありません。その意味で、文香氏のいう「池田澄子の登場」は革新的であり、伴走者のいない道だったのです。文香氏が第三句集『菊は雪』の連作「諒子」にて、視点人物を設定して三人の人物の関係性を俳句で表現するという実験を試みたのも、池田氏に師事する上での矜持のようなものだったのかもしれません。
『ぜんぶ残して湖へ』の作品は、バンドの演奏の場にやや遅参した人にささやくような〈薫風や今メンバー紹介のとこ〉、比較的若年の社会人同士の会話の断片と思われる〈アメリカンチェリー親孝行ってどうしてる?〉等、言葉遣いによって主体のキャラクターが推察されるという点で池田氏と二重写しになります。
かつ、その主体のキャラクター自体が俳句作品としては類を見ないものです。それは幼さ、そして幼さを隠さない心性(ないしはそれに対する無自覚さ)です。〈コンビニの食べていい席柳の芽〉の「食べていい席」は、ほかの俳人が詠もうとすれば、仮に脳内では「食べていい席」という言葉で認知していたとしても、飲食席・イートインスペースなどと「俳句のための言葉」に直すでしょう。しかしながら重要なのはこの句で「食べていい席」という幼い言葉がそのまま使われていることであり、ここではコンビニのイートインスペースだけではなく、それを「食べていい席」と呼ぶ主体自体も詠まれているのです。
〈まだパジャマ紫陽花が野菜みたいで〉〈スニーカー適当に萩だと思う〉〈棗棗夏休みみたいに過ごす〉〈古いめのニュータウンなりオクラ買う〉〈お祈りをしたですホットウイスキー〉にも同様のことが言えるでしょう。「お祈りをしたです」の句に対しては相子智恵氏による秀抜な一句鑑賞(「ウラハイ」「月曜日の一句」2021年12月13日分)があります。相子氏はこの句に対して「幼児のような独り言からは、他者から見て小さいと思えるような祈りが、実は、その人にとっては言葉遣いを退行させないと表出できないほどの、真に深いところにある祈りなのだと、逆に思わせる力がある」という評を与えています。
幼児のような言葉遣いであるからこその深度ということでいえば現代短歌の〈三越のライオン見つけられなくて悲しいだった 悲しいだった〉(平岡直子『みじかい髪も長い髪も炎』2021年)と共通する部分もありそうです。口語表現の多様性では相当先を行っていた短歌の背中がようやく見えてきたといった感がします。
茄子漬がすこしふしぎで輝きぬ
ペリエ真水に戻りて偲ぶだれをだれが
千両を見ると嬉しい鳥だった
秋は今三十デニールくらい 川
これらの句も、前述の幼さとはまた少し異なりますが、このような言葉遣いをする主体だからこそ内容が活きてくる句です。
〈鮭のシーズンにこにこも伝はります〉〈つぐみ来るから燃えるつてしぐさして〉等、主体の気分が朧化していくような小川楓子『ことり』、〈いつからか粗品と名乗りかじかむ手〉〈あした穴を出ようとおもう熊であった〉等、視点の位置が奇妙な木田智美『パーティーは明日にして』、〈ゆず湯の柚子つついて恋を今している〉〈今日は晴れトマトおいしいとか言って〉等、軽快さやリズム感が古典文法の俳句に対するカウンターとなる越智友亮『ふつうの未来』など、既存の口語俳句を打破するような水準で口語を駆使する句集が昨年から次々刊行されていますが、『ぜんぶ残して湖へ』もその一冊です。
一方、〈枝がちの空も冷たく古りゐたり〉〈西国の人とまた会ふ水のあと〉など、言葉の持つ意味の強さを薄めた先に言葉が発する響きを追求したような生駒大祐『水界園丁』、〈ひいふつとゆふまぐれくる氷かな〉〈ゆかりなき秋の神輿とすこし行く〉等、選び抜かれた言葉で景を作り出していく安里琉太『式日』をはじめ、古典文法の表現を基調として格調のある表現を志向する一群の句集も近年続々と刊行されています。これら二つの流れは相反するものではなく、表現に対する執着という点では共振するのでしょう。〈ととのへる茂みに妃そしりゐん〉のような古典文法を酷使する句と〈髪にしたシガーの匂い避暑の旅〉のような新感覚の口語句が並ぶ藤田晢史『楡の茂る頃とその前後』の存在はその証左です。
秀句佳作の多寡だけではなく、方法論の有無・如何が句集の評価に関わる時代が来ているといえるのかもしれません。(編集部)
〈予告〉
小川楓子句集『ことり』、越智友亮句集『ふつうの未来』は、本サイト「本の森」でも近く紹介予定です。