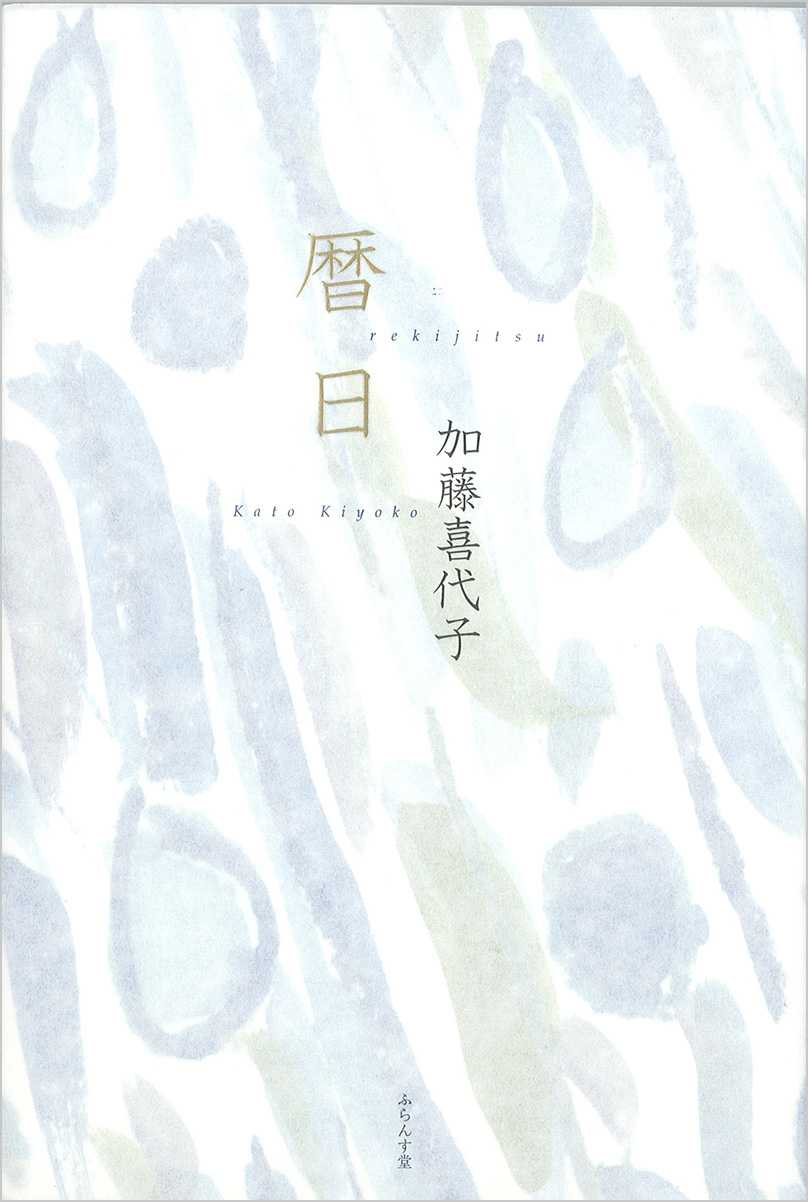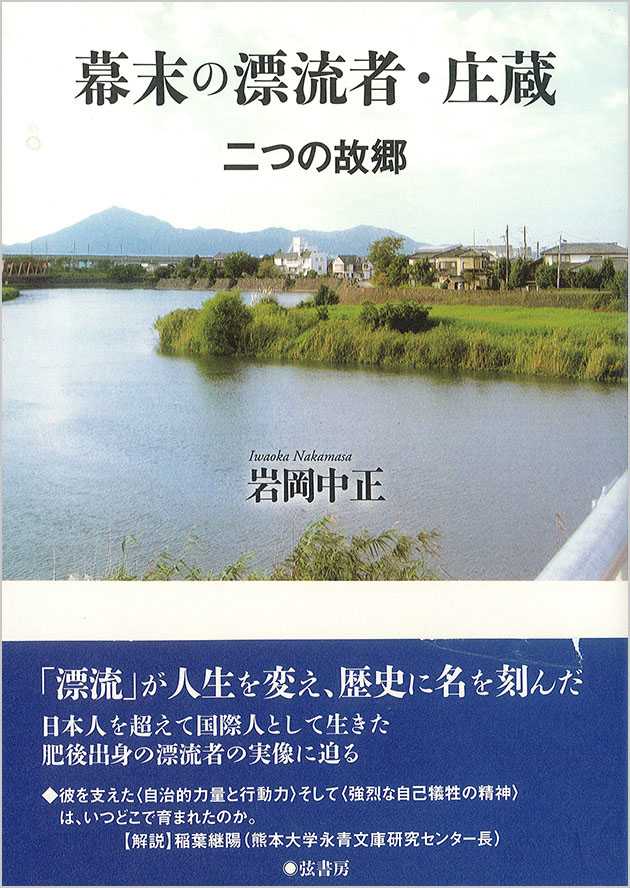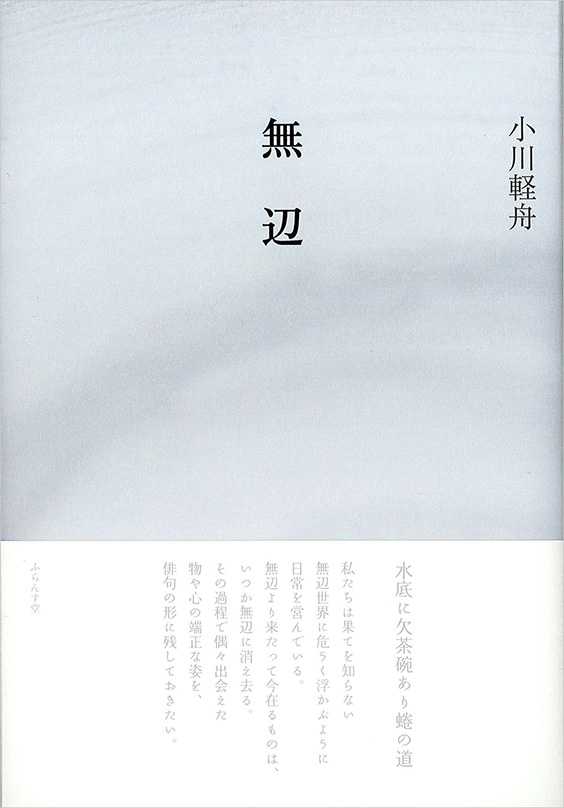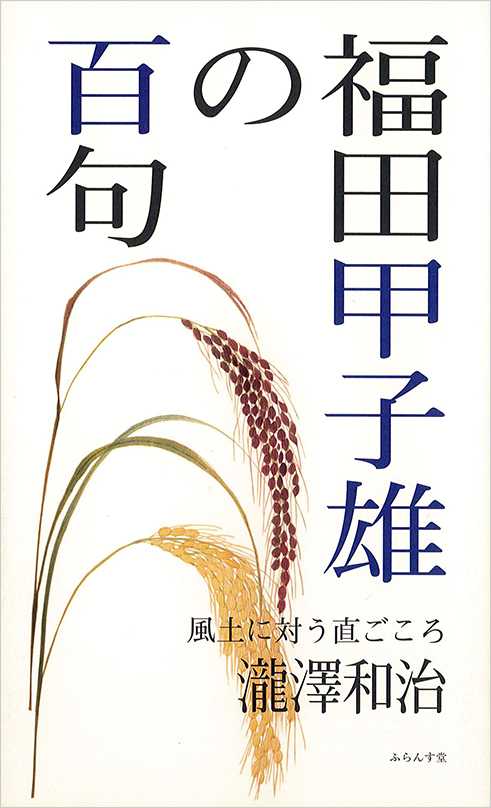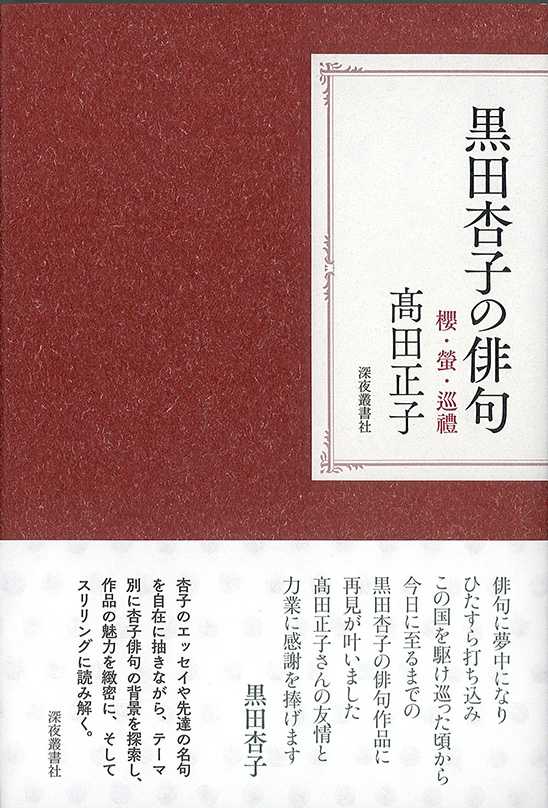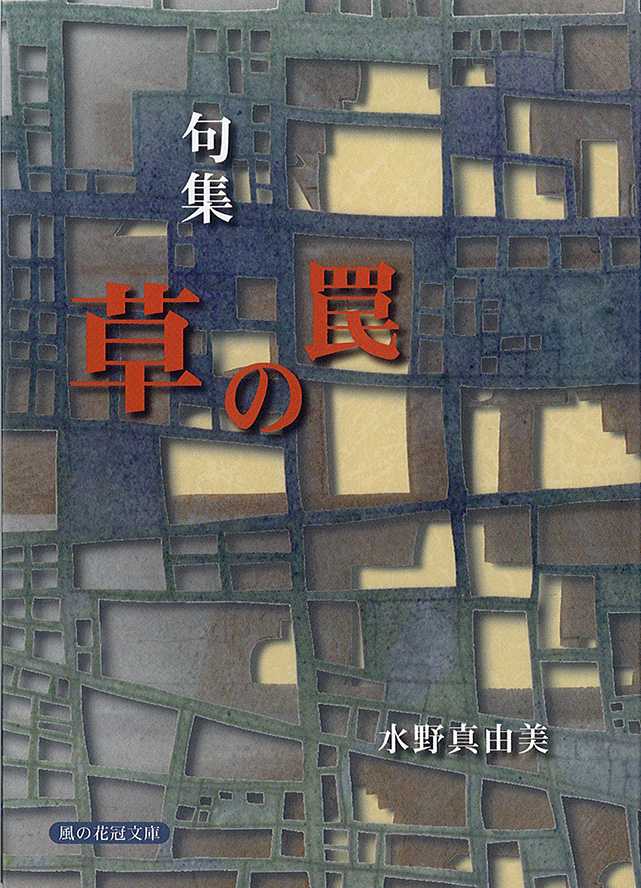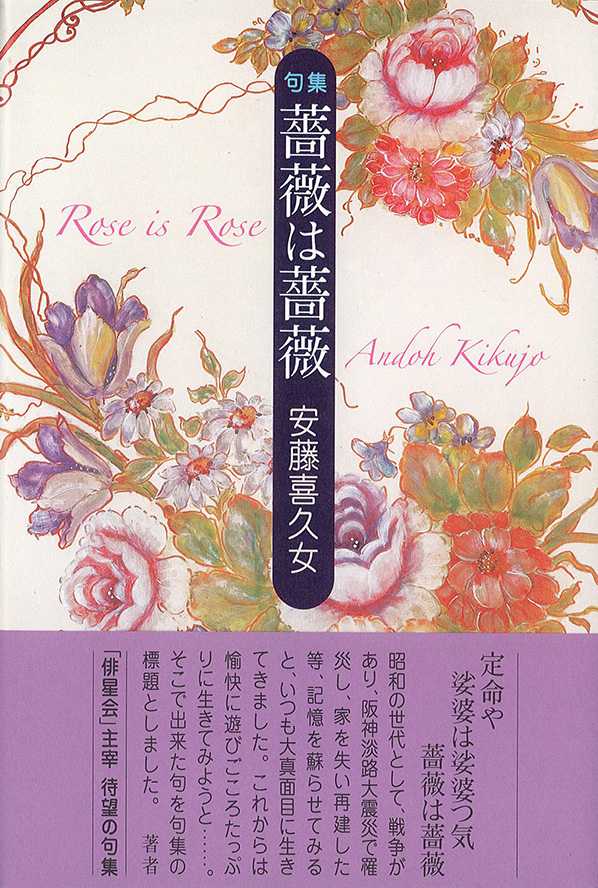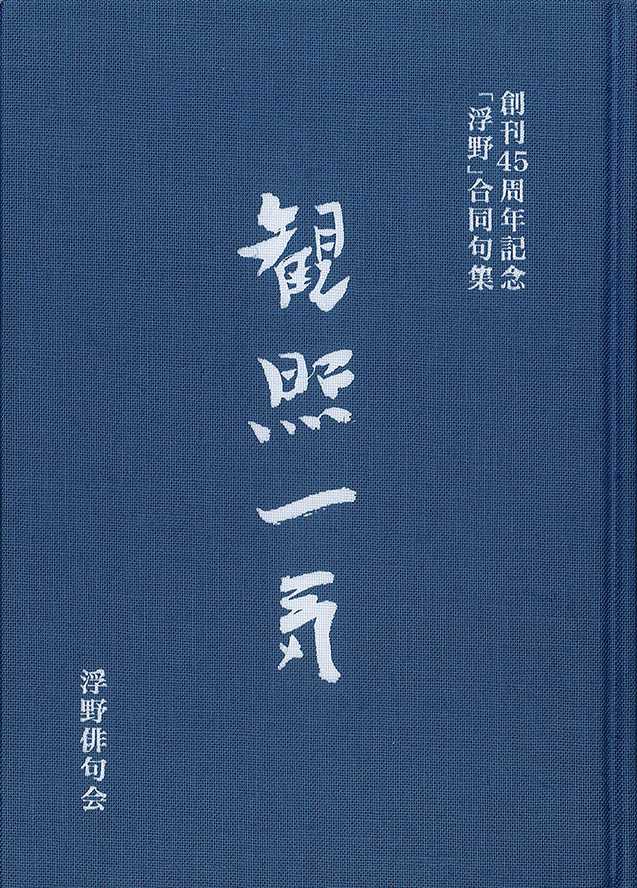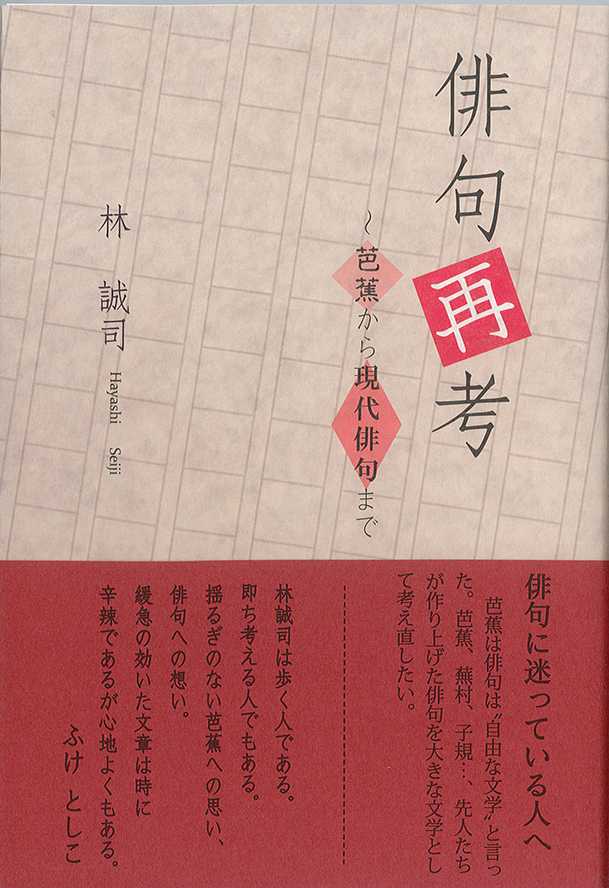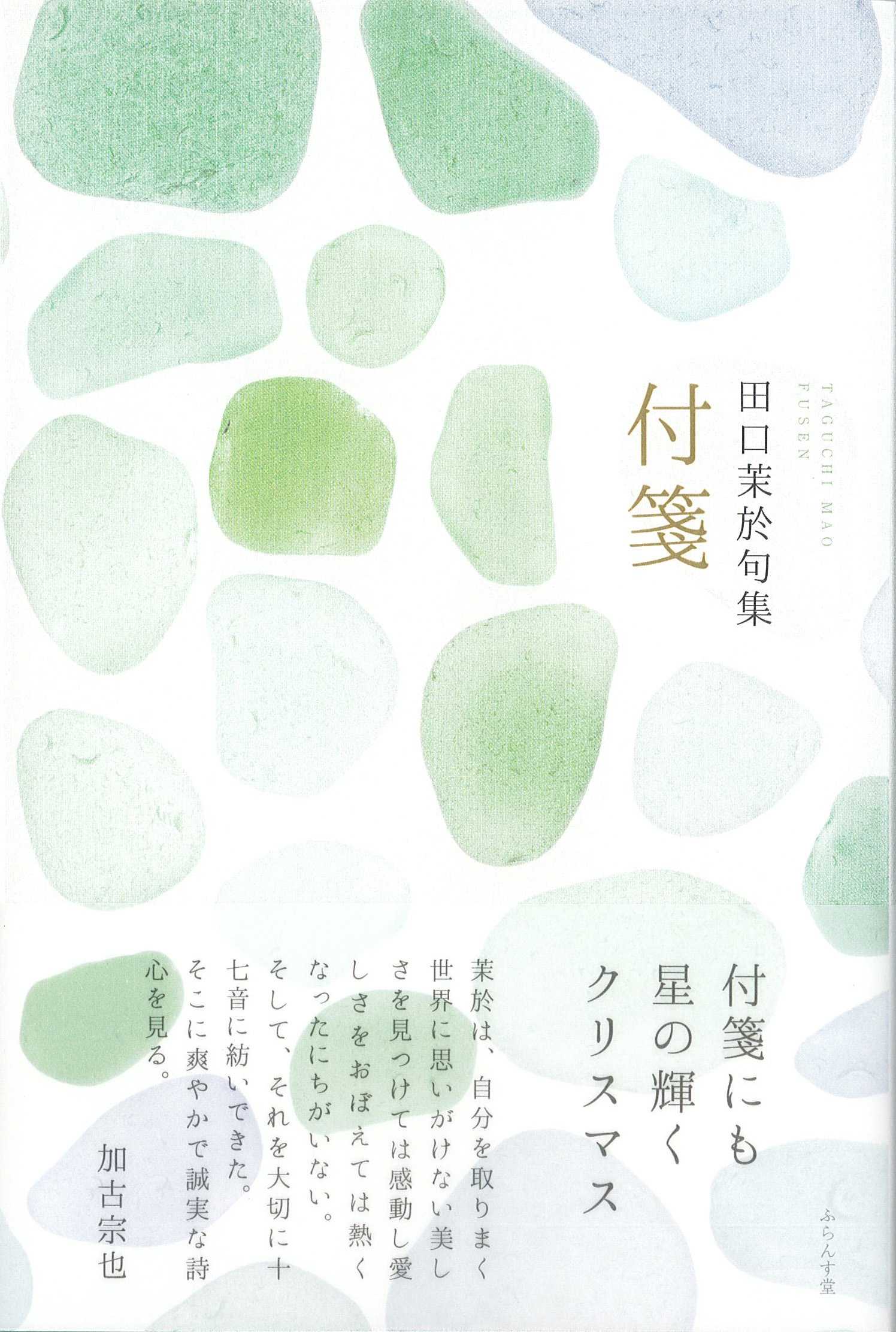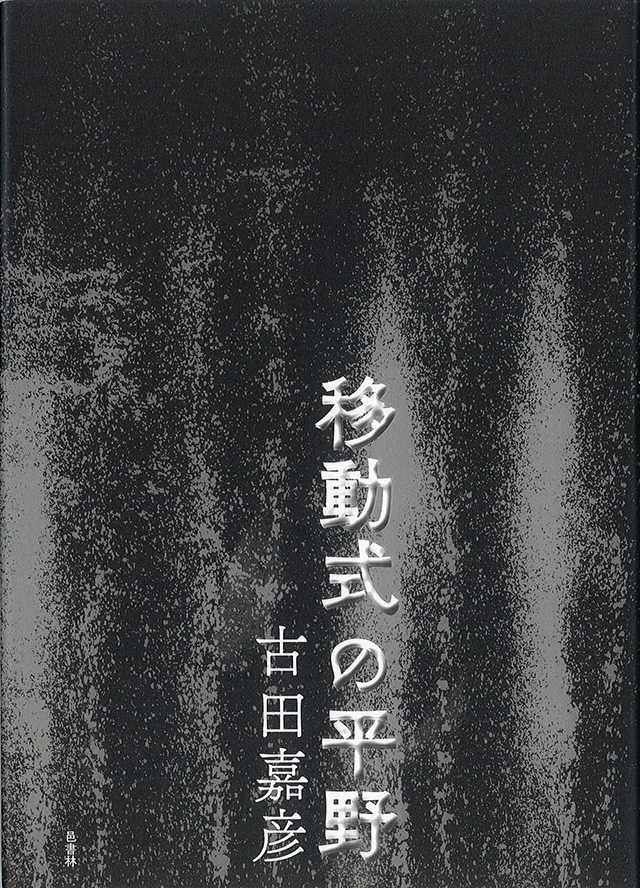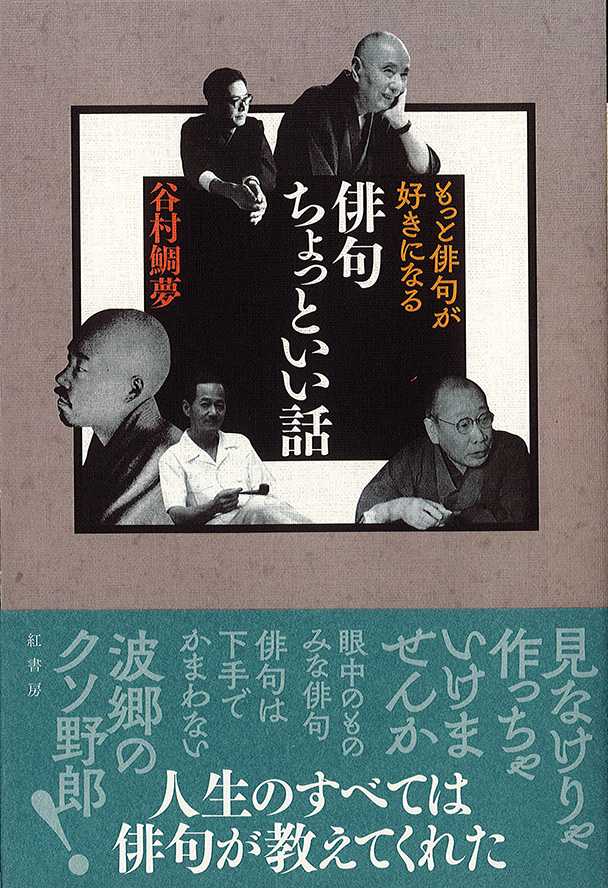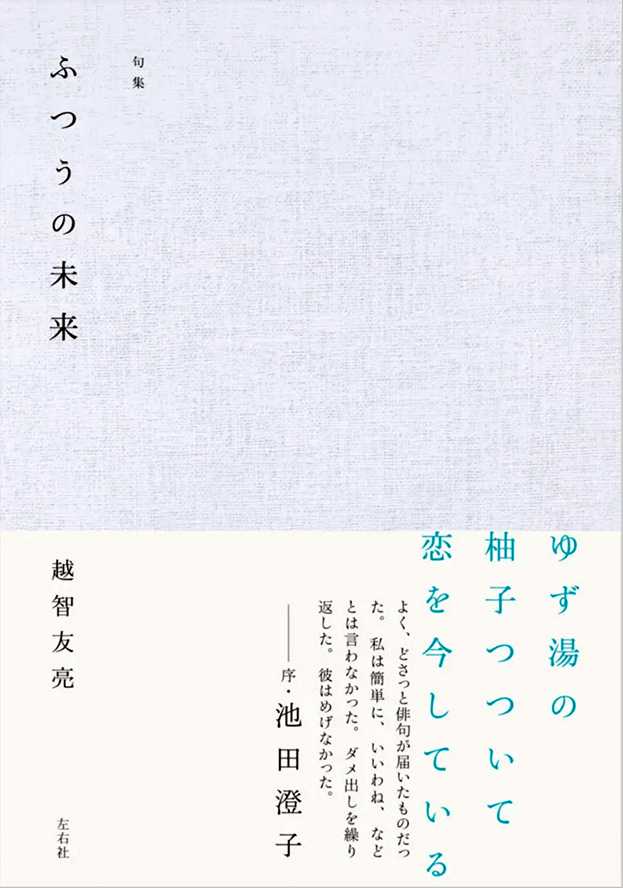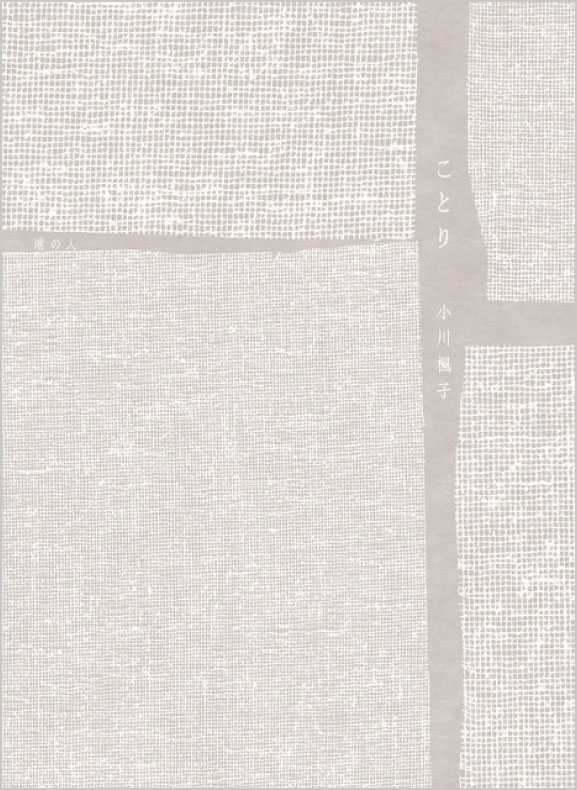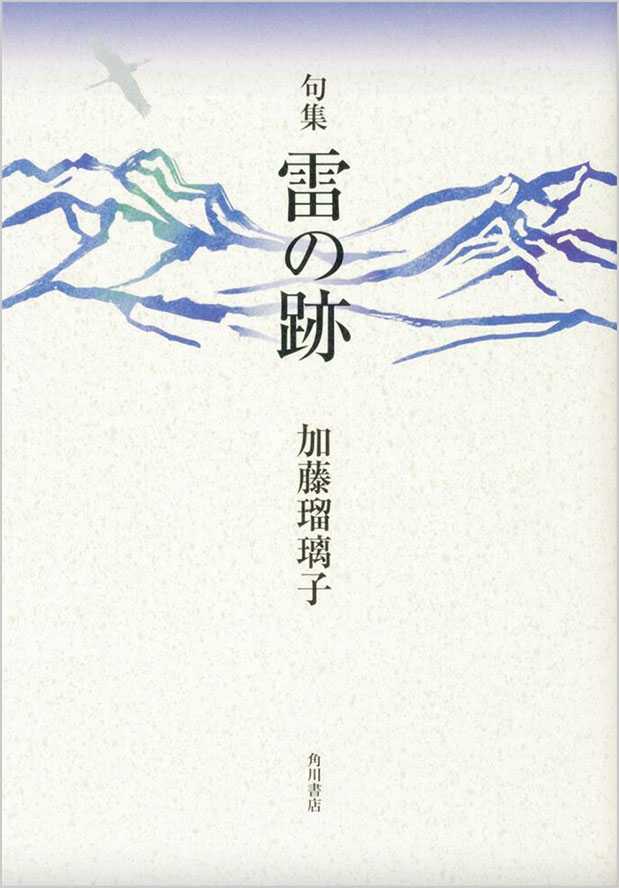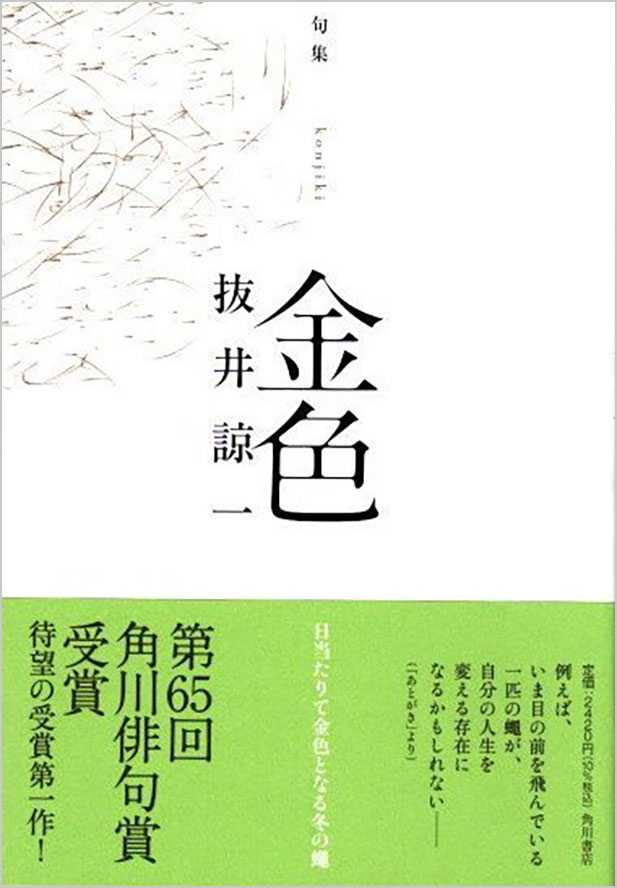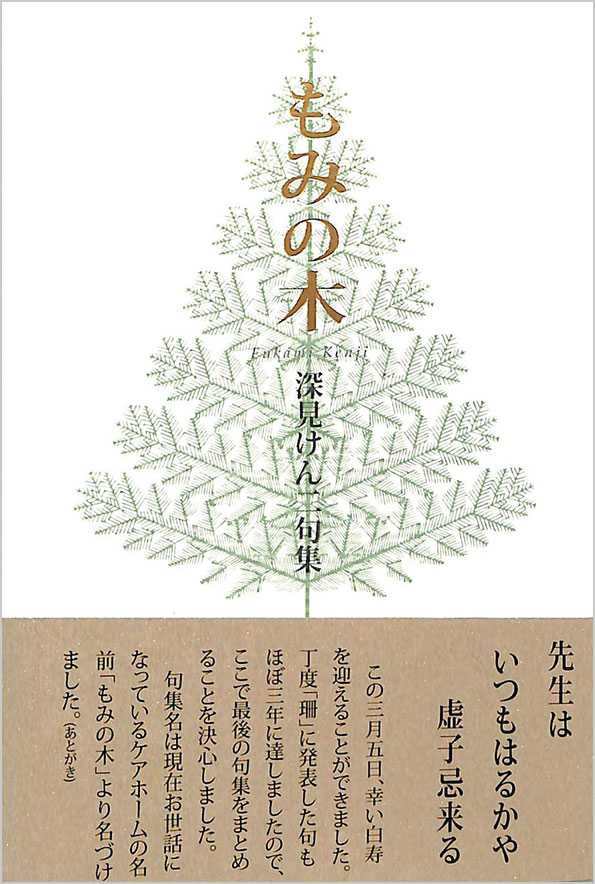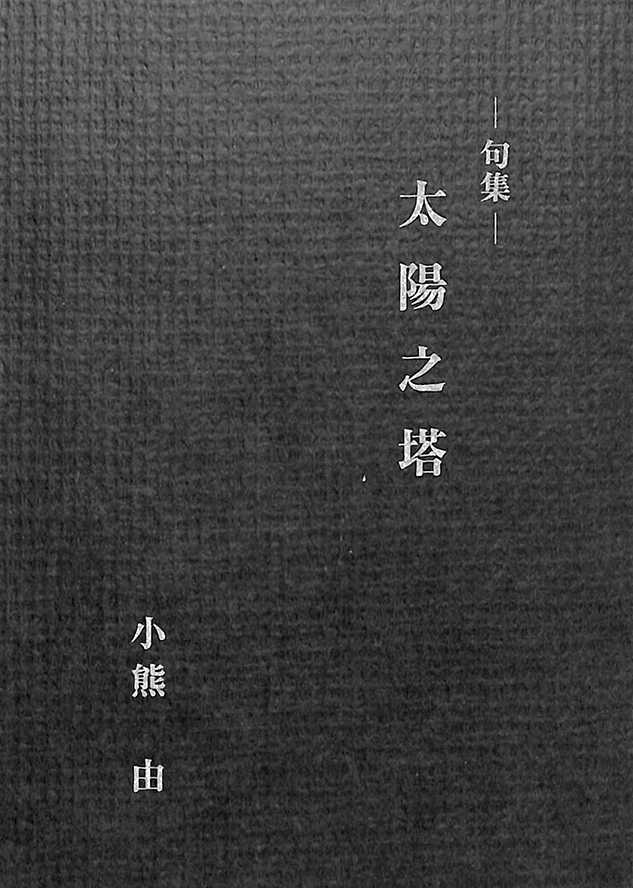本の森
編集部へのご恵贈ありがとうございます
2021年以後の刊行書から順不同でご紹介します
『暦日』加藤喜代子句集
令和4年12月
ふらんす堂
定価:2860円(税込)
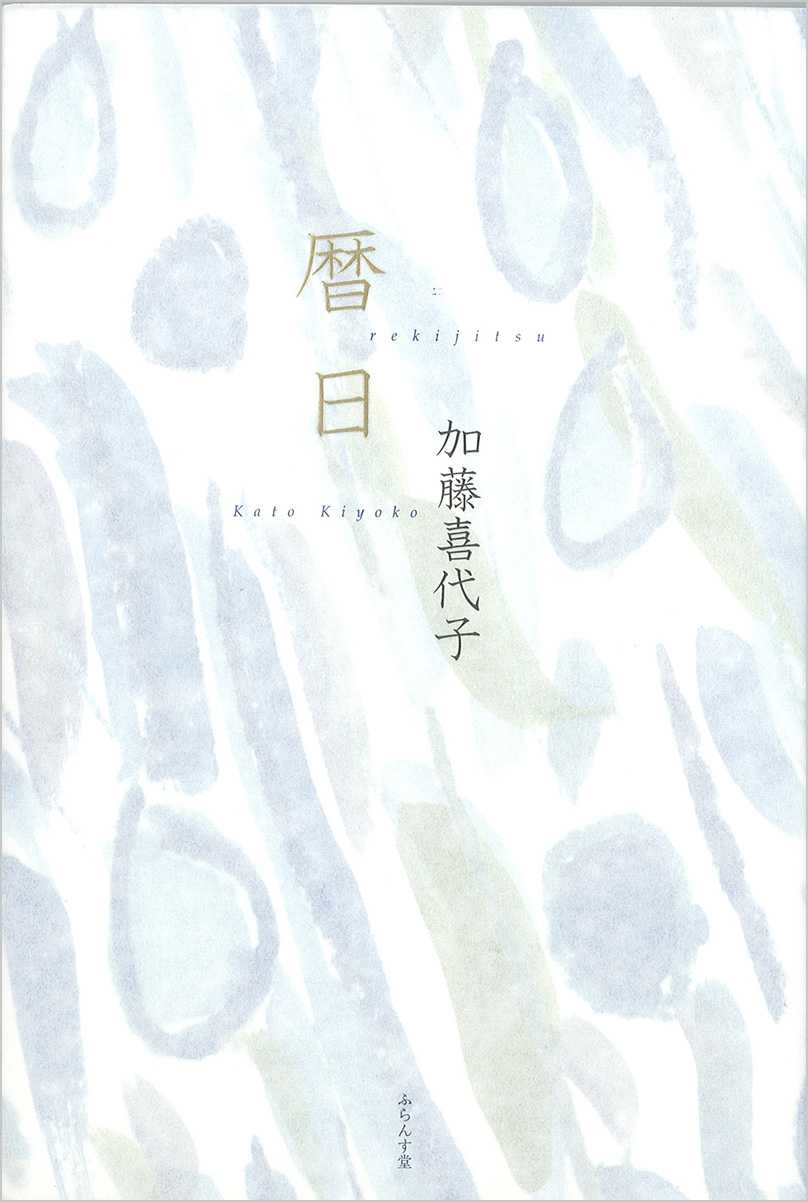
大正13年に生まれ、「駒草」を経て波多野爽波に師事、爽波の没後は田中裕明に師事した著者の遺句集。細やかで詩情のある写生句が並びます。
雨しづくして橘に花多き
小ぶりで白い橘の花が枝先に密集し、雨雫が垂れています。好ましく思って近づいて眺めるうちに、花が放つ高い香りが雨後の湿った空気に交じっているのが感じられてくるようです。使われている言葉はわずかですが、花橘の質感や印象が丁寧に描かれています。
馳せくだる水に漬けおく夏花かな
夏安居のあいだじゅう毎日新しく仏前に供える夏花。摘んできたあと、取り替える頃合いまでまだ少し間があるので、傷みが進まないよう、岩間から湧き出る清水に漬けておいたというような景でしょうか。透明でいかにも冷たそうな水が絶えず鮮やかな花にそそぐという視覚的なイメージが清新で美しい句です。「馳せくだる」は普通、馬に乗って高所から駆けてゆくことで、ここでは水の動きに対する比喩として効果的に用いられています。
野茨の実の多きまま水に影
秋が深まって葉がすっかり落ちてしまったあともびっしりと枝に残る茨の実が、澄んだ水の底に影を落としています。どこか物寂しさが感じられる景です。「多きまま」という季節の経過を暗示する鷹揚な表現と、「水に影」という詰まった表現が呼応し、一句に緩急をもたらしています。
雪きざす空に残りて榠櫨の実
二つの季語を詠んで季節のあわいの情景を繊細に表わした句です。「榠櫨の実」は晩秋の季語ですが、「雪きざす」は雪の降り出しそうな冬空の意でしょうから、初冬の景と読むのがよいかと思います。高枝に重たげに実る榠櫨の実。木を見上げれば、誰にも採られないまま残っているのが、鈍い色の雲に覆われた空の手前に見えました。雲を背景に、でこぼことした榠櫨の実の皮にくっきりとピントが当たっているように見える句です。
ひと偲ぶ旅に冬田やうち晴れて
「裕明先生一周忌」という前書きがあります。30歳以上も年下だった、そして、にもかかわらず病で早世した最後の師に対する敬愛の情が滲みます。師を俳句の作品の上では「ひと」と突き放して呼び、助詞の力を信じて述べすぎず、内容も飾り立てないこの句の詠みぶりは、まさに田中裕明その人の作品を鑑としてきた人のものではないでしょうか。淡々としていながらも下五の「うち晴れて」という短い一語によって一気に心も晴れるようです。ちなみにこの句集の刊行日は12月30日。裕明の命日です。編纂を手伝った孫の藤本夕衣氏があえて選んだ日付ではないでしょうか。
この句に並ぶ〈ひととせの冬水無瀬野の雲つよし〉も、前書きはついていませんが、同じく一周忌の旅の句でしょう。「水無瀬野」は裕明の主宰誌「ゆう」の前身誌の名前でした。したたかに育ち広がる寒雲にありし日の師の面影が二重写しになります。さらに次の句〈坐られし椅子いまもある落葉かな〉も、「坐られし」という敬意表現から、同じ旅の句といえるでしょう。思いを喚起する「椅子」というオブジェと落葉だけで構成されたシンプルで余白の多い句です。
この句のような単純化・抽象化の著しい文体は、裕明が俳壇の中堅として生きた平成期の俳句の一つの典型だったように思われます。
背の高き人を入れたる夕焼かな
「背の高き人」という言葉遣い、その人と夕焼けだけで構成される景。夾雑物のない清潔な詠みぶりから醸し出される独特の詩情があります。
青桐や柱さみしく見ゆる日も
この句も単純化・抽象化の傾向がある句です。この「柱」はいったい何の「柱」なのか、なぜ「さみしく見」えるのか、現実世界と緻密に対応する具体性から離れることで世界の別の見え方の一端を示すような句もあるのです。
一方で〈鳶啼くや春の潮目のあきらかに〉〈来かかるや鱵ときけばのぞかれて〉〈そのからだ熱くぞ雪に囀れる〉のような句の、闊達で熟練の言葉運びにも息を呑みます。ページをめくるごとに、戦後の有季定型と歩みを共にした一人の俳人の姿が見えてくるような、大切にしたい一冊です。(編集部)
-
02月04日
『幕末の漂流者・庄蔵』岩岡中正 -
01月29日
『無辺』小川軽舟句集 -
01月21日
『福田甲子雄の百句』滝澤和治 -
01月15日
『黒田杏子の俳句 櫻・螢・巡禮』髙田正子 -
01月10日
『草の罠』水野真由美句集 -
01月01日
『薔薇は薔薇』安藤喜久女句集 -
12月29日
『創刊45周年記念「浮野」合同句集 観照一気』浮野俳句会 -
12月25日
『俳句再考 芭蕉から現代俳句まで』林誠司 -
12月24日
『遠き船』松野苑子句集 -
12月17日
『付箋』田口茉於句集 -
12月10日
『ねぶた』佐藤弥澄句集 -
12月03日
『北落師門』黛まどか句集 -
11月30日
『移動式の平野』古田嘉彦句集 -
11月19日
『もっと俳句が好きになる 俳句ちょっといい話』谷村鯛夢 -
11月13日
『ふつうの未来』越智友亮句集 -
11月12日
『ことり』小川楓子句集 -
11月05日
『雷の跡』加藤瑠璃子句集 -
11月05日
『金色』抜井諒一句集 -
10月29日
『もみの木』深見けん二句集 -
10月29日
『太陽之塔』小熊由句集