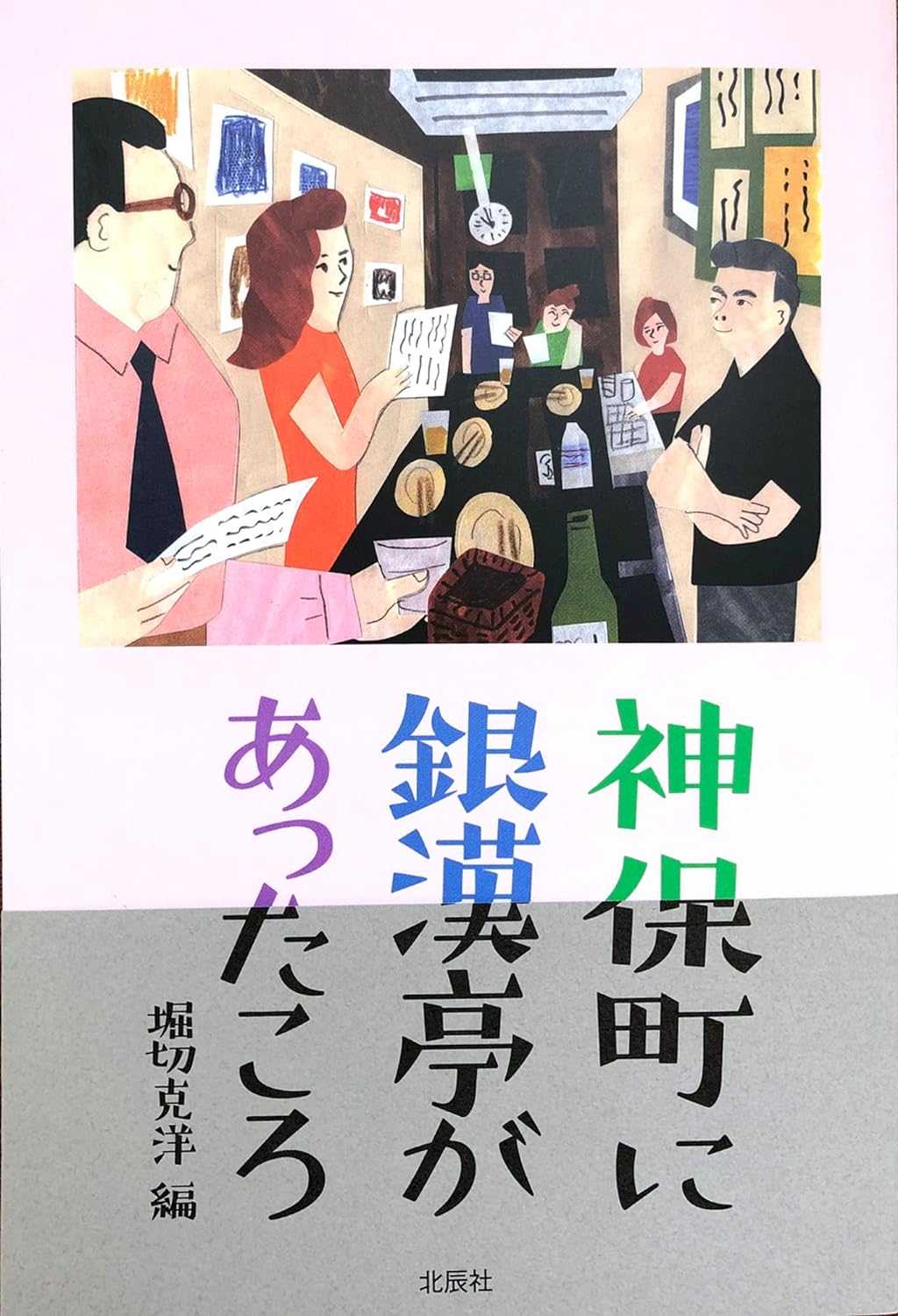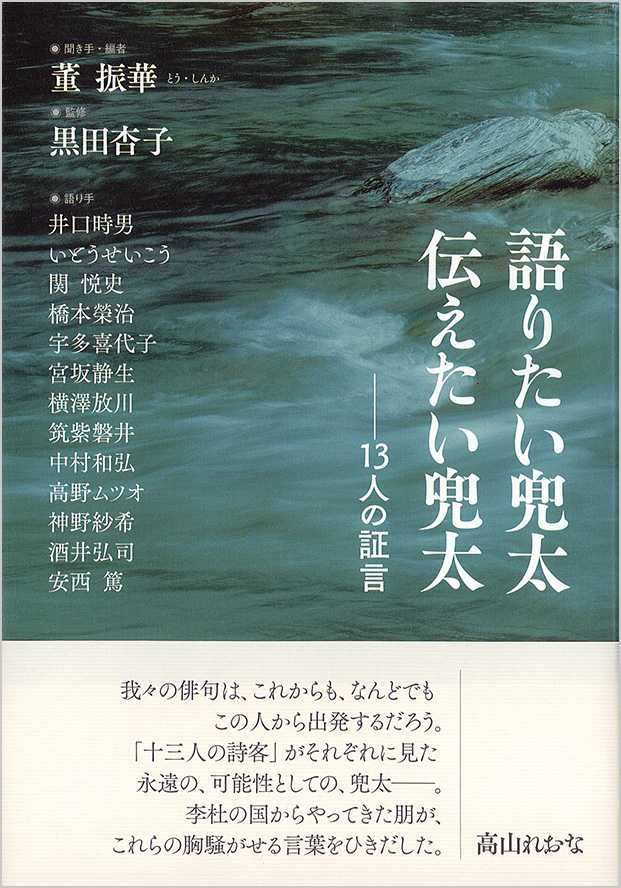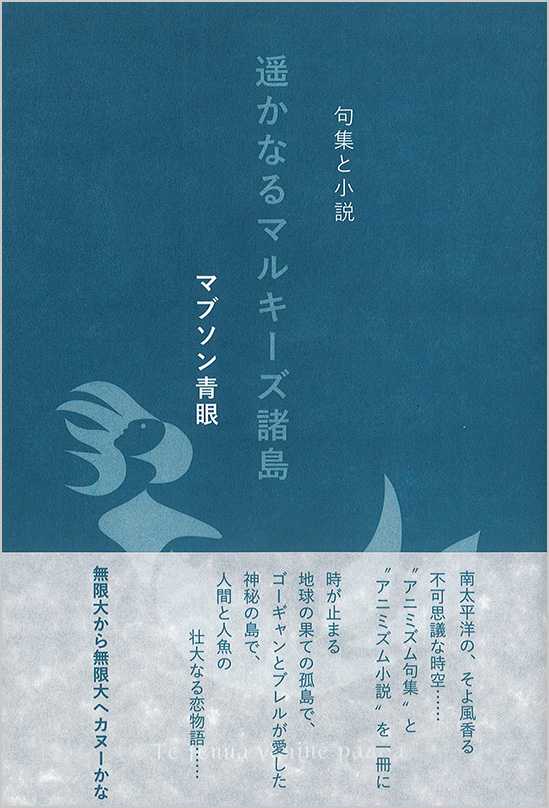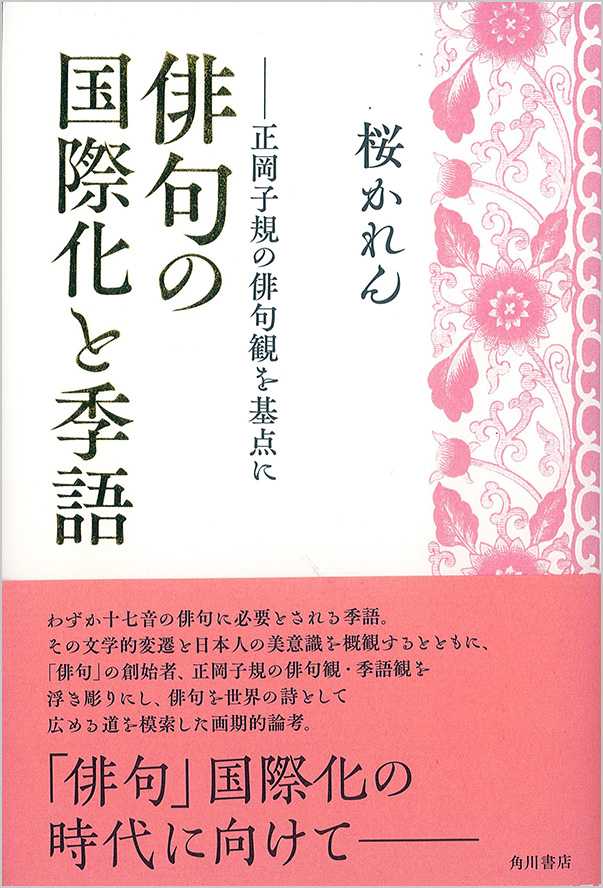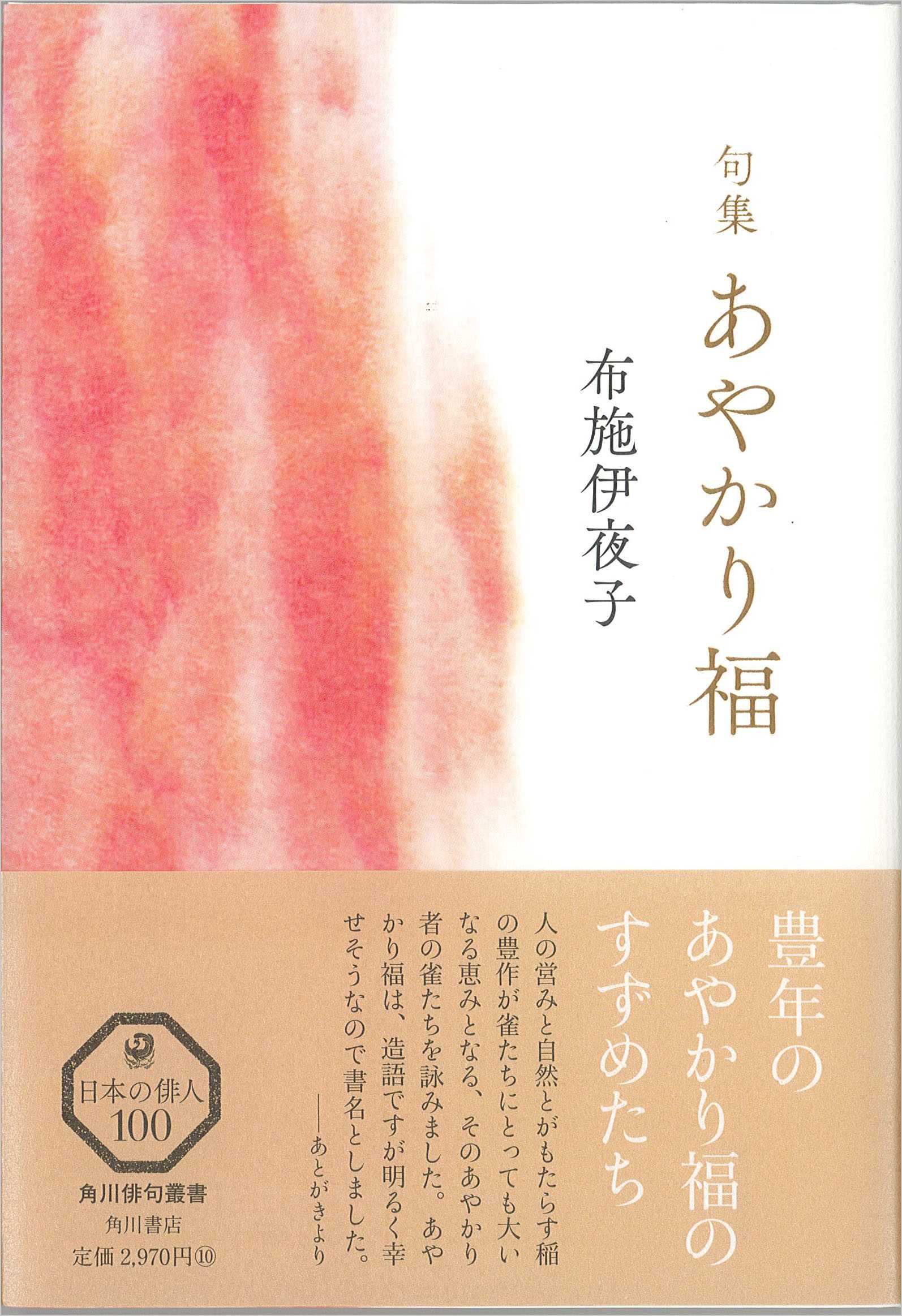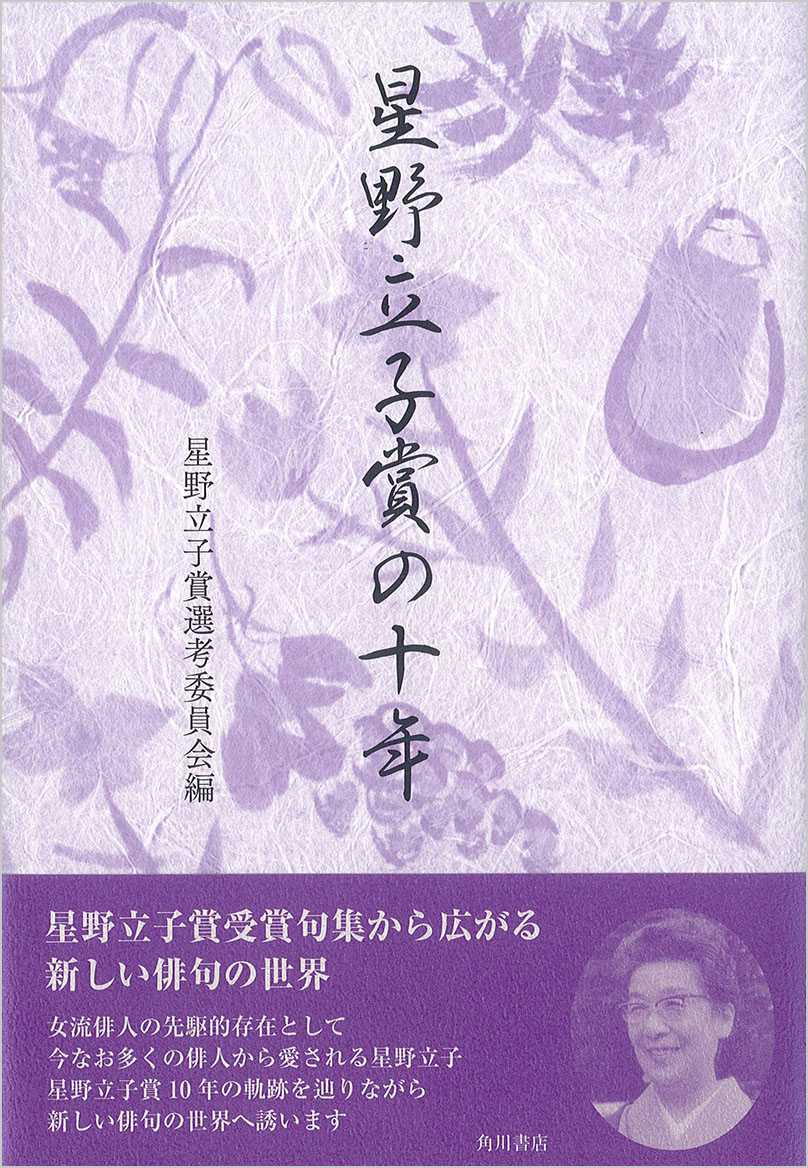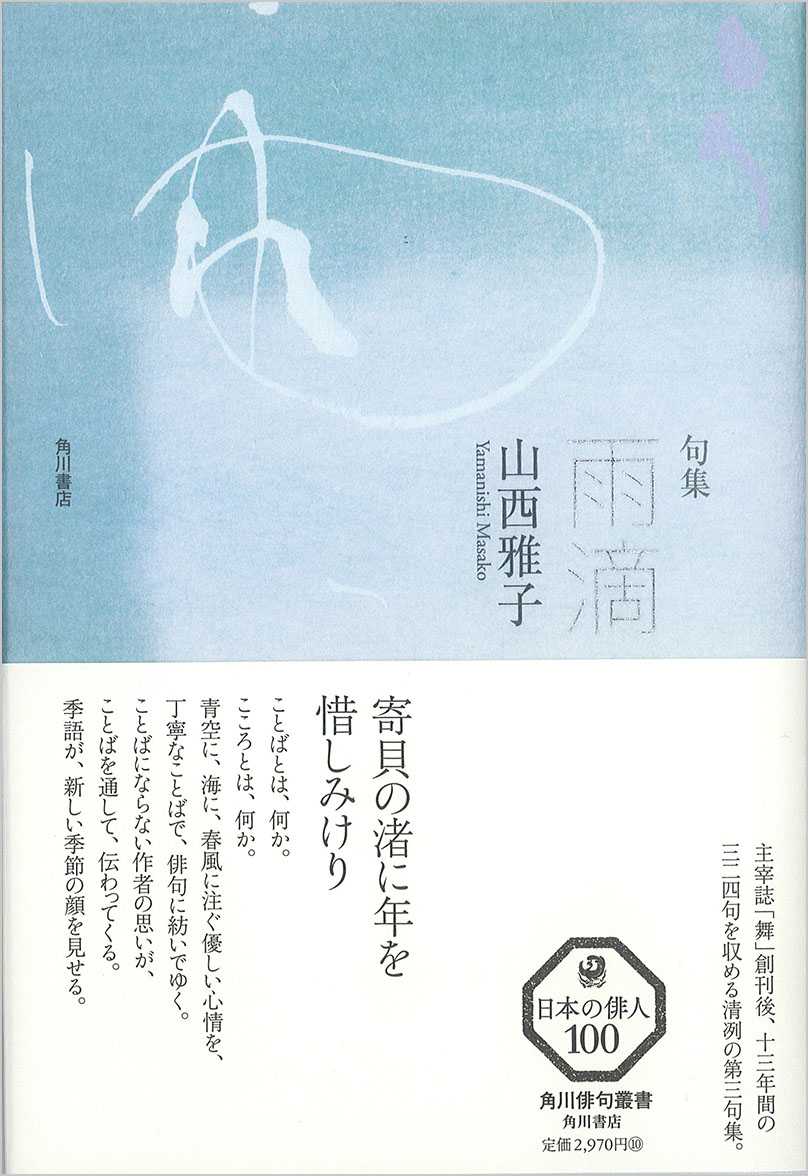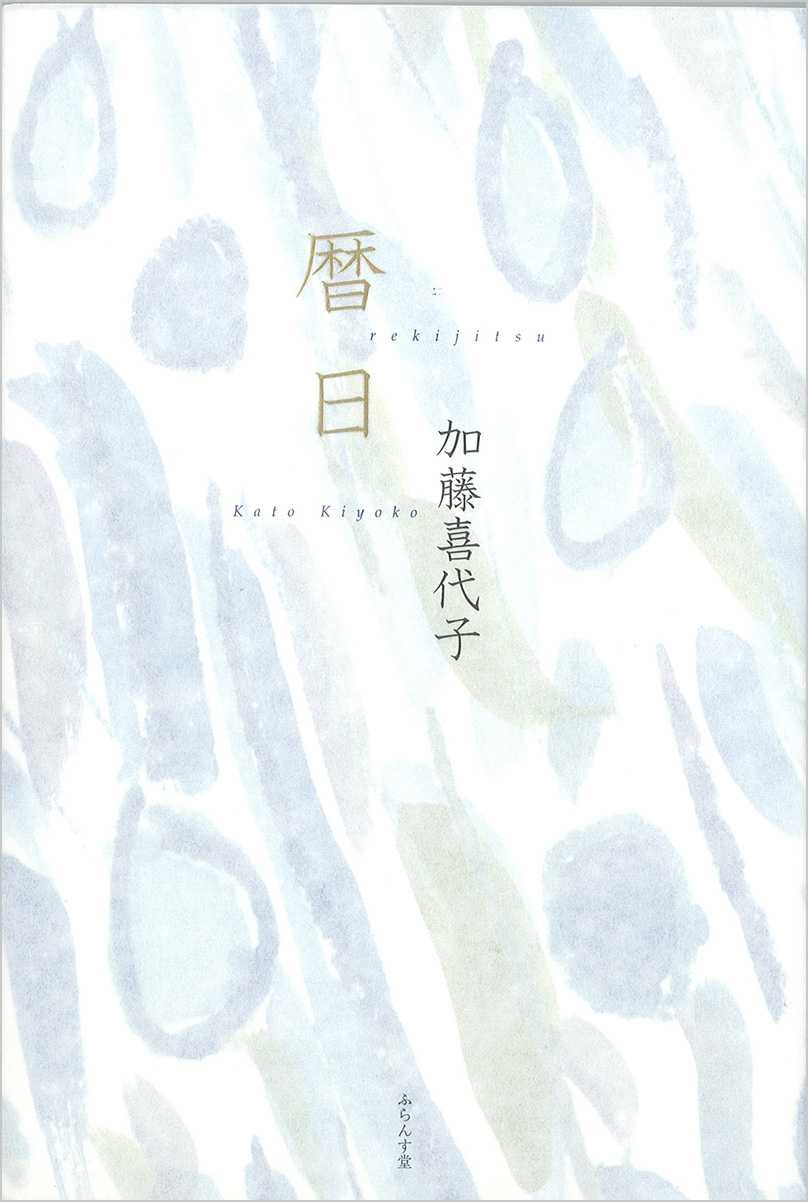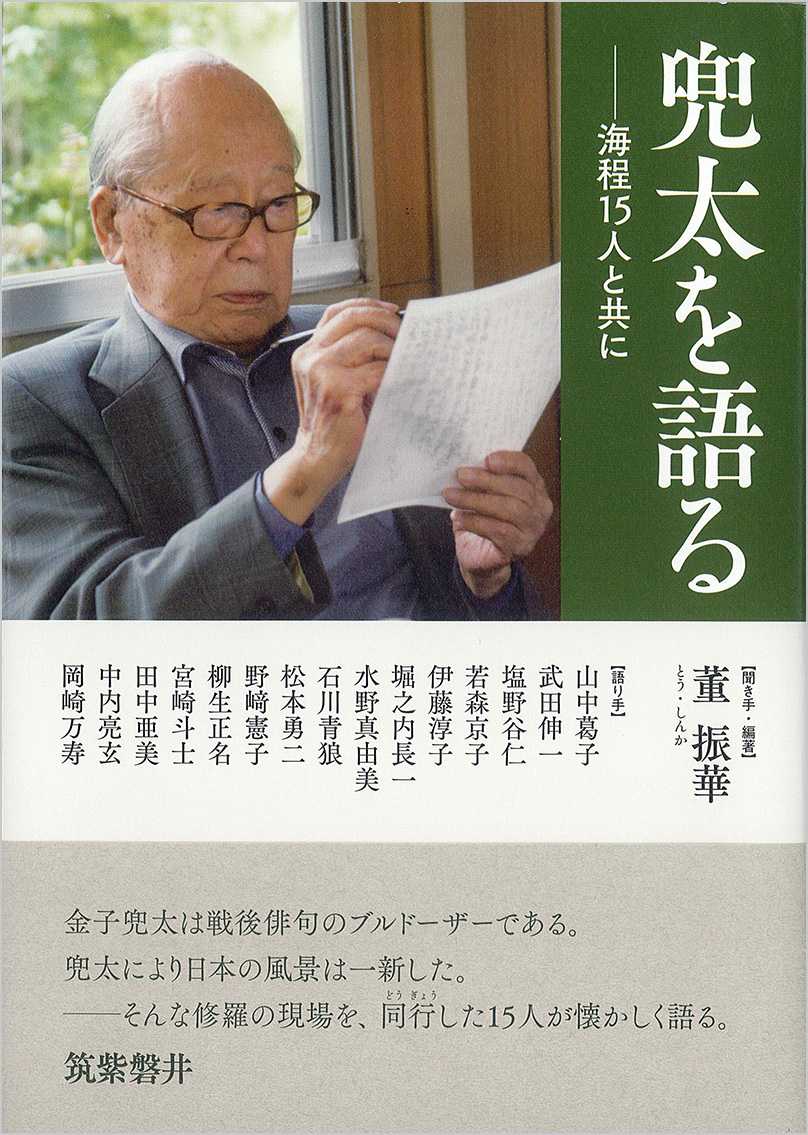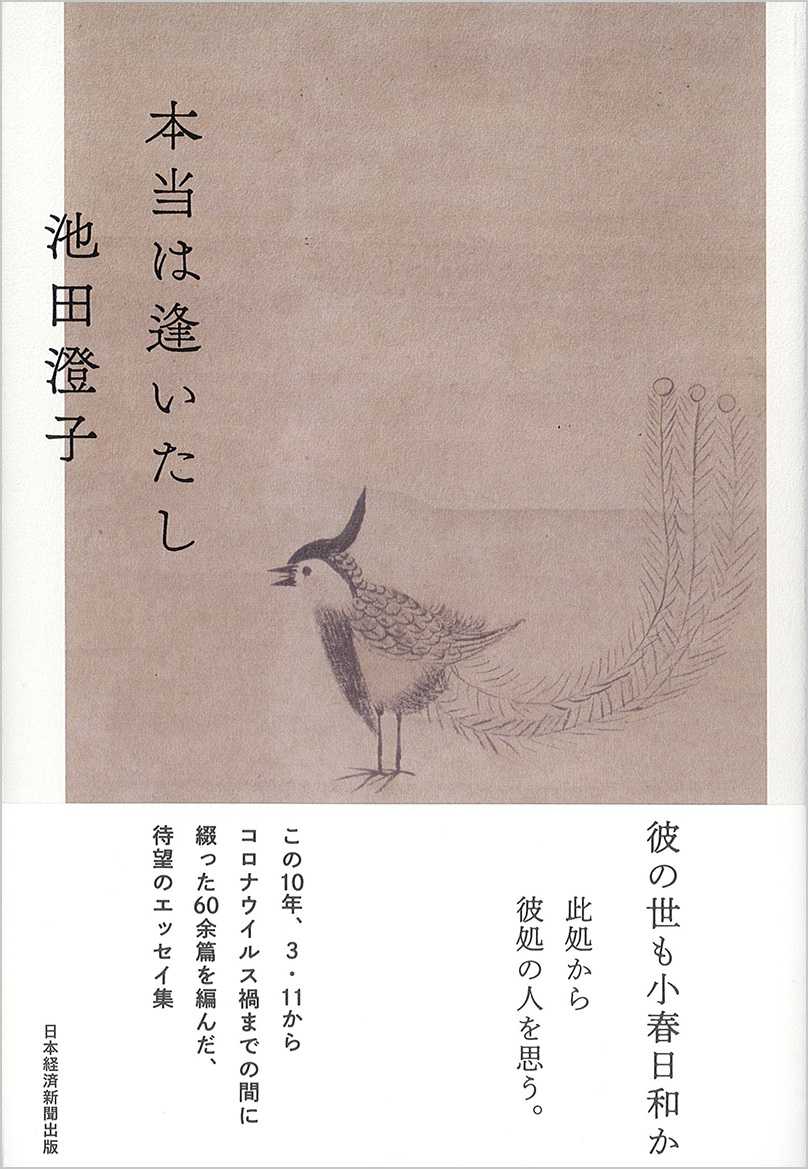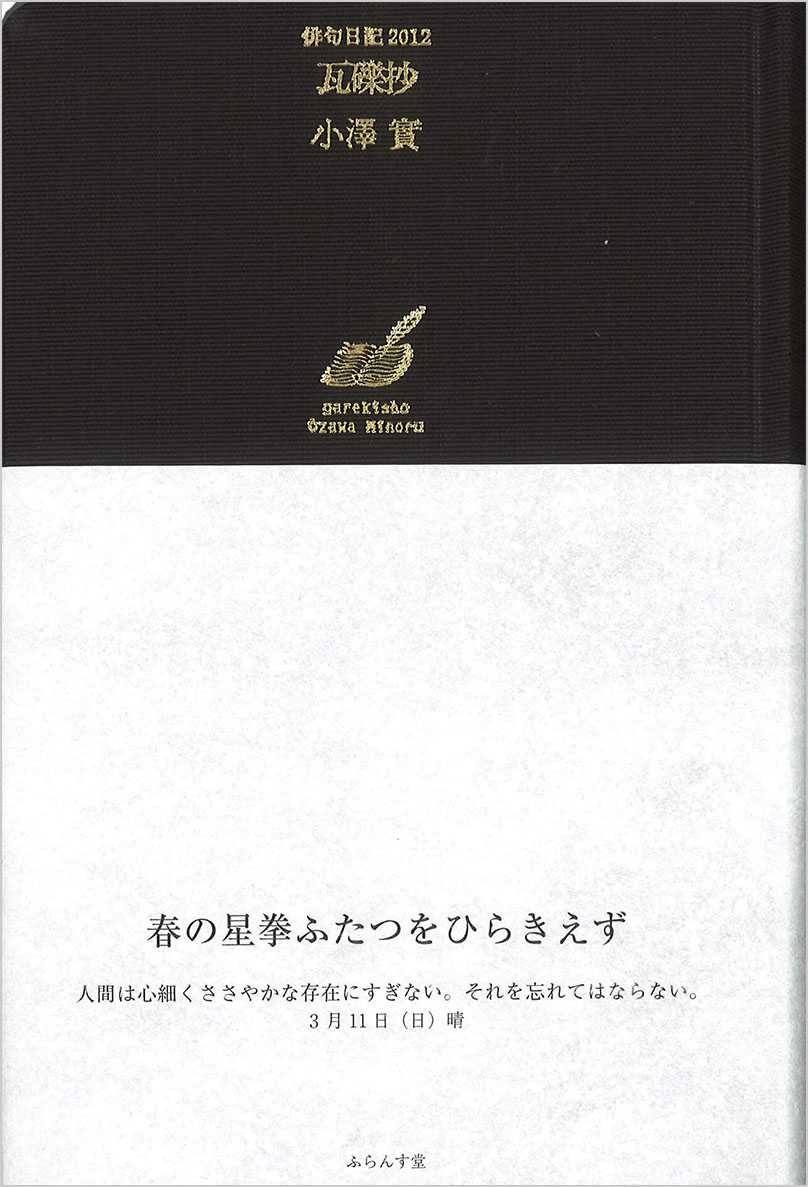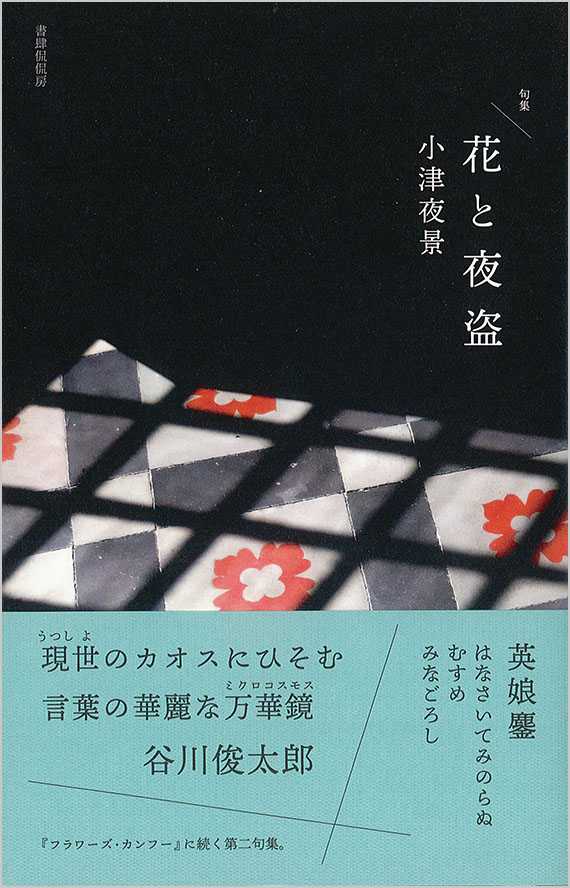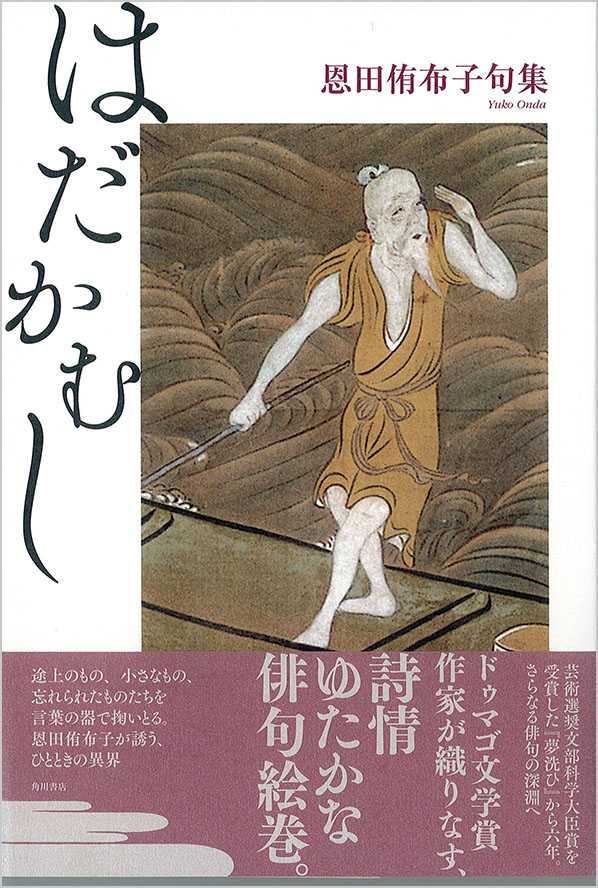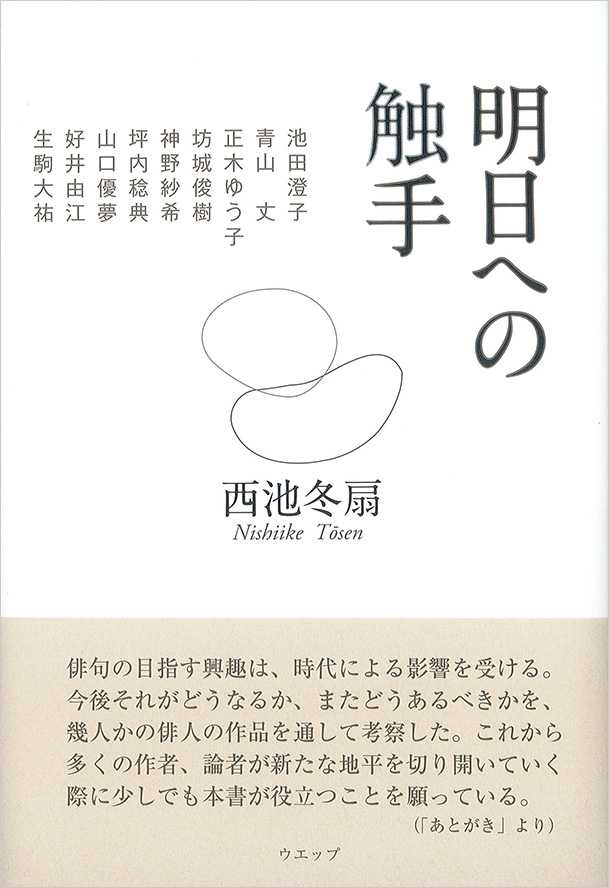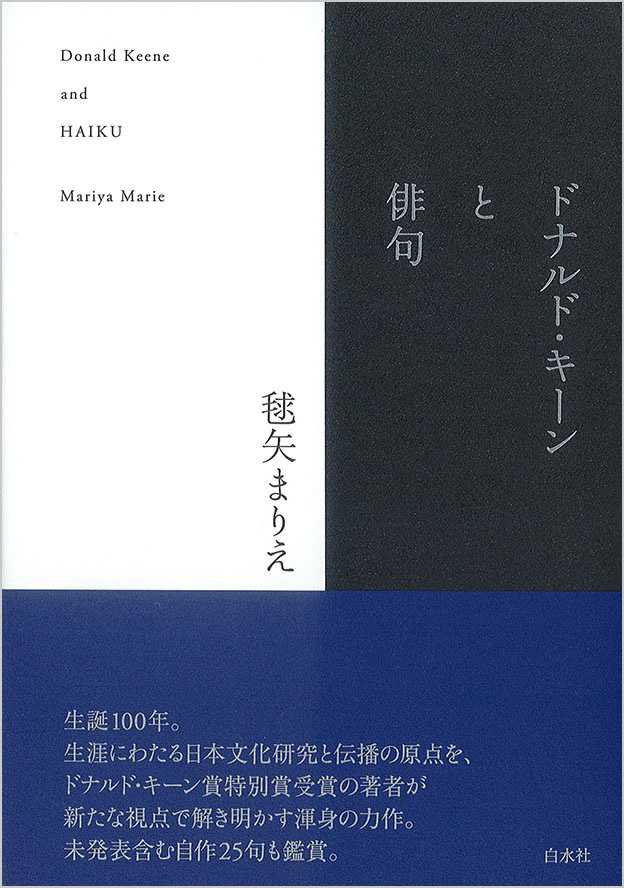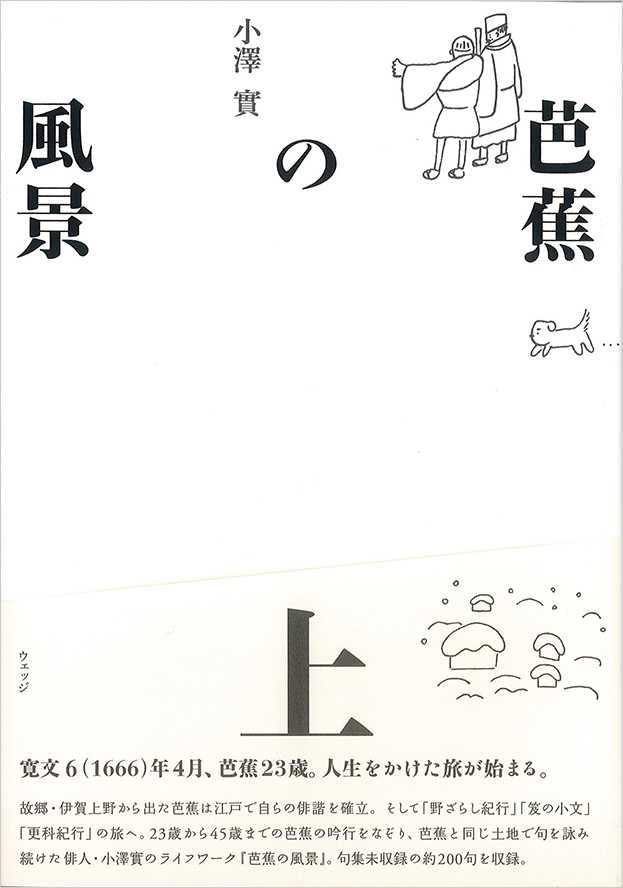本の森
編集部へのご恵贈ありがとうございます
2021年以後の刊行書から順不同でご紹介します
『興』村山半信句集
2021年11月
ふらんす堂
定価:2000円+税

同門の向井去来に「誠に作者にて侍る」(『去来抄』)と評された宝井其角の才知に惚れ込む俳人はいつの時代にもいるものですが、『興』の著者・村山半信氏もその一人。略歴によると、1956年、長崎市に生まれ、早稲田大学を卒業後、博報堂でCMや放送番組、メディアコンテンツなどの企画・制作に携わったそうです。「海程」「小熊座」を経て現在無所属。本名は信一郎で、俳号の「半信」は大の虎党であることに由来するというから愉快です。
『興』は第一句集で、章扉には炭太祇・加舎白雄・上島鬼貫・高桑闌更・与謝蕪村ら中興俳諧の発句を掲げるという洒脱な趣向もあります。愛する其角と結社の主宰のほかに学んだ俳人として渡邊白泉、杉田久女、波多野爽波、後藤比奈夫、川崎展宏、大牧広が挙げられていますが、句を読めば納得のラインナップです。
少女美し日本映画に火事多し
早世の少女夏いろのchouchou遺す
今月は泉について日経サイエンス
地方紙にもの包まれて夜店かな
古日記に餘寒とあるは楽しけれ
日本映画、少女趣味、日経サイエンス、地方紙、骨董屋や古書店に出ている古日記(そしてそこに使われている旧字体)などなどあらゆる種類の世俗のコンテンツを面白がり、俗を承知で俳句に仕立て上げる趣味性。
往年の日本映画や古日記を楽しんでいるだけでも好事家ですが、通人は突き詰めていけば、「日経サイエンス」のニッチな記事や「地方紙」でものを包むうらぶれた夜店まで、なぜか面白く見えてくるものです。こんなものまで面白いなら人生の時間が足りなくなって大変そうだと同情したりもしますが、さておき、こうした「通」の視点を受け止めてくれるのも俳句形式の懐の深さではないでしょうか。あるいは逆に、「日経サイエンス」までが妙味になる俳諧なるものと出会ってしまったがために、氏の目が肥えていったのかもしれません。
菜の花やキツチンで妻とすれ違ふ
絶叫に近いbye-bye夕永し
夫婦のどちらかが菜の花を調理するキッチン、何か声を掛けるでもなくお互いに体の向きを変えてぶつからぬようすれ違うときの絶妙な間合い。今生の別れでもないのでしょうに、人目を憚らず大きな声でバイバイを叫ぶ放課後の学生。「すれ違ふ」に含意を持たせたり、バイバイを洒脱に英語で表記したりと、表現の工夫も愉しい二句。
どちらも面白がりの精神が発揮された諧謔味のある句で、哀歓が同居しているのも共通します。
ぼろぼろの大観覧車だつた昭和
降る霙昭和の日々の濃と淡
昔ばなしは帯解きながら春没日
生粋の面白がりだからこそ、面白いもの、変なものがたくさんあった昭和が愛おしくてならず、といったところでしょうか。通である自分をさえ面白がり、その末になぜか哀歓が押し寄せてくるという風情です。三句目は、年寄りらしくふるまうお作法を教えてくれるかのようです。
巻末には「余興 芭蕉贋作」と題する一章が収められています。これは芭蕉の〈古池や蛙飛びこむ水の音〉をさまざまな人物が詠んだらどうなるかという、俳句による文体模写の試み。いくつか引きます。
中島敦
交(まじはり)を絶ちて哭(おら)ぶや洞(ほら)蛙
井上ひさし
降る雪や何も買はずに帰る道
橋本夢道
古池の資本主義者のかはづ等(ら)から搾取の毎日
中島敦(が詠んだら)の句は漢学の素養を持った最後の小説家であった中島敦の文体を模倣したもの。代表作「山月記」の冒頭にある「人と交を絶つて、ひたすら詩作に耽つた」という箇所からそのまま取ってきていますが、実はこの「交を絶つ」という語法は、「絶交する」と言わずに漢文訓読調にしている点で、この作家の文体を特徴づけるものです。「山月記」にはほかに「破産する」を「産を破る」と表現する箇所も有名です。著者はただ「山月記」の適当な一節を抜いてきているのではなく、中島敦らしさを意識しているのです。
井上ひさし(が詠んだら)の句は、「フルイケ」を中村草田男の「フルユキ」にずらし、「カハズ」と「カヘル」という二匹の蛙を詠み込んだ句。言葉遊びを連発するのが得意だった井上ひさしならば、芭蕉の古池の句というお題を与えられたら、こんなふうにやってみせたのではないか、というわけです。
橋本夢道は〈無礼なる妻よ毎日馬鹿げたるものを食わしむ〉(『無礼なる妻』1954年)などの句で知られる自由律俳人。プロレタリア俳句運動に関わった彼ならば、芭蕉と蛙の関係に資本主義を見てとり、このような長律の自由律俳句にしたかもしれません。(編集部)