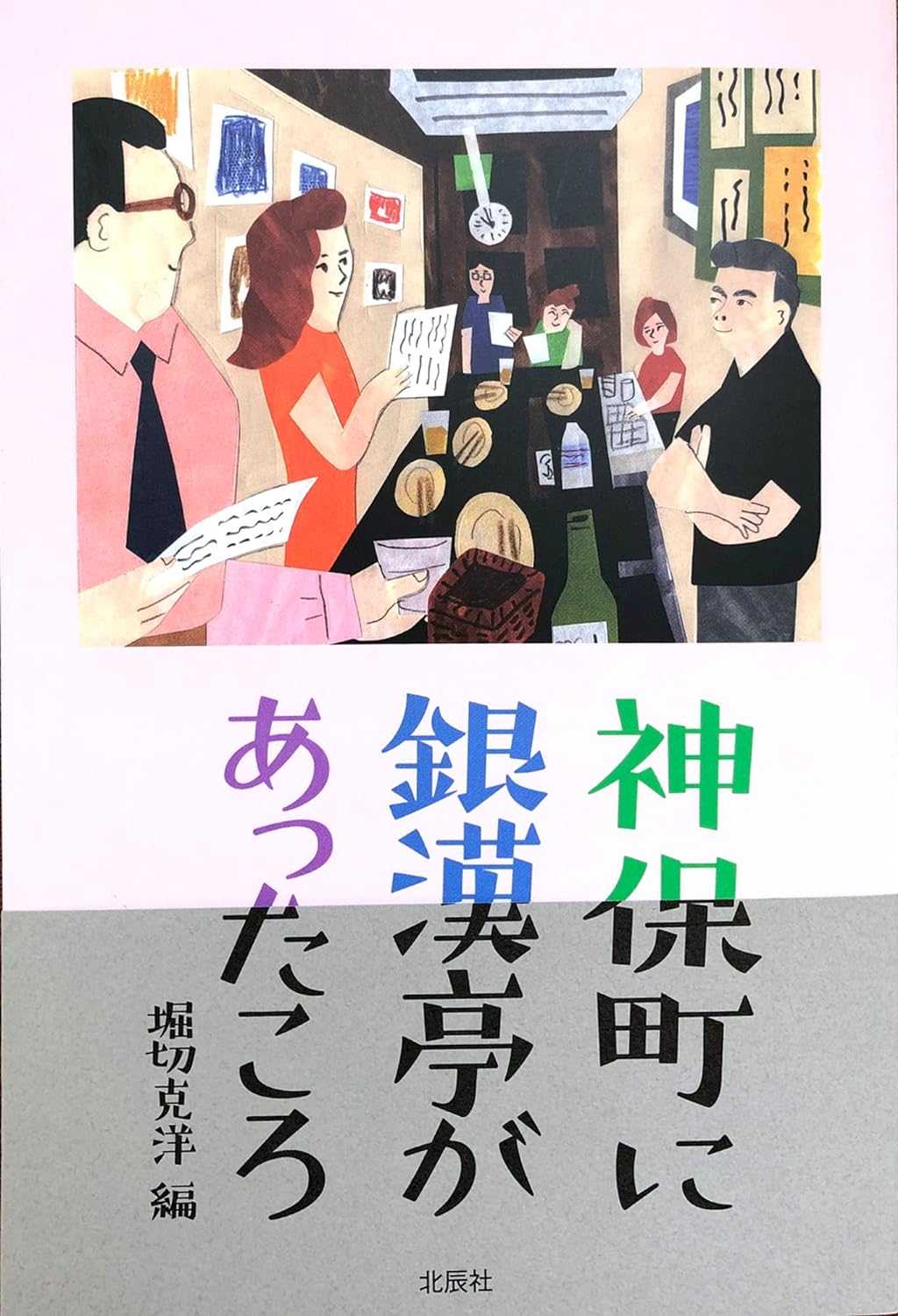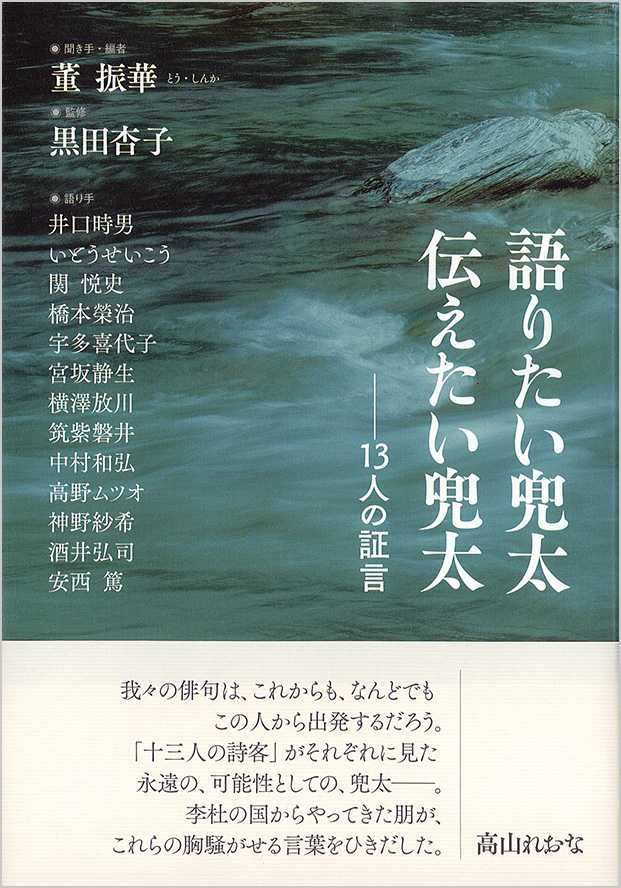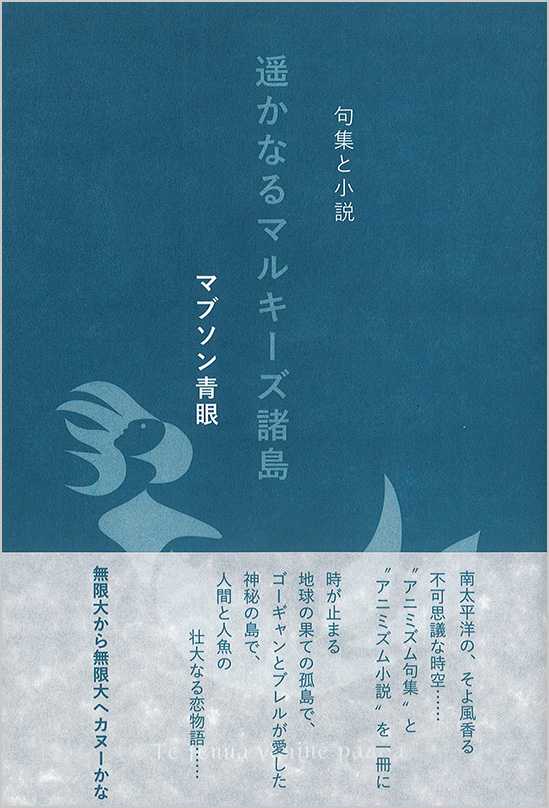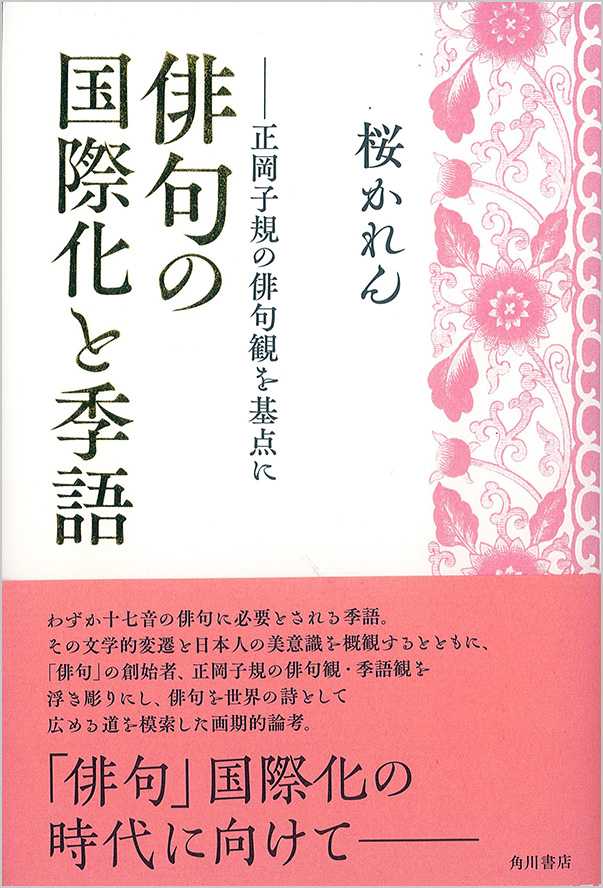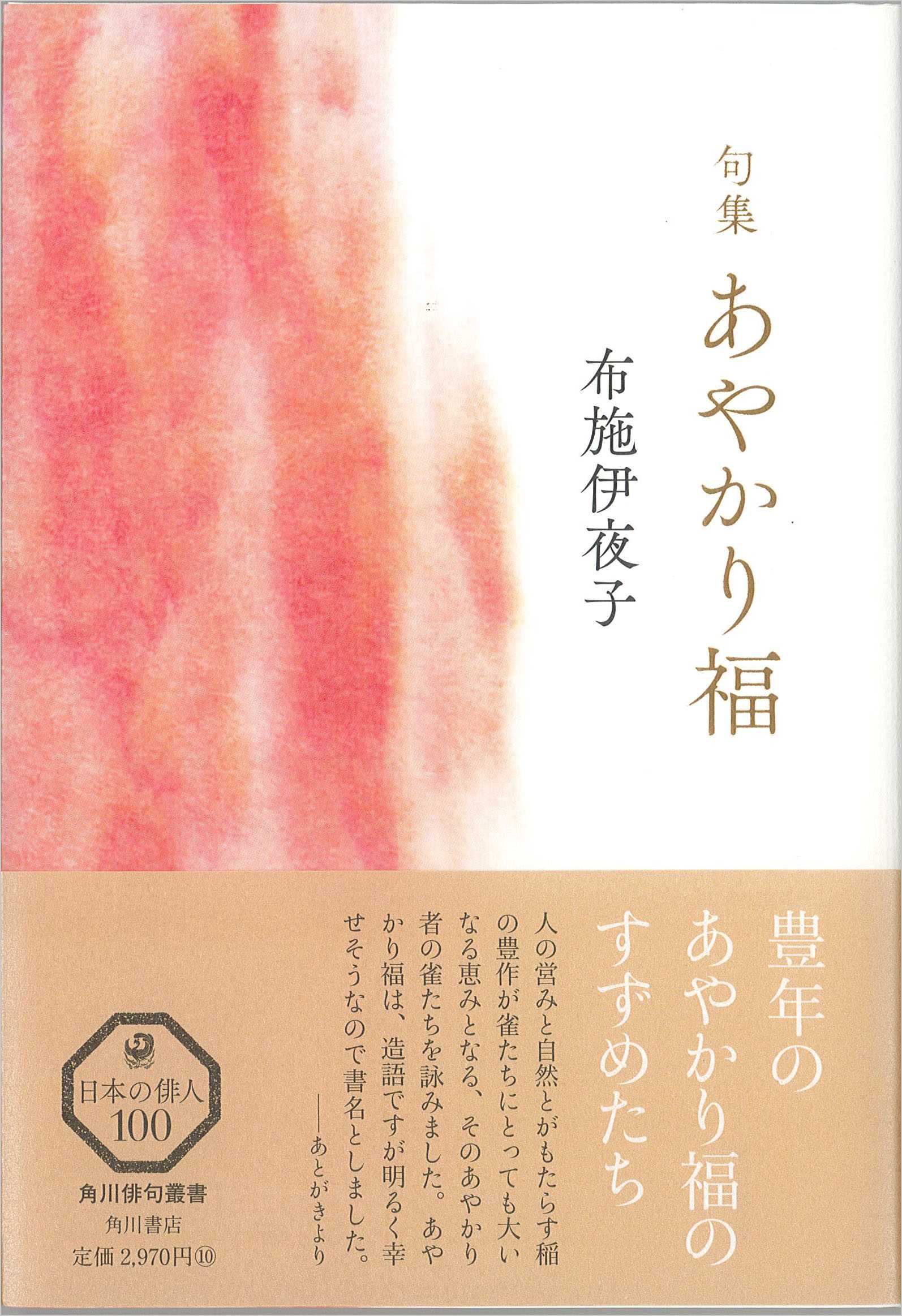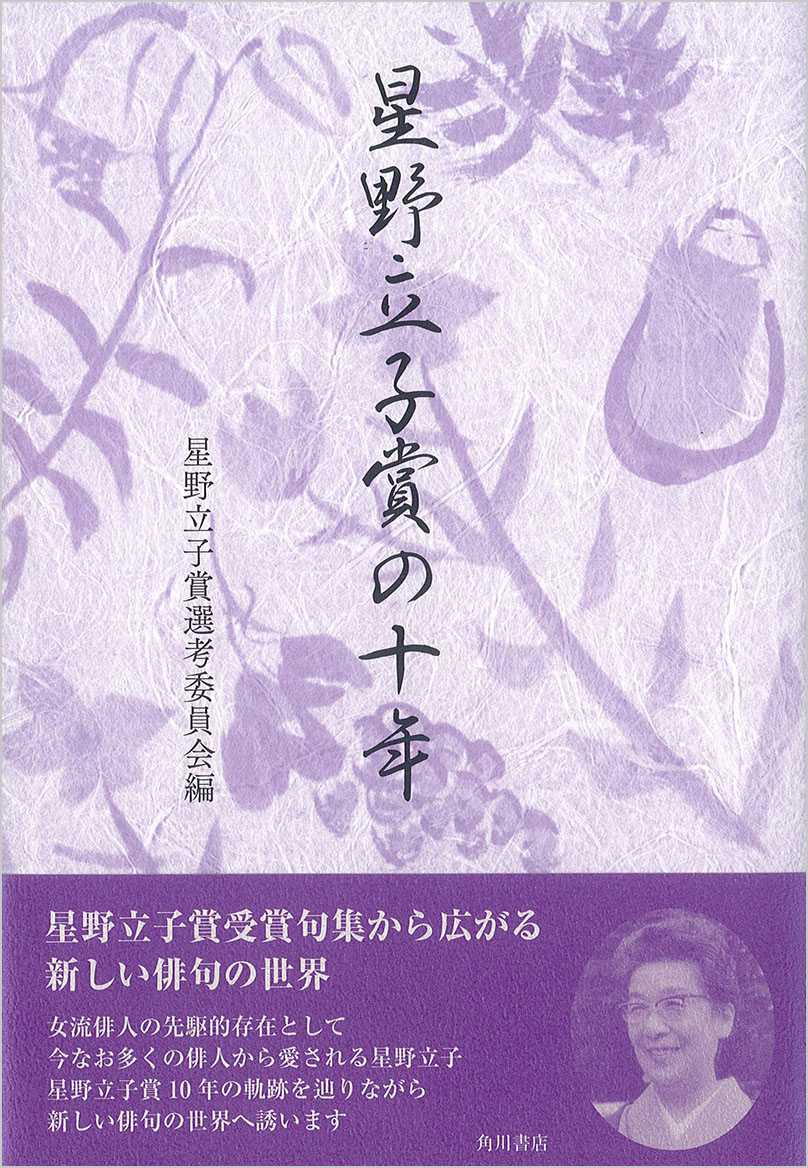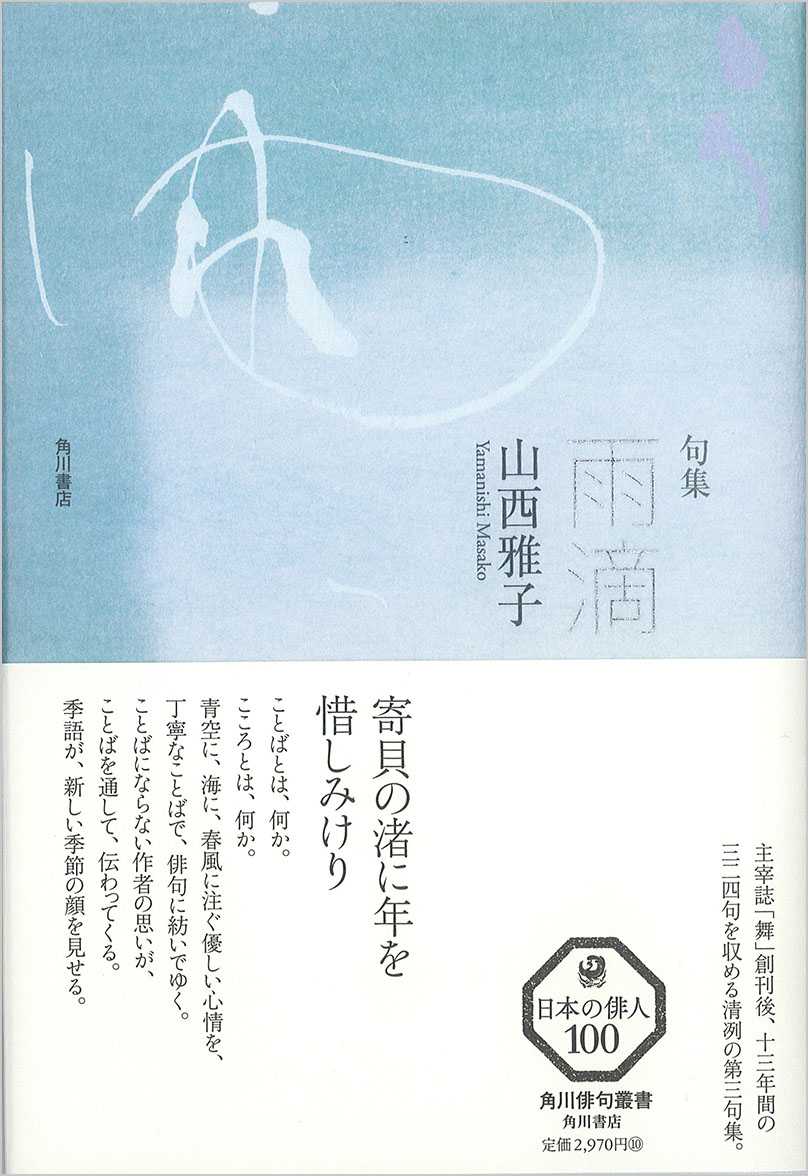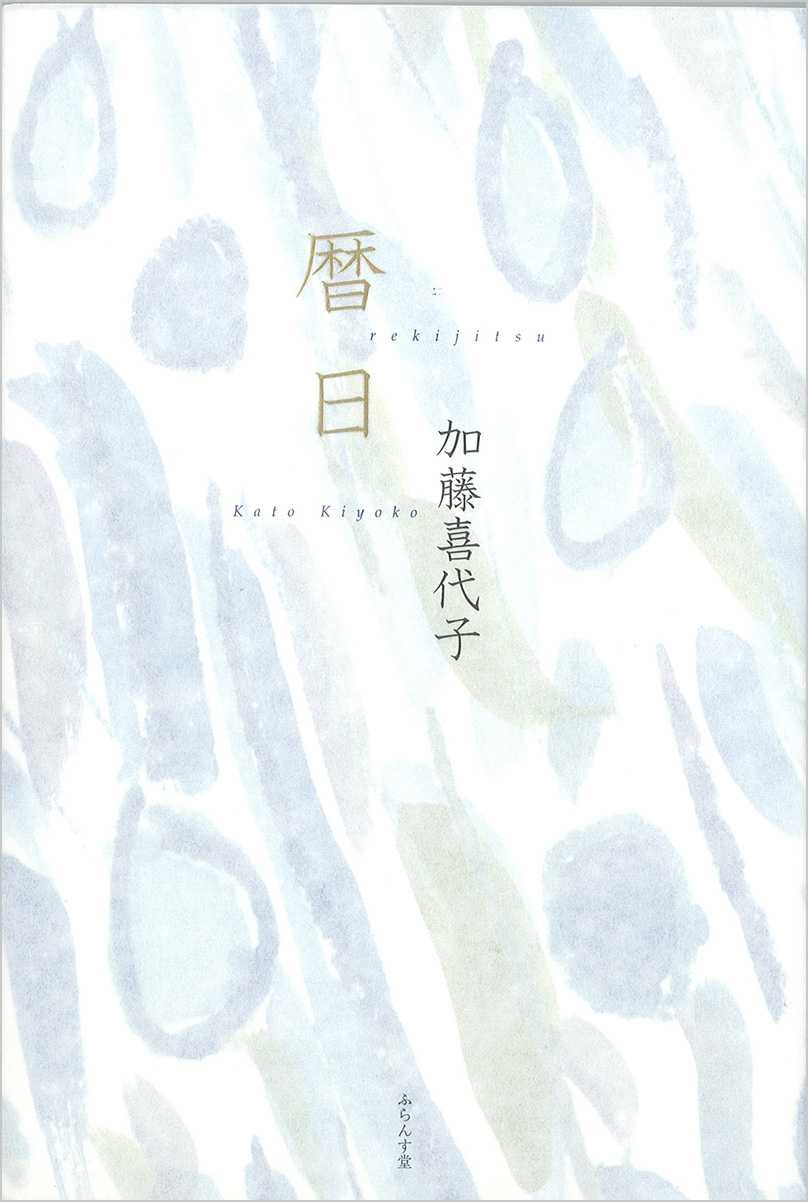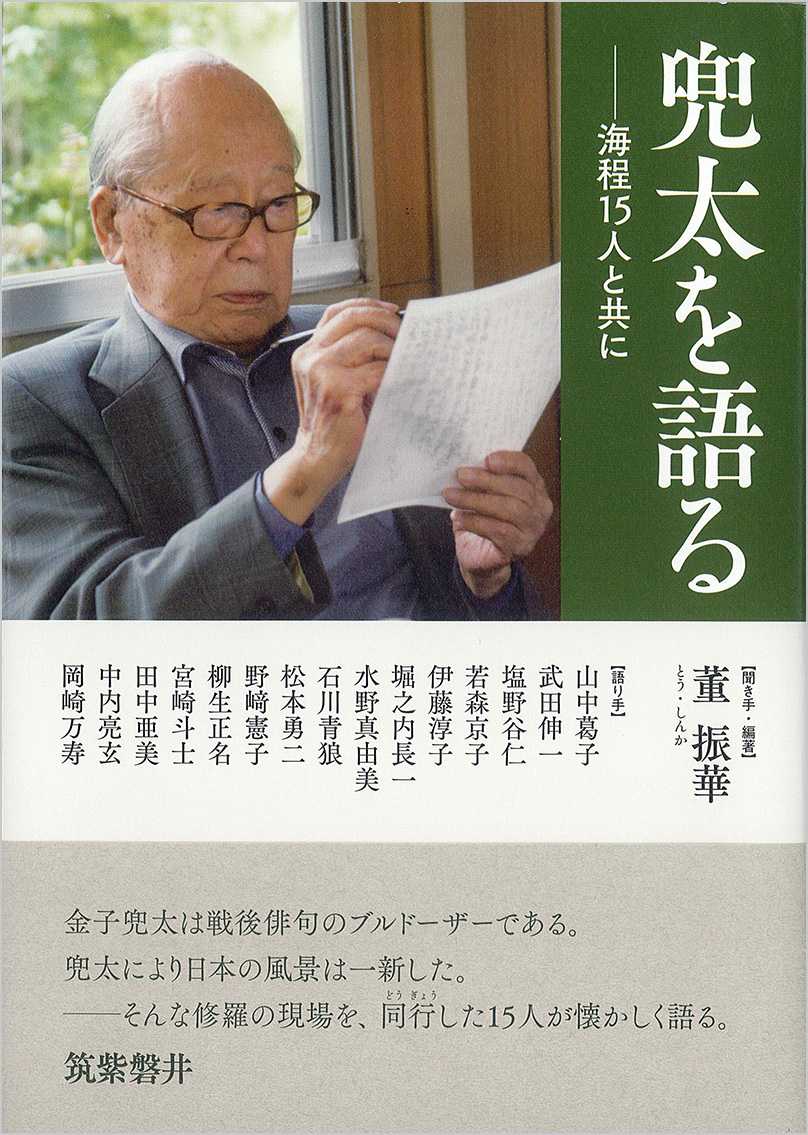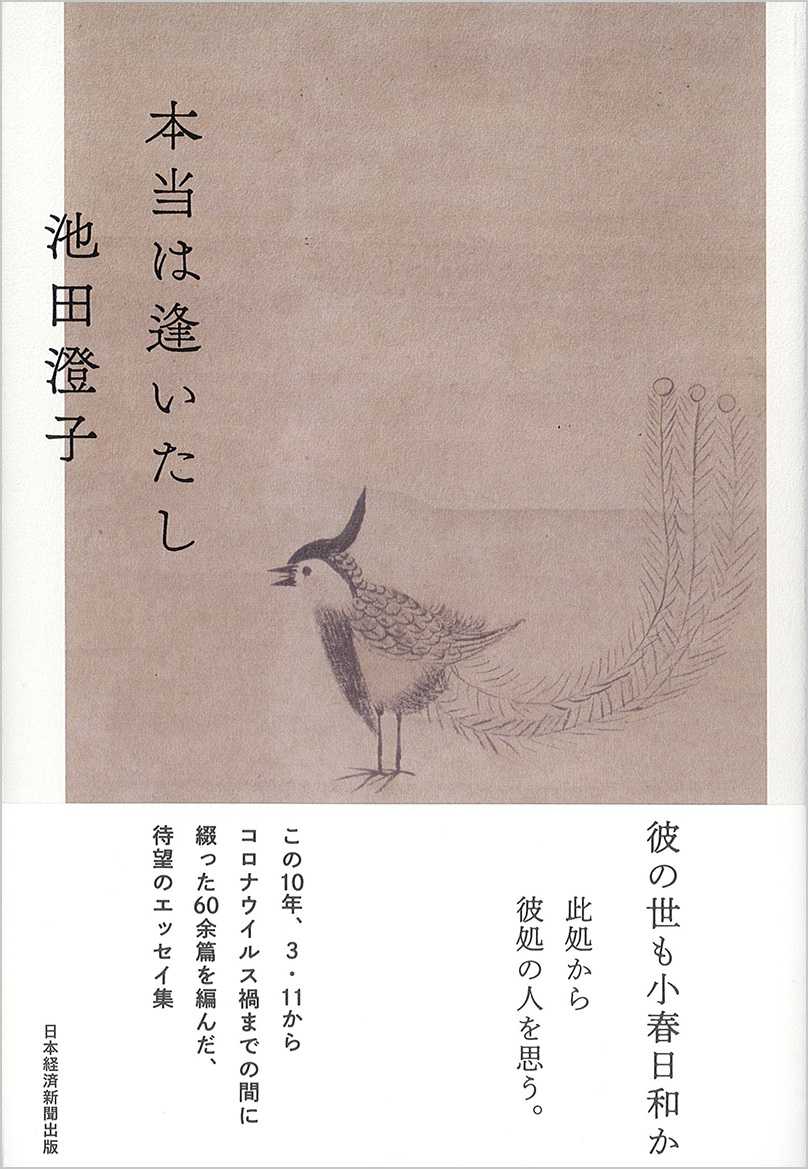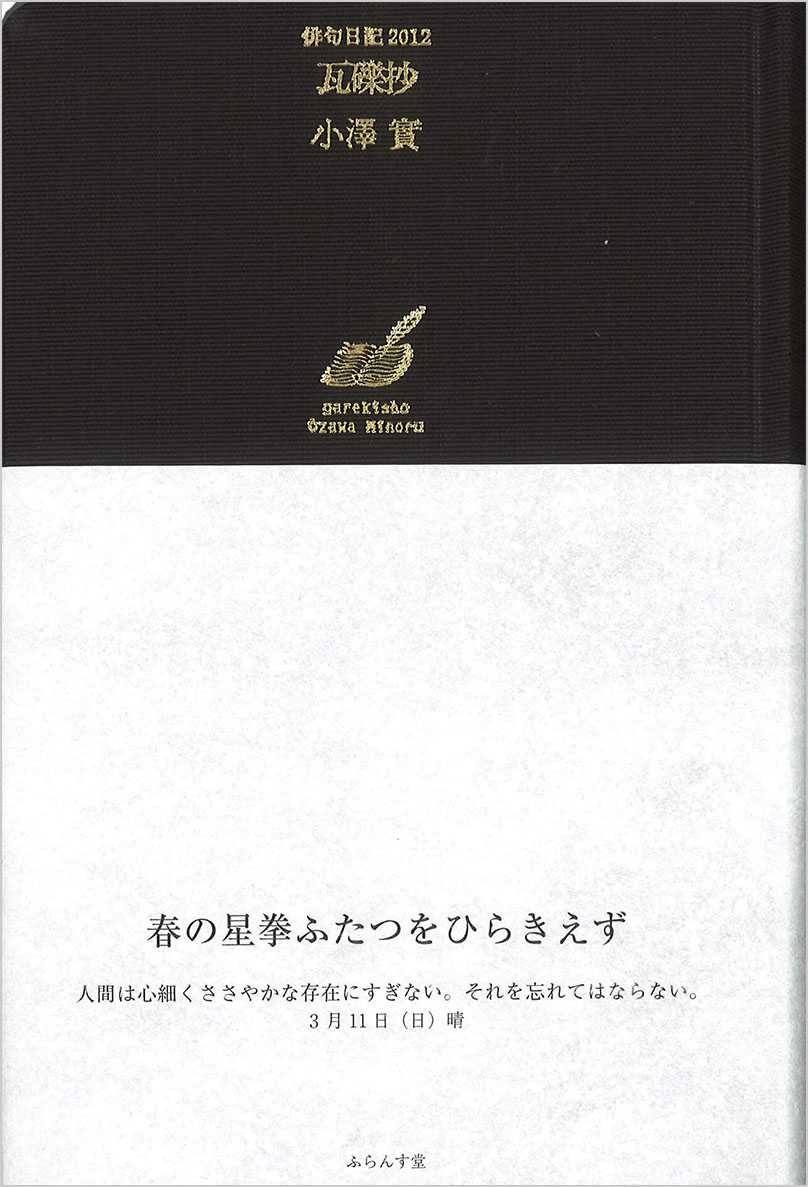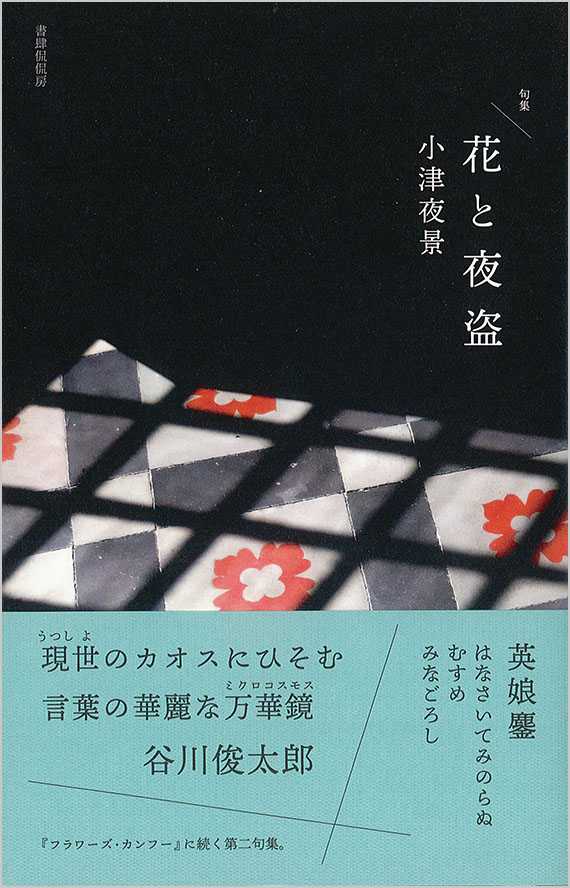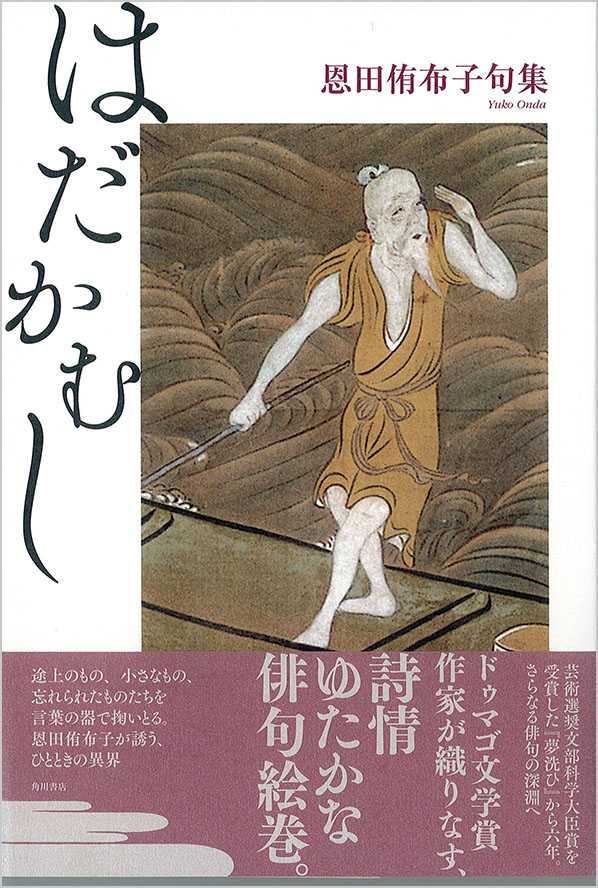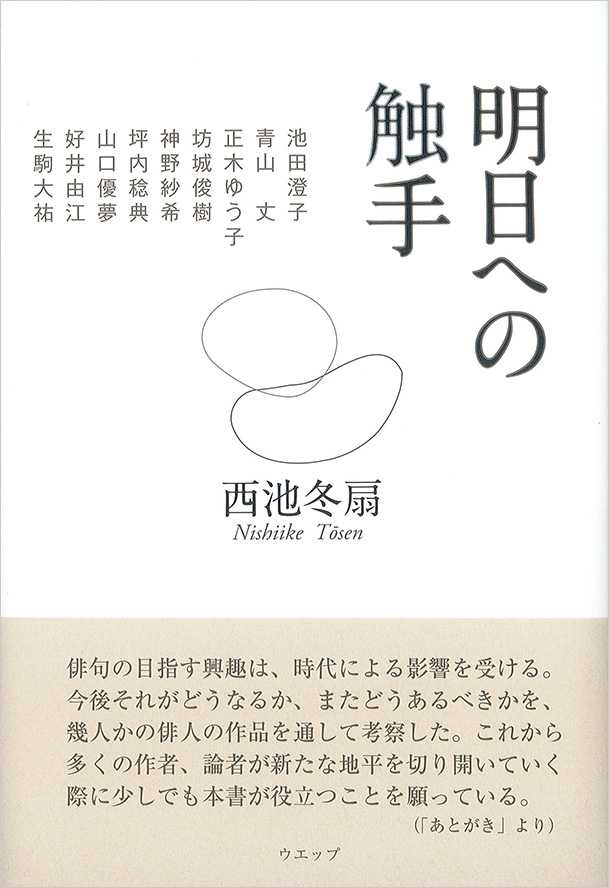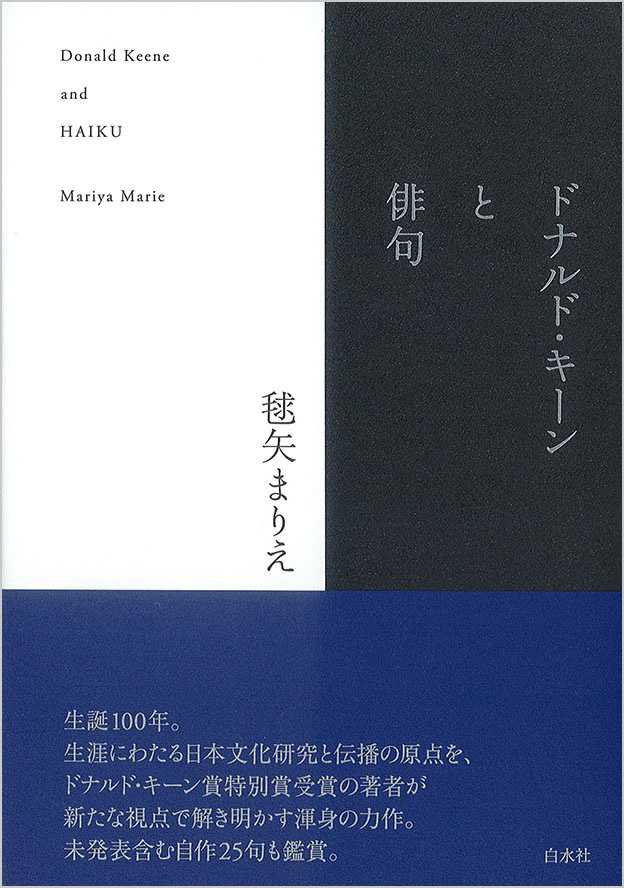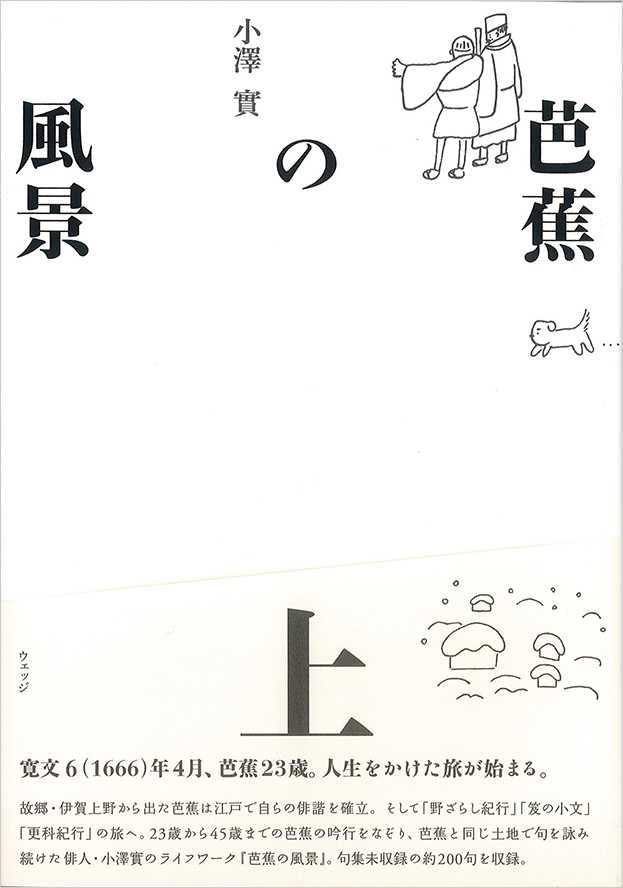本の森
編集部へのご恵贈ありがとうございます
2021年以後の刊行書から順不同でご紹介します
董振華編『語りたい兜太 伝えたい兜太 13人の証言』
令和4年12月
コールサック社
定価:2500円+税

戦後の俳句界に大きな足跡を残した金子兜太。世代の異なる13人の俳人・俳句関係者が兜太の記憶や自身の考える兜太の大きさを語ったインタビュー集です。井口時男、いとうせいこう、関悦史、橋本榮治、宇多喜代子、宮坂静生、横澤放川、筑紫磐井、中村和弘、高野ムツオ、神野紗希、酒井弘司、安西篤の各氏が登場します。
最初に登場する井口時男氏は近年、兜太に注目している文芸評論家です。兜太と出会ったのは最晩年の2016年と、過ごした時間はあまり長くはありませんでしたが、雑誌「兜太 TOTA」の編集委員となり、同誌に本格的な兜太論を寄せる中で、独自の兜太像を打ち出すに至りました。インタビューで氏は兜太作品について、社会性と芸術性を二者択一にせず、メタファーによって統合したこと、そしてもう一つ、文芸でしばしば用いられるイロニーの手法を用いず、ストレートな表現を選択したことに特徴があった、と力説します。
いとう氏は1990年にはじまった伊藤園「お~いお茶新俳句大賞」の審査の場で兜太と出合い、その後最晩年までマスメディアで仕事を共にした人物。「新俳句大賞」の審査の仕事は、兜太と森澄雄の丁々発止の議論が面白く、また勉強になったといいます。この縁で2001年には共著『他流試合 兜太・せいこうの新俳句鑑賞』を出版、同書刊行のために5回にわたる対談が行われ、氏は兜太に思うままに質問をぶつけながら、俳句、ひいては詩のことばというものに迫っていきました。
2010年代のイベントでしばしば兜太に会うことがあったという関氏。詳細な記録と記憶に基づいて兜太との関わりをふり返ります。自身の句集が宗左近俳句大賞にノミネートされ、公開審査に出向いた際、審査員だった兜太に「この関というのは、才気があっていろいろやっているが、韻文になっていない。散文だ。作者が目の前にいたらぶん殴ってやる」と言われたとか。この出来事などを挙げて氏は「兜太にとっては、「韻律」が命だったということでしょうね。弾力のある文体、弾む肉体のような文体」と考えます。
兜太は俳壇随一の人気者として、そのキャラクターを愛された俳人でもありました。「件(くだん)の会」同人として同会と縁の深かった兜太と交流があった橋本氏は、同会が「みなづき賞」を東京新聞の「平和の俳句」に与えた際、自身の妻が花束の代わりのさくらんぼの枝を渡す役目を担ったときの出来事を紹介しています。渡したはいいものの、会場の雰囲気がいまひとつ盛り上がらず、氏は咄嗟に司会の黒田杏子に、「黒田さん、握手、握手」と指示を出しました。すると杏子は「今、ご亭主の橋本栄治さんから『女房と握手してもらってください』という声がありました」と盛り上げ、さらに兜太は、握手ではなくハグをして湧かせた、というのです。
話はこれで終わりません。サービス精神に感心し、鮮明なハグの写真は次号の会誌の話題の一つにもなると考えていた氏のもとに、兜太から留守中に「恥をかかせた」と詫びの電話がありました。「謝るなら妻へ謝ればそれで済む」と考えた氏でしたが、この出来事から氏は、兜太は「外見や行動からは想像できぬ、相手のことを人一倍思いやる方」と知った、といいます。
若き日に俳句をはじめたときには伝統的な結社に属していた宇多喜代子氏は、誕生日に父から兜太のベストセラー『今日の俳句』(1965年)をプレゼントされて面白く読んだところ、句会にいた周囲の明治生まれの大人たちは戸惑い、「あれは悪い本だから、読むな」と止められたといいます。前衛俳句が既存の俳人にどのように受け止められていたのかが窺われるエピソードです。プレゼントしてくれた父はむしろ兜太の俳句を面白がる存在だったとか。
『今日の俳句』は社会性俳句運動から造型俳句論へと発展してゆく時期の兜太が、自身の強靱で独特の俳句観を、一般向けに説き直した、戦後俳句史に残る一冊です。
高校卒業後に土木事務所の職員として働き出し、平行して夜間学校にも通っていた時期の高野ムツオ氏も、書店でこの本と出会ったといいます。小学生時代から俳句を書いていた氏は、高校生の終わりくらいから社会性俳句・新興俳句に興味を持ち、お寺の本棚にあった雑誌「俳句」を耽読、兜太の名前を知っていました。「「古池の『わび』よりダムの『感動』へ」というキャッチフレーズ、表紙に掲載されているカラー印刷の句の数々、装丁もとてもよかった。(中略)そこにはそれまで自分が目にしたことのない俳句の世界が展開されていた。今ふり返ると、私がその本でもっとも惹きつけられたのは、造型俳句という考えより、こうした新しいことを主張する金子兜太という人間の魅力と可能性でした」。
この本の中で兜太は自作〈強し青年干潟に玉葱腐る日も〉を取り上げて解説しています。同書での言及もあってこの句は兜太の代表作の一つとなっているのですが、宮坂氏によればこの句の初出は、藤岡筑邨の「竜胆」だ、といいます。高校時代に筑邨と出会った宮坂氏は、同誌の編集に携わるようになり、大学一年生のとき、俳壇で活躍する俳人に作品を依頼、そのとき送られてきたのがこの句だったというのです。「どきどきして、私宛に貰ったような気がしましたね」。
また兜太は、前衛俳句/伝統俳句という二項対立が瓦解したあとの俳壇において、人間関係のハブとしての役割を担った俳人でもあります。俳壇付き合いがほぼなかった横澤氏は、直接の面識はないままに俳論によって名前を覚えられていきなり総合誌の座談会に呼ばれ、その後成田千空の蛇笏賞の授賞式の機会には、黒田杏子のもとへ連れられて紹介され、以後、杏子・兜太との濃密な交流がはじまりました。
兜太の目配りの広さについては他にもさまざまな証言があります。1999年に兜太は「俳壇」にて、若手俳人らと意見交換をする座談会の司会の仕事をしています。その際に呼ばれた一人が筑紫氏。氏はこれより先に飯田龍太を「六分方」批判する『飯田龍太の彼方へ』(1994)という評論を刊行しており、龍太を意識するところのあった兜太はこれを読んでいたといいます。
名句誕生の現場ということでは、神野氏が兜太の平成期の代表句〈子馬が街を走っていたよ夜明けのこと〉について語っています。この句は神野氏が司会を務めるテレビ番組「俳句王国」の句会に出された句だったそうです。ゲストの渡辺えり氏がこの句について「戦争か何かで日本がもうだめになってしまった、滅びてしまった、もうだめだという時にどこかで生まれた子馬が廃墟の中をさっと走っていく。瓦礫の中の命の息吹だ」と鑑賞し、兜太は「今の解釈で合っているでしょう。私の句です、ありがとうござんした」と満足そうだったのだとか。
この人に語らせたい、と思わせる何かがあったのも兜太という俳人の大きさでした。中村氏は自身の主宰する「陸」の講演を兜太に打診した際、演題を求められ、兜太のかつての句集『詩経国風』についての話をリクエストしたといいます。この『詩経国風』は兜太の作風の境目に位置する句集でありながら、批評が少なく、また兜太自身も言及することがあまりなかった句集でした。インタビューでは、講演で兜太が語ったこの句集での「失敗」が具体的に紹介されています。
「海程」という兜太の城で彼と関わった俳人たちの語りは、本書と同じく董氏が編んだ『兜太を語る 海程15人と共に』にも収められているのですが、本書にも2人の俳人が参加しています。1人目は10年間の地方生活を終えて東京に戻ってきた時期の兜太と出会った酒井弘司氏。「海程」創刊を間近で見た氏は、当時の俳壇が高浜虚子の死去、60年安保の反対運動、現代俳句協会の分裂という激動の中にあったことを指摘し、このような時代背景が兜太に「海程」創刊を決意させたのではないか、と推測します。もう1人の安西篤氏も同じく「海程」の黎明期を知る人物。当時所属していた「胴」の忘年会に兜太が現われ、勧誘されたのだといいます。氏はそれ以前から兜太の句を雑誌で読み、衝撃を受け、「この人と俳句が作れたらなあ」と願い、「胴」在籍のまま「風」に投句していたのでした。
兜太と出会った時代、距離感、立場が異なる13人のインタビューはそれぞれに特徴的な兜太像を多面的に描き出し、インタビュー内のさまざまなディティールは結び付き合い、響き合いながら、金子兜太という一人の俳人が存命中に放った存在感を雄弁に語ります。13人それぞれが、単なる回顧談を超える「兜太論」を、談話という形式で語り起こすことを意識していることが窺えるインタビュー集です。(編集部)
-
09月30日
『神保町に銀漢亭があったころ』堀切克洋編 -
07月30日
『森は今』西池みどり句集 -
07月24日
『語りたい兜太 伝えたい兜太 13人の証言』董振華編 -
05月28日
『句集と小説 遙かなるマルキーズ諸島』マブソン青眼 -
05月21日
『俳句の国際化と季語 正岡子規の俳句観を基点に』桜かれん -
05月13日
『あやかり福』布施伊夜子句集 -
04月30日
『星野立子賞の十年』星野立子賞選考委員会編 -
04月23日
『雨滴』山西雅子句集 -
04月16日
『暦日』加藤喜代子句集 -
04月09日
『兜太を語る 海程15人と共に』董振華編 -
04月02日
『本当は逢いたし』池田澄子 -
03月26日
『俳句日記2012 瓦礫抄』小澤實 -
03月19日
『水と茶』斉藤志歩句集 -
03月12日
『花と夜盗』小津夜景句集 -
03月05日
『はだかむし』恩田侑布子句集 -
02月19日
『黛執全句集』 -
02月19日
『明日への触手』西池冬扇 -
02月12日
『ドナルド・キーンと俳句』毬矢まりえ -
02月12日
『芭蕉の風景』(上・下)小澤實