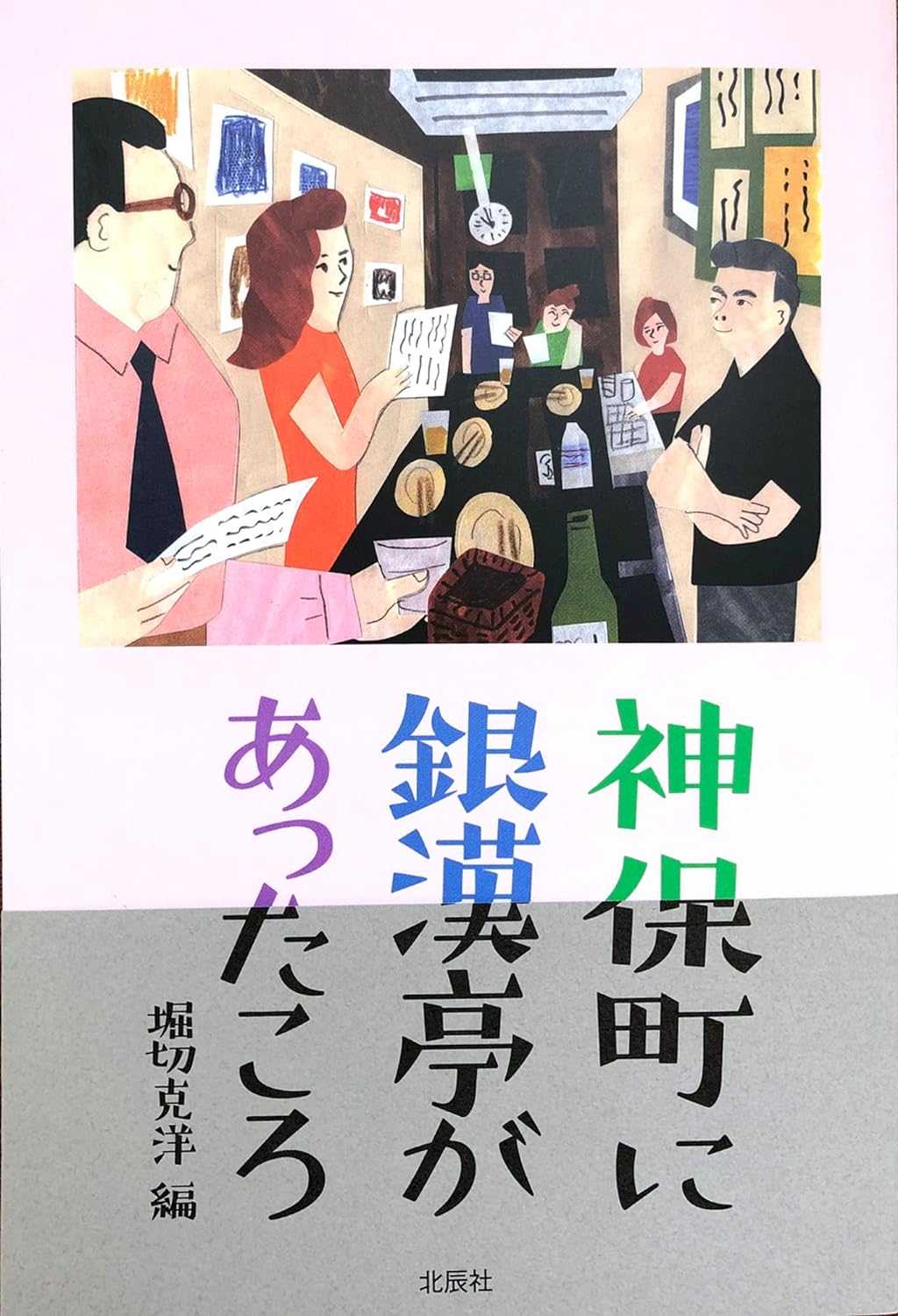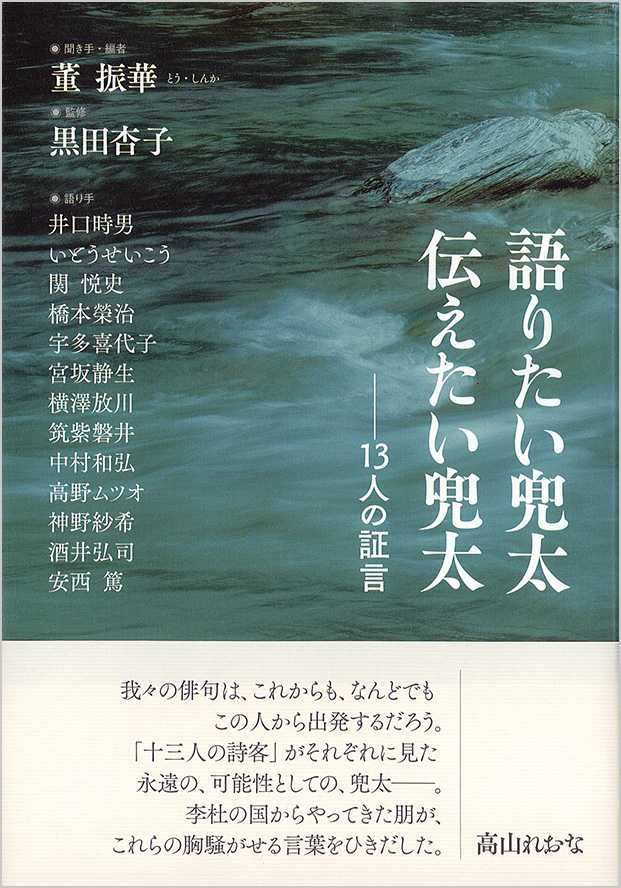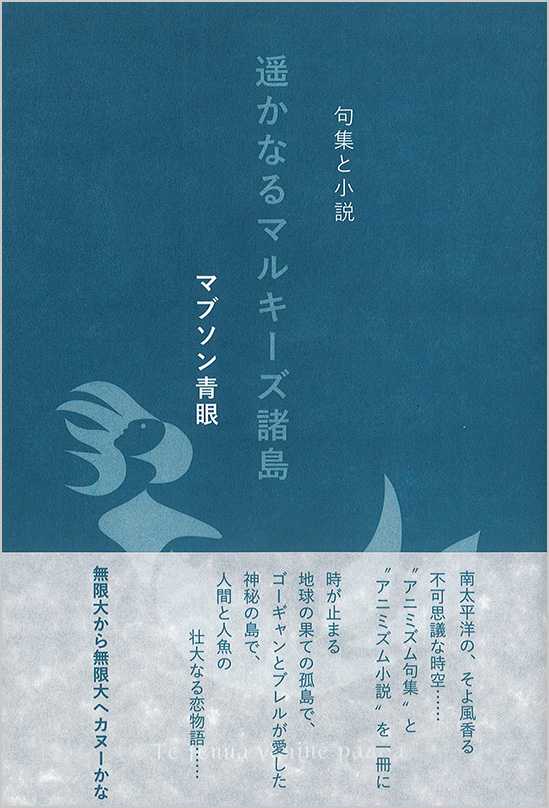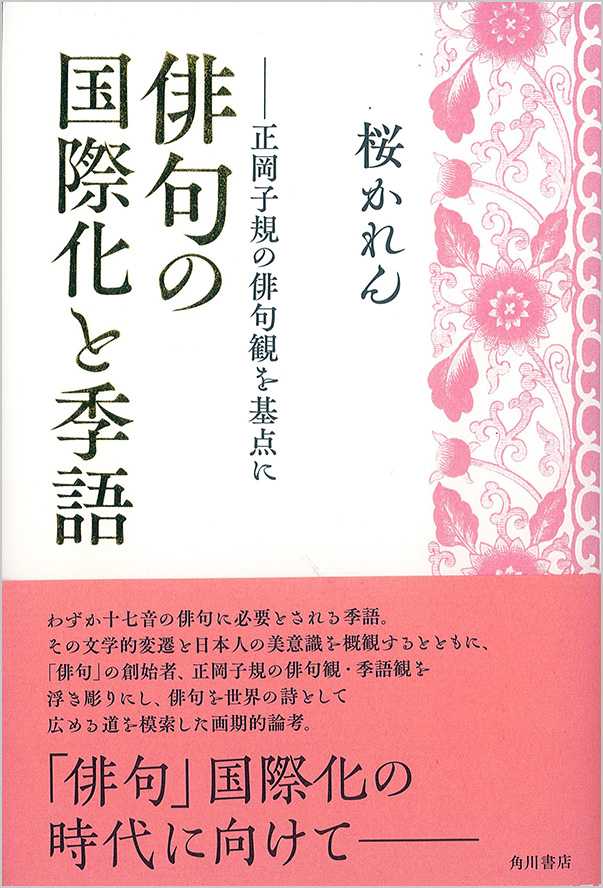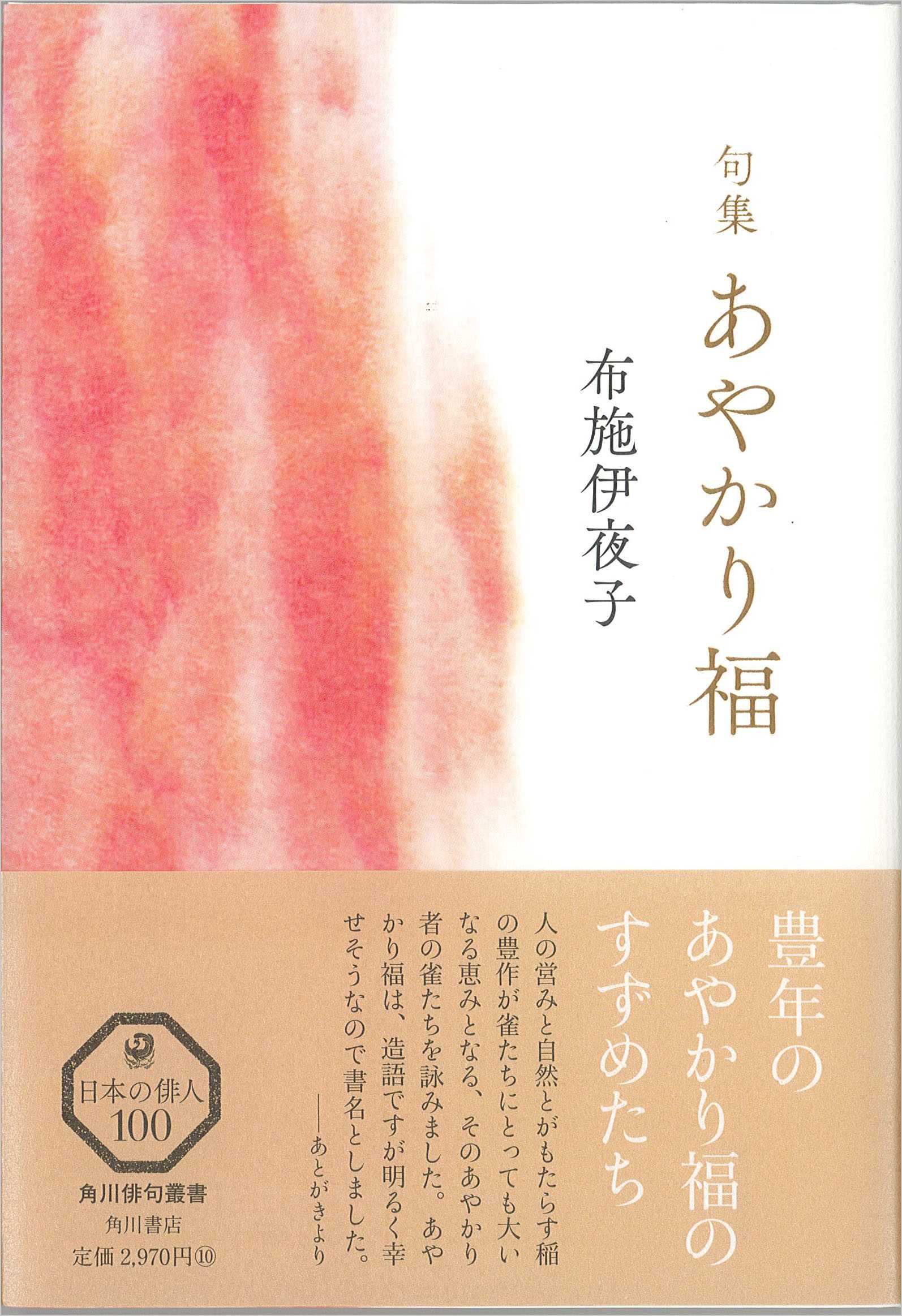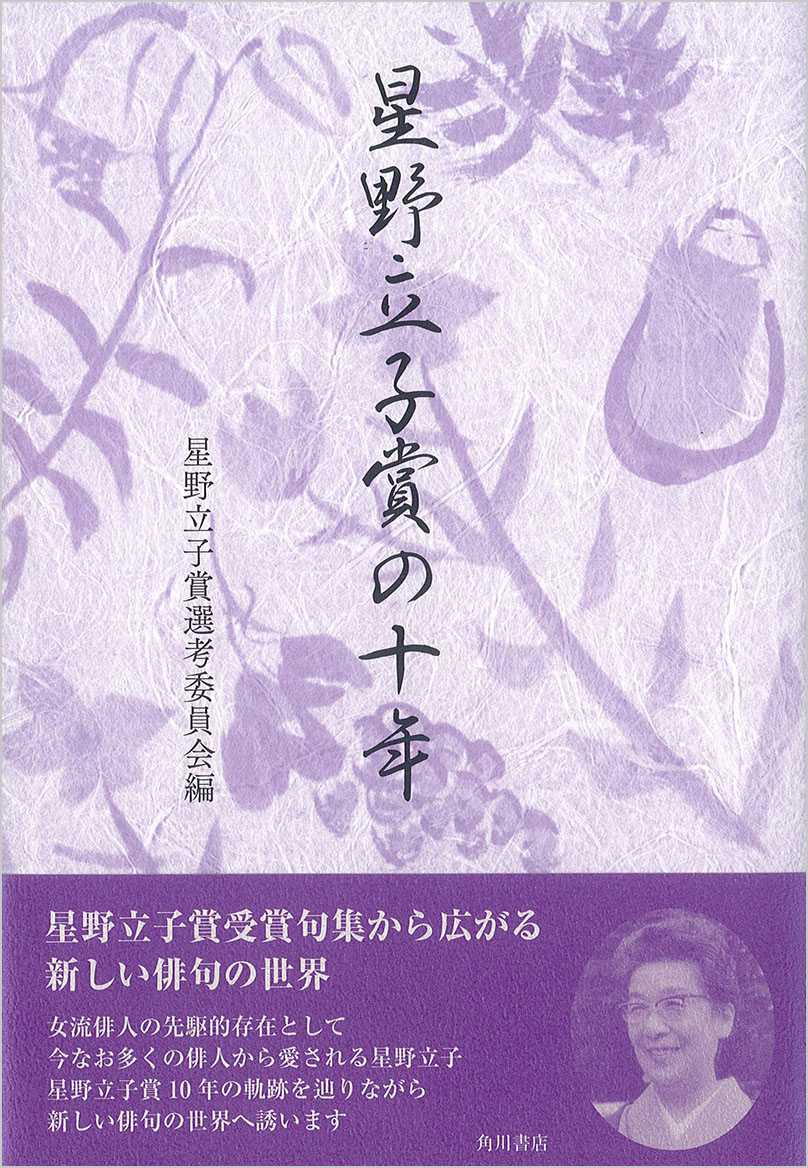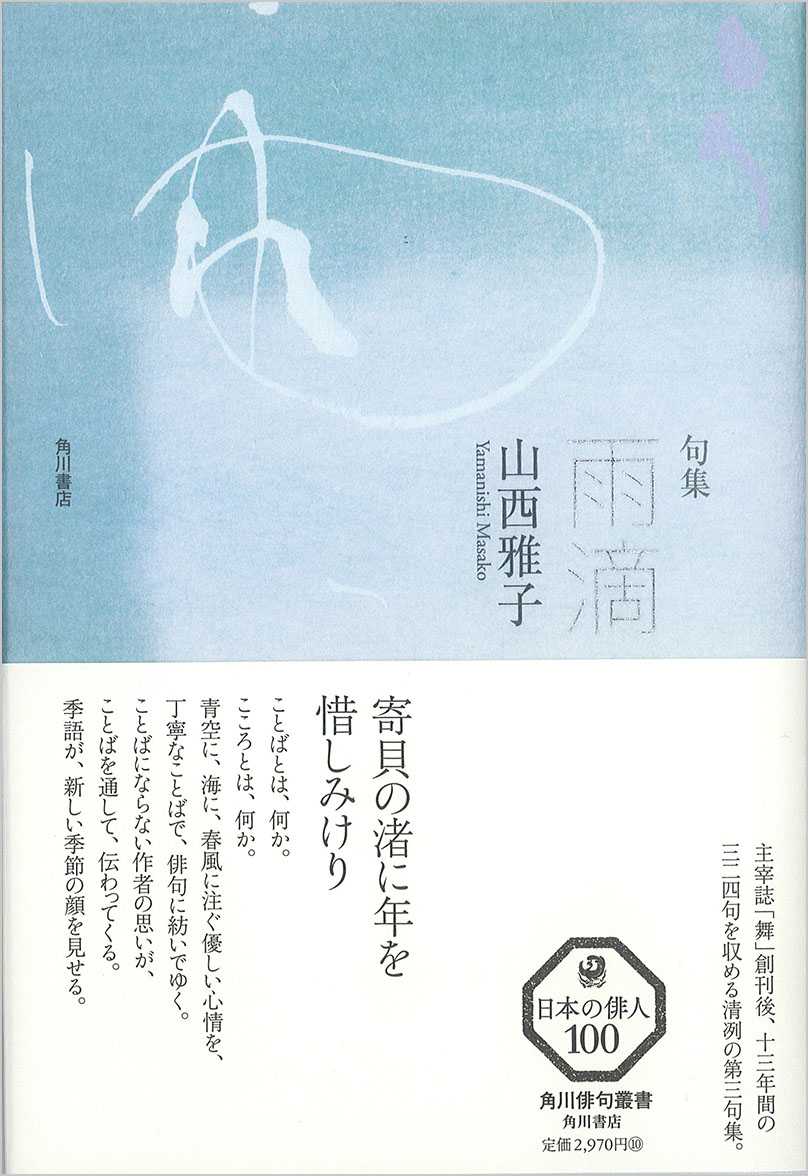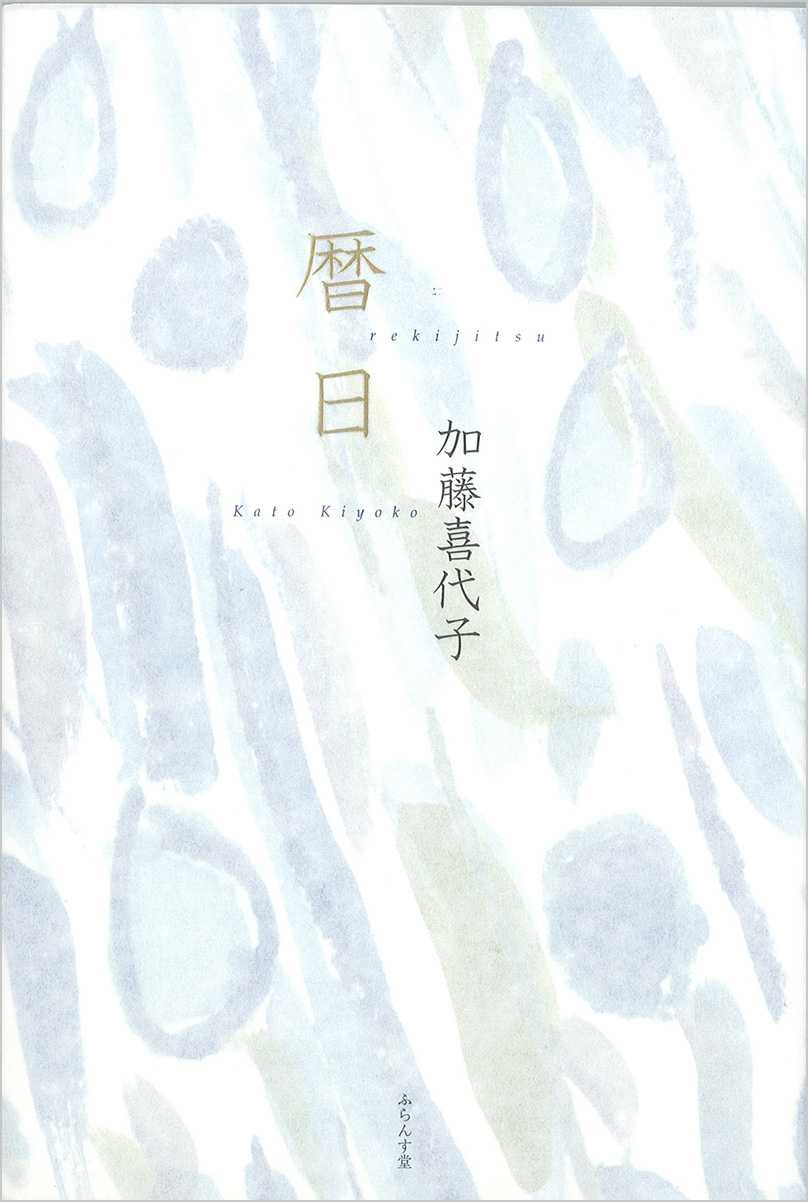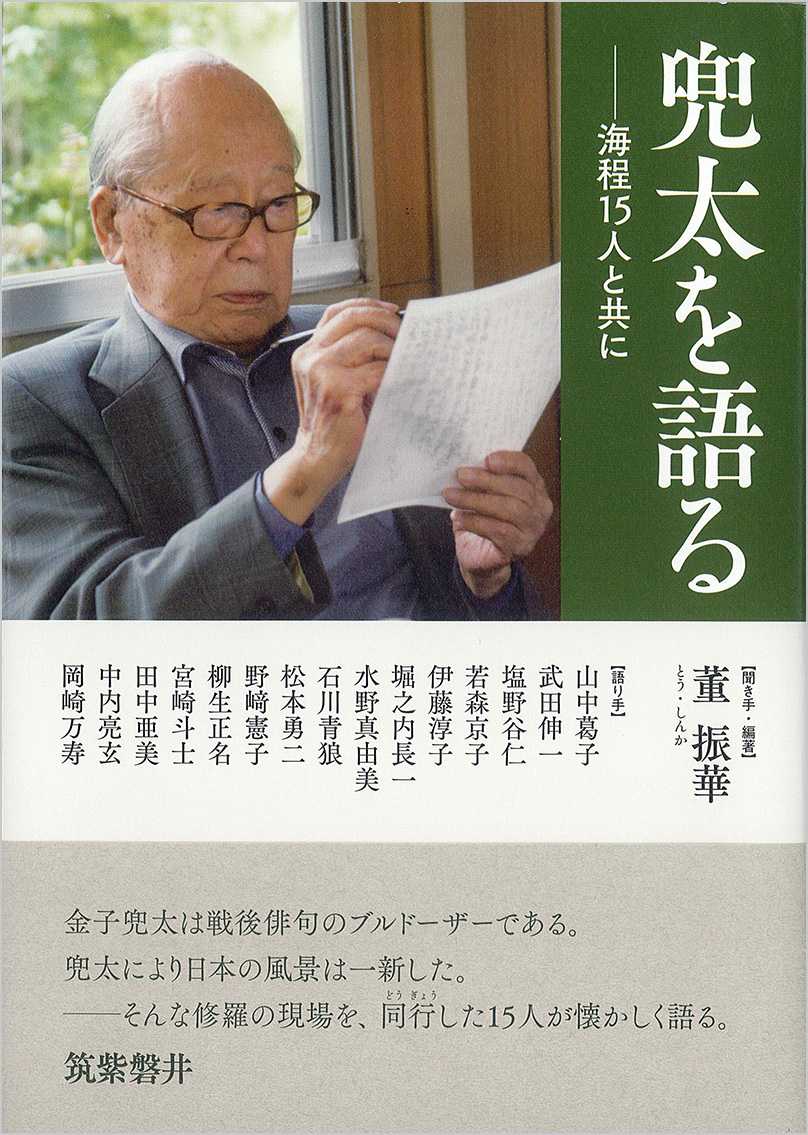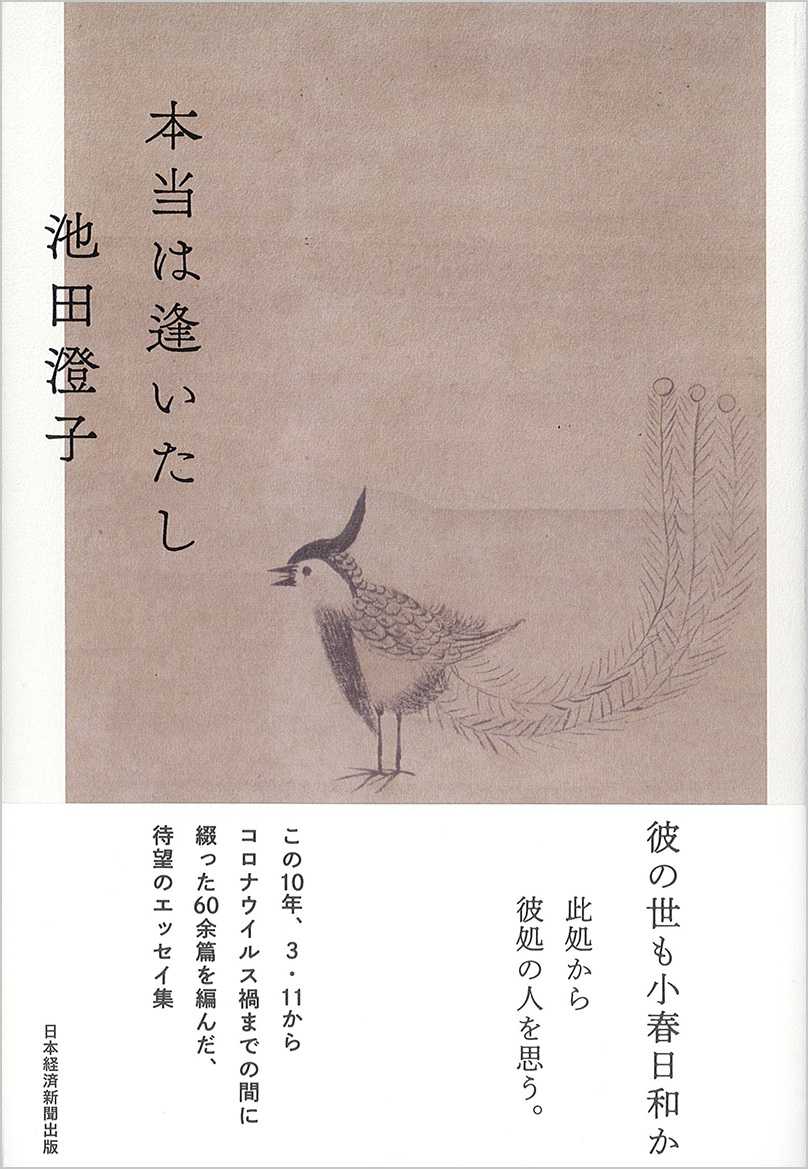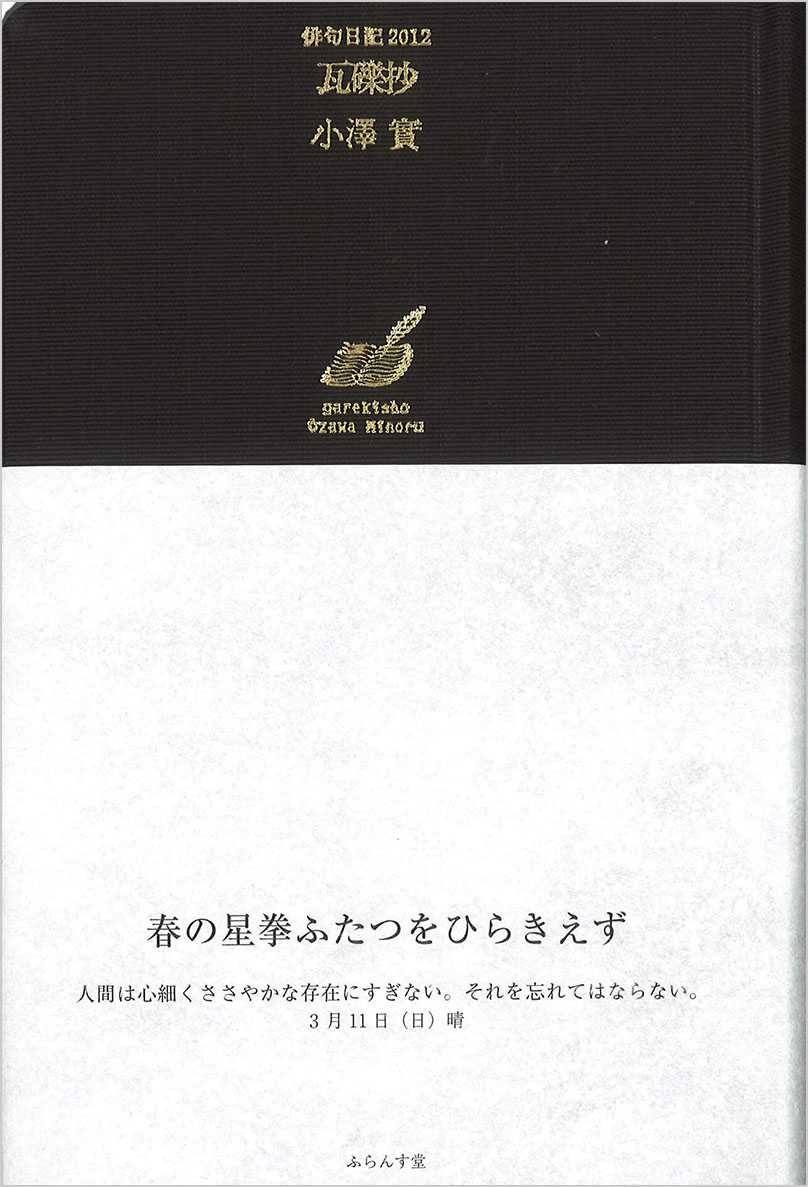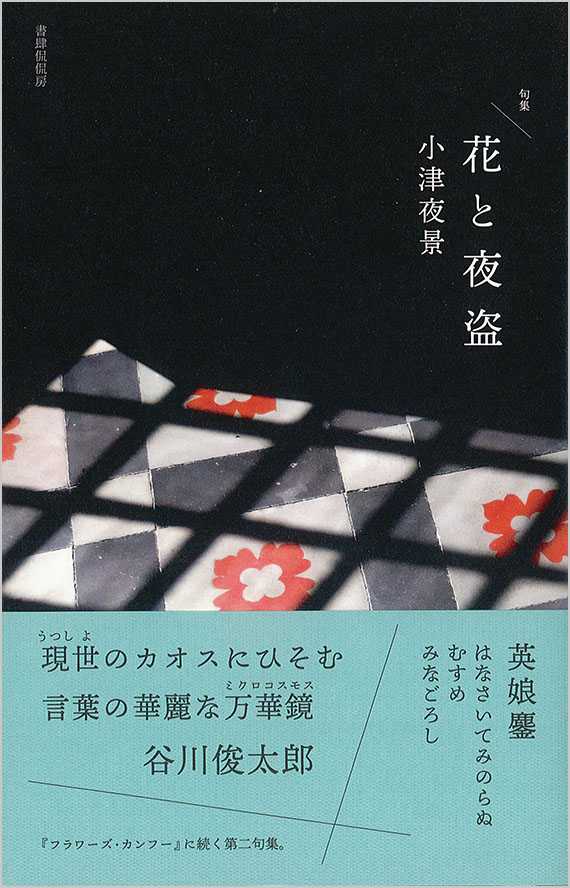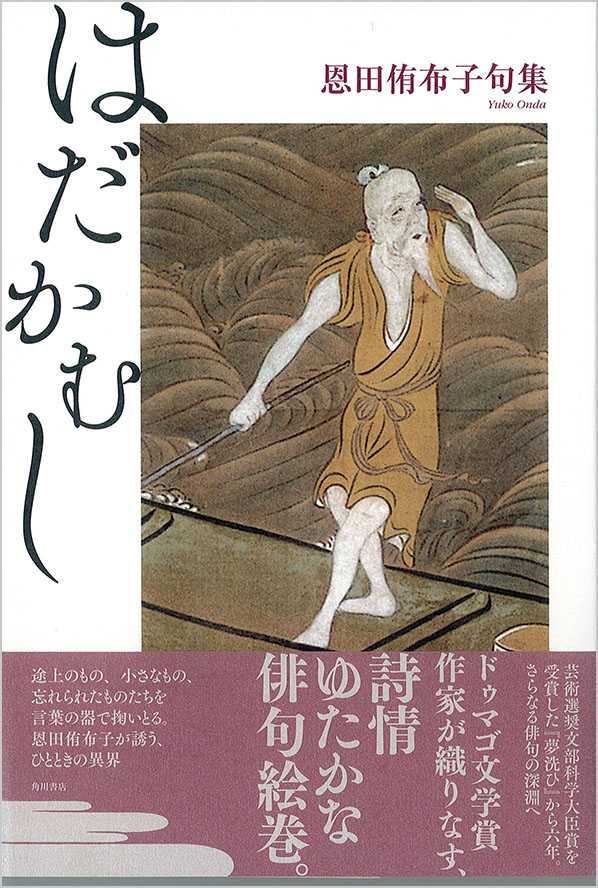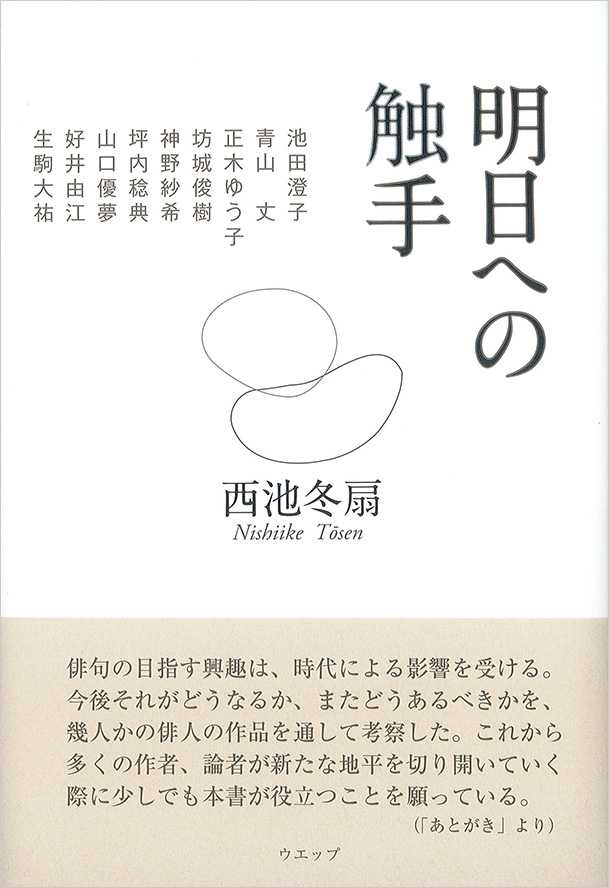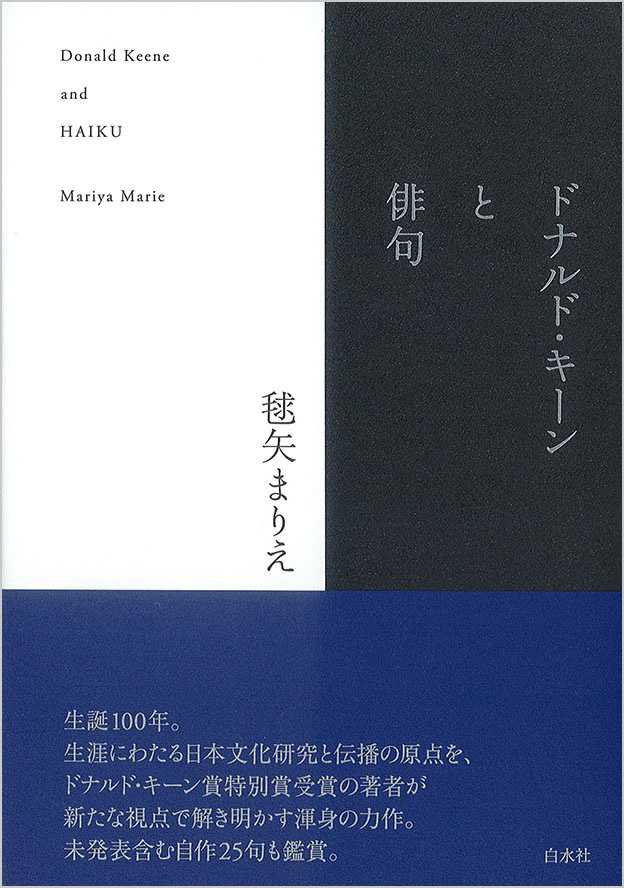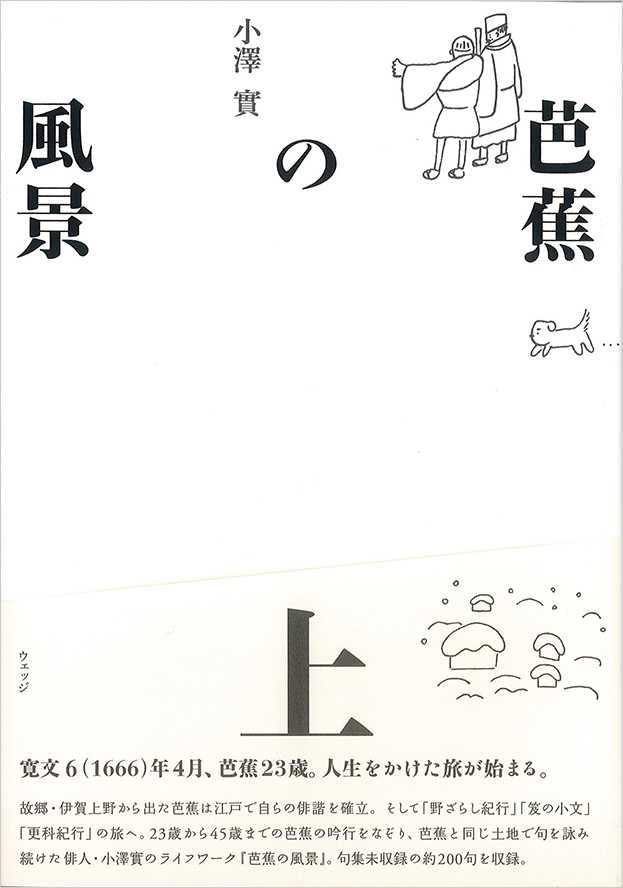本の森
編集部へのご恵贈ありがとうございます
2021年以後の刊行書から順不同でご紹介します
桜かれん『俳句の国際化と季語 正岡子規の俳句観を基点に』
令和5年3月
角川文化振興財団
定価:3000+税

明治20年代から30年代にかけ、近代的な文学観によって俳句というジャンルを革新した正岡子規。文学史上もっとも重要な俳人の一人ですが、彼がどのような俳句をつくっていたのかとなると、「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」「あたたかな雨が降るなり枯葎」などごく一部の代表句を除いてはよく知らない方が多いのではないでしょうか。彼の志を継承した高浜虚子が、その理念だけでなく俳句作品も含めて多く記憶されているのとは対照的に、明治という混沌とした、そして現代から遠く隔たった子規が、自らの信じる革新の実践として残した句の数々は、実際の読者が極めて少ないのが現状です。
本書は昭和11年生まれの著者が、令和3年度に慶應義塾大学文学部生として提出した卒業論文を元に刊行された、新しい子規論です。著者は自身が所属する国際俳句交流協会が中心となって推進している、俳句を世界文化遺産にしようという活動を挙げ、俳句が国際化している現状を意識しながら、季節感の異なる国がある以上、俳句を世界に広げることはできるのか、という問いから語りはじめます。そしてこの問題について考えるために、近代俳句の創始者である子規は季語をどのように考えていたのか、という問題に注目し、なかでも特に、子規の作品に多く見られる新事象・新題(新季語)の句を取り上げ、季語の役割を探ろうとします。
幕末の動乱、そして明治維新によって、それまで社会にはなかった新しい事象が次々に誕生しました。従来、勝峯晋風、村山古郷、加藤楸邨らが注目してきたように、明治時代の俳人たち、いわゆる旧派俳人たちはこれらの新事象を躊躇なく俳句に取り入れました。子規もこのような新しい俳句の題は意識しており、明治25年の「獺祭書屋俳話」で論じ、自身の実作にも取り入れていました。
著者の分析によれば、子規による新事象・新題の取り入れには何度かの変化があるようです。まず明治18年から24年まではほとんどこの種の俳句が見られず、しかし明治25年に84句を作って以降、その割合は最晩年まで増加しつづけます。明治28年までの時期については、他の旧派俳人同様、新事象を他の季語と取り合わせた句がほとんどで、新事象そのものを季語とする新題は〈人の世になりても久し紀元節〉と〈海晴れて天長節の日和かな〉の2句のみ、「当時既に新題(新季語)になっていたはずの「クリスマス」でさえ、他の季語と配合して作句されていた」といいます。
ところが明治29年以降は、「夏帽」「クリスマス」「夏休み」「毛布」「ストーブ」「外套」「焼芋」「ラムネ」「バナナ」といった新事象のみを季語として詠みこむ句が増加します。画期となったのは明治29年に詠んだ「夏帽」の連作です。
夏帽をかぶつて来たり探訪者
夏帽や吹き飛ばされて濠に落つ
夏帽の対なるをかぶり二三人
このように「夏帽」を季語とする句を中心としてまとめられた「夏帽十句」は、のちに門下の河東碧梧桐が「我等の俳句はこの夏帽から一転化、格段な進歩をして居る」(「ホトトギス」第5巻第12号、明治35年10月)と回想している通り、子規周辺の俳人たちにとって重要な試みとなりました。ただし、興味深いことに、その後明治32年以降の子規は、〈夏休ミ夜店ニ土産トトノヘテ〉等、新題に他の季語を取り合わせる句を積極的に詠むようになっていったようです。
著者はこうした実例を丹念に調査し、子規の自作ばかりでなく、子規が編んだ選集などにもあたりながら、明治という新しいものにあふれた時代を生きた子規が、それらを季語というルールの中でどのようにとらえようとしていたのかをあぶり出そうとします。そして、季語の歴史や必要性、国際俳句における季語の理解などについても、さまざまな俳人・研究者の見解を参照し、整理しながら読者に示そうとします。子規と新題というオールドでミクロな視点から国際俳句という現代的でマクロな問題を考えようという意欲的な論考です。(編集部)
-
09月30日
『神保町に銀漢亭があったころ』堀切克洋編 -
07月30日
『森は今』西池みどり句集 -
07月24日
『語りたい兜太 伝えたい兜太 13人の証言』董振華編 -
05月28日
『句集と小説 遙かなるマルキーズ諸島』マブソン青眼 -
05月21日
『俳句の国際化と季語 正岡子規の俳句観を基点に』桜かれん -
05月13日
『あやかり福』布施伊夜子句集 -
04月30日
『星野立子賞の十年』星野立子賞選考委員会編 -
04月23日
『雨滴』山西雅子句集 -
04月16日
『暦日』加藤喜代子句集 -
04月09日
『兜太を語る 海程15人と共に』董振華編 -
04月02日
『本当は逢いたし』池田澄子 -
03月26日
『俳句日記2012 瓦礫抄』小澤實 -
03月19日
『水と茶』斉藤志歩句集 -
03月12日
『花と夜盗』小津夜景句集 -
03月05日
『はだかむし』恩田侑布子句集 -
02月19日
『黛執全句集』 -
02月19日
『明日への触手』西池冬扇 -
02月12日
『ドナルド・キーンと俳句』毬矢まりえ -
02月12日
『芭蕉の風景』(上・下)小澤實